日本ワインコラム
THE CELLAR ワイン特集
長野・信州たかやまワイナリー
日本ワインコラム | 長野・信州たかやまワイナリー 「産地の形成」その役割を担うワイン生産者は数多くいるだろうし、あるいは、ほとんどの生産者がそうであるといっても過言ではないかもしれない。ワイン新興国の日本にとって、各地域がワイン生産地として確立されることが大きな目標で、それぞれの地域はそれぞれのやり方で、ワイン造りとその普及に励んでいる。そんな中で、「信州たかやまワイナリー」の鷹野さんは、おそらく最も現実的かつ建設的なかたちで、その活動に携わる人の中の一人だと感じる。 ▲ 高山村に醸造用葡萄を広めた第一人者佐藤宗一さんが栽培を担う角藤農園。 1996年より、醸造用の葡萄栽培が始まった高山村。「この地域でならば、世界に通用する葡萄が作れる」。隣接する地域で、長く醸造用葡萄の栽培に携わる角藤農園の佐藤宗一さんや、小布施ワイナリーによる熱心な働きかけによって、それは実現した。2004年には、村内外の意欲的な栽培家や有識者が中心となって、「高山村ワインぶどう研究会」が発足。前村長の協力もあり、遊休耕作地の再生をはじめ、海外研修など精力的な活動を続け、栽培面積は拡大。大手酒造メーカーへの葡萄の供給を行い、その品質は高く評価され、「高山村」のネームバリューは、大きな躍進を見せた。 鷹野さんが高山村の地を踏んだのは、そんな発展の最中だった。 山梨大学工学部発酵生産学科で学問を修めたのちに、大手酒造メーカーで醸造技術者として長くキャリアを積み、「高山村」の原料も多く扱った経験を持つ鷹野さん。 高山村は、そんな優れたキャリアを有する彼を、ワインに関する業務を専門的に行う任期付き職員として採用した。 ▲ ワイン醸造の専門職員として鷹野さんが務めた高山村役場。「まさかこの年で地方公務員になるとは思っていなかった」と鷹野さん。 ワイン産地としてのインフラを整えたいと思いました。"自然との対話"が必要とされる中で、肌感覚の情報も重要ではありますが、データと共に後世に残せるものとして、気象観測器の設置を考えました。 ▲ 信州たかやまワイナリーは、高山村の中でも比較的標高の高い傾斜地に位置している。 彼が任期中に取り組んだものとして、あげてくださったのが「ICT気象観測器の設置」だ。村内6箇所に設置された観測器は、気象データを収集、集積し、高山村の気候における特殊なキャラクターを示してくれた。 村内の葡萄畑が広がる領域だけでも、標高400~830mと高低差に富んだ地形である高山村。標高の低いところの気候区分はイタリア南部、高いところではシャンパ―ニュやドイツに相当する特異な土地であった。 「小さな地域 の中で、同じ品種でも酸の高低をはじめ、異なる味わいの個性を持った葡萄が取れるということは、大きなアドバンテージと言えます。 それらをアッサンブラージュしてワインを作ることが出来るのは、国内でも稀なケースと言えるかも知れません。」 栽培地の拡大や気象データの集積、栽培技術の向上など、「高山村ワインぶどう研究会」と自治体の取り組みにより、96年以降、醸造用葡萄栽培地として目覚ましい発展を遂げてきた高山村だが、依然それらの葡萄は外部のワイナリーへ供給される一途をたどっており、村内でのワインの生産は実現に至っていなかった。そんな中、「葡萄産地」から、「ワイン産地」へという新たなステージへの移行を志し、 13人の栽培家を中心に、酒販店や旅館などの出資によって、2016年、「信州たかやまワイナリー」は設立された。そのスローガンともいえるキーワードが、「ワイン産地の形成」だ。長野県というと、既に国内での認知も高く、「ワイン産地」と呼んで相違ないとも思われる地域ではあるが、まだまだ栽培から醸造、ワイナリー経営のノウハウを備えた人材を育成していく必要があり、現状5軒ある同村内のワイナリー数も更に増加していくことが見込まれる。。鷹野さんは、その先駆けとも言えるかたちで設立された「信州たかやまワイナリー」で、取締役執行役員、醸造責任者を努めている。 ▲ 高山村の中核ワイナリーたる「信州たかやまワイナリー」では、若いスタッフの方の姿も多く見られる。 ワイン産地の条件の一つとして、そこに優れたワインを造る複数のワイナリーがあることが欠かせません。このワイナリーの役割は、村内の原料からワインを製造する事は勿論として、複数のワイナリーの中核的な存在となること、そして今後ワイナリーの経営を担っていく人材の教育・育成という側面が大きくあります。 いままで訪問したワイナリーの中にも、研修生を受け入れている施設は多くあったが、農協出資や第三セクタ―とは別の形式で、地域のワイン産業の中核的な役割を担う「信州たかやまワイナリー」は、全国的にも稀有な存在と言えるかもしれない。 他方で「農家さんに選ばれた」、醸造のみを担うワイナリーとして、栽培家を尊重する姿勢が強く感じられる点も印象的だ。 「栽培者の飲みたいワイン。栽培者が思いを寄せることが出来る品種というものを彼ら自身が選んでいます。客観的な選択よりも、好きか嫌いかというような思いの乗った選択のほうが、よりいいものが出来ると考えています。」 「また収穫のタイミングの決断は、農家さんの想いを繋ぐために重要な工程です。そのため常に、栽培者と醸造家がクロスする、我々が畑に出向き、状況を実際に感じることで、両者が同じ視点で話を出来るようなプロセスを踏んでいます。」 鷹野さんが醸造を担う者として、その醸造工程の設計やその衛生管理における細やかな気配りも、再度意識してみると緻密で、システマティックに機能しているように思われる。「ワイナリーの役割は、"葡萄畑と食卓とを繋げる、そのための設え"だと思っています。そのために、まず蔵の中でワインが侵されないことが非常に重要です。」...
長野・信州たかやまワイナリー
日本ワインコラム | 長野・信州たかやまワイナリー 「産地の形成」その役割を担うワイン生産者は数多くいるだろうし、あるいは、ほとんどの生産者がそうであるといっても過言ではないかもしれない。ワイン新興国の日本にとって、各地域がワイン生産地として確立されることが大きな目標で、それぞれの地域はそれぞれのやり方で、ワイン造りとその普及に励んでいる。そんな中で、「信州たかやまワイナリー」の鷹野さんは、おそらく最も現実的かつ建設的なかたちで、その活動に携わる人の中の一人だと感じる。 ▲ 高山村に醸造用葡萄を広めた第一人者佐藤宗一さんが栽培を担う角藤農園。 1996年より、醸造用の葡萄栽培が始まった高山村。「この地域でならば、世界に通用する葡萄が作れる」。隣接する地域で、長く醸造用葡萄の栽培に携わる角藤農園の佐藤宗一さんや、小布施ワイナリーによる熱心な働きかけによって、それは実現した。2004年には、村内外の意欲的な栽培家や有識者が中心となって、「高山村ワインぶどう研究会」が発足。前村長の協力もあり、遊休耕作地の再生をはじめ、海外研修など精力的な活動を続け、栽培面積は拡大。大手酒造メーカーへの葡萄の供給を行い、その品質は高く評価され、「高山村」のネームバリューは、大きな躍進を見せた。 鷹野さんが高山村の地を踏んだのは、そんな発展の最中だった。 山梨大学工学部発酵生産学科で学問を修めたのちに、大手酒造メーカーで醸造技術者として長くキャリアを積み、「高山村」の原料も多く扱った経験を持つ鷹野さん。 高山村は、そんな優れたキャリアを有する彼を、ワインに関する業務を専門的に行う任期付き職員として採用した。 ▲ ワイン醸造の専門職員として鷹野さんが務めた高山村役場。「まさかこの年で地方公務員になるとは思っていなかった」と鷹野さん。 ワイン産地としてのインフラを整えたいと思いました。"自然との対話"が必要とされる中で、肌感覚の情報も重要ではありますが、データと共に後世に残せるものとして、気象観測器の設置を考えました。 ▲ 信州たかやまワイナリーは、高山村の中でも比較的標高の高い傾斜地に位置している。 彼が任期中に取り組んだものとして、あげてくださったのが「ICT気象観測器の設置」だ。村内6箇所に設置された観測器は、気象データを収集、集積し、高山村の気候における特殊なキャラクターを示してくれた。 村内の葡萄畑が広がる領域だけでも、標高400~830mと高低差に富んだ地形である高山村。標高の低いところの気候区分はイタリア南部、高いところではシャンパ―ニュやドイツに相当する特異な土地であった。 「小さな地域 の中で、同じ品種でも酸の高低をはじめ、異なる味わいの個性を持った葡萄が取れるということは、大きなアドバンテージと言えます。 それらをアッサンブラージュしてワインを作ることが出来るのは、国内でも稀なケースと言えるかも知れません。」 栽培地の拡大や気象データの集積、栽培技術の向上など、「高山村ワインぶどう研究会」と自治体の取り組みにより、96年以降、醸造用葡萄栽培地として目覚ましい発展を遂げてきた高山村だが、依然それらの葡萄は外部のワイナリーへ供給される一途をたどっており、村内でのワインの生産は実現に至っていなかった。そんな中、「葡萄産地」から、「ワイン産地」へという新たなステージへの移行を志し、 13人の栽培家を中心に、酒販店や旅館などの出資によって、2016年、「信州たかやまワイナリー」は設立された。そのスローガンともいえるキーワードが、「ワイン産地の形成」だ。長野県というと、既に国内での認知も高く、「ワイン産地」と呼んで相違ないとも思われる地域ではあるが、まだまだ栽培から醸造、ワイナリー経営のノウハウを備えた人材を育成していく必要があり、現状5軒ある同村内のワイナリー数も更に増加していくことが見込まれる。。鷹野さんは、その先駆けとも言えるかたちで設立された「信州たかやまワイナリー」で、取締役執行役員、醸造責任者を努めている。 ▲ 高山村の中核ワイナリーたる「信州たかやまワイナリー」では、若いスタッフの方の姿も多く見られる。 ワイン産地の条件の一つとして、そこに優れたワインを造る複数のワイナリーがあることが欠かせません。このワイナリーの役割は、村内の原料からワインを製造する事は勿論として、複数のワイナリーの中核的な存在となること、そして今後ワイナリーの経営を担っていく人材の教育・育成という側面が大きくあります。 いままで訪問したワイナリーの中にも、研修生を受け入れている施設は多くあったが、農協出資や第三セクタ―とは別の形式で、地域のワイン産業の中核的な役割を担う「信州たかやまワイナリー」は、全国的にも稀有な存在と言えるかもしれない。 他方で「農家さんに選ばれた」、醸造のみを担うワイナリーとして、栽培家を尊重する姿勢が強く感じられる点も印象的だ。 「栽培者の飲みたいワイン。栽培者が思いを寄せることが出来る品種というものを彼ら自身が選んでいます。客観的な選択よりも、好きか嫌いかというような思いの乗った選択のほうが、よりいいものが出来ると考えています。」 「また収穫のタイミングの決断は、農家さんの想いを繋ぐために重要な工程です。そのため常に、栽培者と醸造家がクロスする、我々が畑に出向き、状況を実際に感じることで、両者が同じ視点で話を出来るようなプロセスを踏んでいます。」 鷹野さんが醸造を担う者として、その醸造工程の設計やその衛生管理における細やかな気配りも、再度意識してみると緻密で、システマティックに機能しているように思われる。「ワイナリーの役割は、"葡萄畑と食卓とを繋げる、そのための設え"だと思っています。そのために、まず蔵の中でワインが侵されないことが非常に重要です。」...

山梨・ダイヤモンド酒造
日本ワインコラム | 山梨 ダイヤモンド酒造 住宅地に佇むごく一般的な建築物。 一瞥してワイナリーらしい雰囲気はなく、むしろ、街の内科クリニックのような風体。多くの注意を惹きつけるような勇んだ姿勢を感じない看板くらいが、ここがワイナリーであることを教えてくれる。ダイヤモンド酒造。日本でも指折りのマスカット・ベーリーAの赤ワインを送り出す、山梨県随一のワイナリー。その地位に登り詰めた雨宮吉男さんは、マスクをしていること以外にほとんど外交的な要素を纏わぬ、ノーガードなスタイルで現れた。農作業の途中の人ならまだしも。 そして思った。多分その辺はどうでもいいのだ。 ▲ 筆者自身も桜をバックにおじさん2人のツーショットを取ったのは初めてだったが、撮られたほうも初めてだったのではなかろうか。ともあれ、中々趣のあるショット。 「勝沼は他の町に比べると、夜温が下がりやすいんです。「笹子おろし」と言って、笹子峠から夕方風が吹き下ろしてくるんです。だから、隣町の人は「勝沼って、夕方涼しいね。」って言うんです。でも、最近は気候が変わってきていて、あまり風が吹かなくなりました。 土壌は砂っぽくて、影響している山や川砂の影響が強いので水捌けがいい。 ▲ 契約農家の葡萄畑。「なんもないでしょ。」と言われたらそうなのですが、勝沼の砂っぽい土壌を識別いただけるだろうか。 最近はマグヴィスワイナリーさんが土壌分析をしていますが、今まではそう言ったことはやってなくて、何となくそういうものだろうという形でした。 なので、彼らの分析によって変わってくるところもあるのだろうと思います。 対して、(ダイヤモンド酒造の原料の)マスカット・ベーリーAが植えられている穂坂は、完全に粘土質です。なので、赤ワイン用品種に適している。「勝沼は甲府盆地の東の縁なので、朝日が遅くて夕日が長い。穂坂は盆地の西の縁。日の当たり方が真逆なんです。朝日が早くて夕日が短い。」 山梨県甲州市勝沼、果樹栽培のみならず、国内産ワインの発祥の地として知られる土地で、ダイヤモンド酒造はワイン造りを行なっている。 元々は、近隣の農家がそれぞれの葡萄を持ち寄ってワインをつくる自家醸造施設であったが、生産量が増えたことによって金銭のやりとりが発生すようになると、税務署指導もあって、雨宮家が酒造の権利を農家から買い取り、有限会社化。のちに株式会社化を果たし、現在にいたる。現当主の雨宮吉男さんは、勝沼や穂坂の契約農家からの葡萄を使って、ワイン造りを行なっている。 契約栽培先を選ぶなんてのは中々できないですよね。何かしらの人としての関係性もありますから。甲州に関しては一律の値段で買っていますが、ベーリーAに関しては、畑でできたワインのクオリティで葡萄の値段を決めているので、農協の30-100%増しくらいの値段になるんですが、そういった価格での差別化はしていますけどね。 買い葡萄のみを使用する、無理やりフランス風に言えば、ネゴシアン的なスタイルのダイヤモンド酒造。自身の理想のスタイルに近づくため、マスカット・ベーリーAの究極を目指すため、多くの注文をつけるのではなかろうか、とも思ったが、実のところはそうではない。 兼業農家や家族経営が多い中、雨宮さんが一人で各契約栽培先をコントロールすることは不可能であるし、産業としての構造がやはり山梨県とブルゴーニュでは、大きく異なる。この後引用されるデュジャックはそのネゴシアンブランドで契約農家の畑に強く介入することで有名だが、それに関するシンプルな疑問はやや筋違いということで解消しておく。そんなことが頭をよぎったのは筆者だけかもしれないが。 ▲ リーファーコンテナは古いので、冷却用にエアコンの室外機が繋がれている。 「農家さん達もどうしたらいいか、とか助言を求めることはあるので、こういう風にしたほうがいいんじゃないですか、というアドバイスをすることはあります。粘土質だと栄養素が抜けないので、肥料に関しても、最初からたくさん撒くよりも、足りなくなったら葉面散布で足せばいいということや、大きな房に価値がある生食と、コンパクトで凝縮した葡萄に価値がある醸造では考え方が大きく異なるので、摘房などに関して、こうしたらいい、ああしたらいい、は言います。 昔、ブルゴーニュのデュジャックに行った時に思ったのですが、デュジャックってモレサンド二の生産者ですが、ヴォーヌロマネの畑持ってるじゃないですか。でも、飲み比べてみるとモレサンドニの方が美味しいんですよ。それはやっぱり、元々モレサンドニの生産者だからかな、と思っていて。勝沼の人間が穂坂の人間にあんまりいうのは良くない。その人たちの方が土地をわかっているということだから、と考えています。」 ▲ 「リーファーコンテナを使って」とおっしゃっていたので、同機能の何かかと思ったが、本当にリーファーコンテナだ。 必ずしも意図的でないにしても、栽培に関しての自身の介入が少ない。雨宮さんが造るワインに対する評価は、醸造に多くのリソースを注ぐ、まさに醸造家としての彼の実力に与えられたものだろう。しかし、 (マスカット・ベーリーAに関しては) ちんたらやることですね。...
山梨・ダイヤモンド酒造
日本ワインコラム | 山梨 ダイヤモンド酒造 住宅地に佇むごく一般的な建築物。 一瞥してワイナリーらしい雰囲気はなく、むしろ、街の内科クリニックのような風体。多くの注意を惹きつけるような勇んだ姿勢を感じない看板くらいが、ここがワイナリーであることを教えてくれる。ダイヤモンド酒造。日本でも指折りのマスカット・ベーリーAの赤ワインを送り出す、山梨県随一のワイナリー。その地位に登り詰めた雨宮吉男さんは、マスクをしていること以外にほとんど外交的な要素を纏わぬ、ノーガードなスタイルで現れた。農作業の途中の人ならまだしも。 そして思った。多分その辺はどうでもいいのだ。 ▲ 筆者自身も桜をバックにおじさん2人のツーショットを取ったのは初めてだったが、撮られたほうも初めてだったのではなかろうか。ともあれ、中々趣のあるショット。 「勝沼は他の町に比べると、夜温が下がりやすいんです。「笹子おろし」と言って、笹子峠から夕方風が吹き下ろしてくるんです。だから、隣町の人は「勝沼って、夕方涼しいね。」って言うんです。でも、最近は気候が変わってきていて、あまり風が吹かなくなりました。 土壌は砂っぽくて、影響している山や川砂の影響が強いので水捌けがいい。 ▲ 契約農家の葡萄畑。「なんもないでしょ。」と言われたらそうなのですが、勝沼の砂っぽい土壌を識別いただけるだろうか。 最近はマグヴィスワイナリーさんが土壌分析をしていますが、今まではそう言ったことはやってなくて、何となくそういうものだろうという形でした。 なので、彼らの分析によって変わってくるところもあるのだろうと思います。 対して、(ダイヤモンド酒造の原料の)マスカット・ベーリーAが植えられている穂坂は、完全に粘土質です。なので、赤ワイン用品種に適している。「勝沼は甲府盆地の東の縁なので、朝日が遅くて夕日が長い。穂坂は盆地の西の縁。日の当たり方が真逆なんです。朝日が早くて夕日が短い。」 山梨県甲州市勝沼、果樹栽培のみならず、国内産ワインの発祥の地として知られる土地で、ダイヤモンド酒造はワイン造りを行なっている。 元々は、近隣の農家がそれぞれの葡萄を持ち寄ってワインをつくる自家醸造施設であったが、生産量が増えたことによって金銭のやりとりが発生すようになると、税務署指導もあって、雨宮家が酒造の権利を農家から買い取り、有限会社化。のちに株式会社化を果たし、現在にいたる。現当主の雨宮吉男さんは、勝沼や穂坂の契約農家からの葡萄を使って、ワイン造りを行なっている。 契約栽培先を選ぶなんてのは中々できないですよね。何かしらの人としての関係性もありますから。甲州に関しては一律の値段で買っていますが、ベーリーAに関しては、畑でできたワインのクオリティで葡萄の値段を決めているので、農協の30-100%増しくらいの値段になるんですが、そういった価格での差別化はしていますけどね。 買い葡萄のみを使用する、無理やりフランス風に言えば、ネゴシアン的なスタイルのダイヤモンド酒造。自身の理想のスタイルに近づくため、マスカット・ベーリーAの究極を目指すため、多くの注文をつけるのではなかろうか、とも思ったが、実のところはそうではない。 兼業農家や家族経営が多い中、雨宮さんが一人で各契約栽培先をコントロールすることは不可能であるし、産業としての構造がやはり山梨県とブルゴーニュでは、大きく異なる。この後引用されるデュジャックはそのネゴシアンブランドで契約農家の畑に強く介入することで有名だが、それに関するシンプルな疑問はやや筋違いということで解消しておく。そんなことが頭をよぎったのは筆者だけかもしれないが。 ▲ リーファーコンテナは古いので、冷却用にエアコンの室外機が繋がれている。 「農家さん達もどうしたらいいか、とか助言を求めることはあるので、こういう風にしたほうがいいんじゃないですか、というアドバイスをすることはあります。粘土質だと栄養素が抜けないので、肥料に関しても、最初からたくさん撒くよりも、足りなくなったら葉面散布で足せばいいということや、大きな房に価値がある生食と、コンパクトで凝縮した葡萄に価値がある醸造では考え方が大きく異なるので、摘房などに関して、こうしたらいい、ああしたらいい、は言います。 昔、ブルゴーニュのデュジャックに行った時に思ったのですが、デュジャックってモレサンド二の生産者ですが、ヴォーヌロマネの畑持ってるじゃないですか。でも、飲み比べてみるとモレサンドニの方が美味しいんですよ。それはやっぱり、元々モレサンドニの生産者だからかな、と思っていて。勝沼の人間が穂坂の人間にあんまりいうのは良くない。その人たちの方が土地をわかっているということだから、と考えています。」 ▲ 「リーファーコンテナを使って」とおっしゃっていたので、同機能の何かかと思ったが、本当にリーファーコンテナだ。 必ずしも意図的でないにしても、栽培に関しての自身の介入が少ない。雨宮さんが造るワインに対する評価は、醸造に多くのリソースを注ぐ、まさに醸造家としての彼の実力に与えられたものだろう。しかし、 (マスカット・ベーリーAに関しては) ちんたらやることですね。...

山梨・くらむぼんワイン
日本ワインコラム | 山梨 くらむぼんワイン 「一番の転機は、フランスへ行ったことです。23歳の時に留学をしました。当時は、家業を継ぐこともあまり考えていなくて、弟がいるので、どちらかが継ぐのだろうなぁ、といったような認識でした。」 アイルトン・セナに憧れて、慶応大学理工学部にまで入り、ゆくゆくはルノーでのエンジニアリングライフを見据えていたかどうかは存じ上げないが、ともあれ、野沢たかひこさんは、FW16程に不安定な大学時代に、学歴社会をコースアウトして、南仏へ飛び立った。 ▲ 「森の香りがするんです。」と、自社畑の土を香る野沢さん。わざわざポーズを決めていただいたのに、普通の写真ですみません。レンズ変えるべきでした。 「ニースのホームステイ先で、ワインを毎日出してくれて、それでワインを初めて美味しいと感じました。それまで、日本に美味しいワインってあまりなかったんですよね。元々は親の仕事にも興味がなくワインには関心がなかったのですが、フランスで体験した、家族や友達が集まり、ワインを中心にして人間関係とかが広まっていく、ということを地元の山梨でもやれたらなぁ、と思いました。 大学時代は、授業にも出ていなかったのですが、フランスに行ったら新しい人生の始まりという感じでした。」 煌びやかなニューライフ。周りには、自分のことを知っているものなど誰もいない。地中海を臨み、国籍の違う仲間たちと、夜な夜なワインをボトルで回し飲みする、スーパーモラトリアムな日々。そんな語学学校生活を経て、野沢さんは、ブルゴーニュのCFPPA(ボーヌ農業促進・職業訓練センター)でディプロマを得た。 ▲ 終始朗らかにご対応くださった野沢さん。お迎えいただきありがとうございました。 しかし、意外にも彼が最も影響を受けた生産者として、名前を挙げるのは 「Domaine de Souch」、1987年創業という異端な歴史を持ちながら、ジュランソンを代表すると評される生産者だ。 彼女は夫亡き後、60歳代でワイン造りを始めた、ビオディナミの先駆者の一人 です。彼女の造る「Jurancon sec(辛口)」や「moelleux(甘口)」をタンクから試飲させていただいた時、そのあまりにピュアで、土地の花や土の風味に溢れ、自然な風味でそして幸せな余韻も永く続くワインに、とにかく圧倒されました。これこそがテロワール、いやブドウがある風土がそのままワインに出ていると。もちろん、彼女の人柄がワインに表れていたのは言うまでもありません。 広大な敷地に、荘厳かつ柔らかい空気纏って佇む、養蚕農家を移築したという日本家屋の母屋が印象的な『くらむぼんワイン』。自家醸造の酒蔵として大正2年に創業した同社は、協同組合となって近隣の農家の葡萄からワインを醸造。 ▲ 吹き付ける強風に「ガタガタ」と大きな音を立てる母屋の縁側。夜中にトイレへ行くときは物凄い恐怖感だそうです。 昭和37年から、農家の株を買い取り「有限会社山梨ワイン醸造」が設立。後に株式会社化を経て、2014年、『株式会社くらむぼんワイン』と社名変更がなされた。 野沢たかひこさんは、同社の三代目に当たる。 「フランスから帰国してワイナリーで働き始めた当初は、日本のような雨が多い 気候では農薬を効果的に散布しなければブドウの収穫が出来ないと考えて、叢生 栽培は行っていましたが、化学農薬・肥料は普通に使っていました。」 そういった、謂わば「農家として普通の栽培」を行っていた野沢さんが出会ったのが、福岡正信著作の「自然農法 藁一本の革命」だった。...
山梨・くらむぼんワイン
日本ワインコラム | 山梨 くらむぼんワイン 「一番の転機は、フランスへ行ったことです。23歳の時に留学をしました。当時は、家業を継ぐこともあまり考えていなくて、弟がいるので、どちらかが継ぐのだろうなぁ、といったような認識でした。」 アイルトン・セナに憧れて、慶応大学理工学部にまで入り、ゆくゆくはルノーでのエンジニアリングライフを見据えていたかどうかは存じ上げないが、ともあれ、野沢たかひこさんは、FW16程に不安定な大学時代に、学歴社会をコースアウトして、南仏へ飛び立った。 ▲ 「森の香りがするんです。」と、自社畑の土を香る野沢さん。わざわざポーズを決めていただいたのに、普通の写真ですみません。レンズ変えるべきでした。 「ニースのホームステイ先で、ワインを毎日出してくれて、それでワインを初めて美味しいと感じました。それまで、日本に美味しいワインってあまりなかったんですよね。元々は親の仕事にも興味がなくワインには関心がなかったのですが、フランスで体験した、家族や友達が集まり、ワインを中心にして人間関係とかが広まっていく、ということを地元の山梨でもやれたらなぁ、と思いました。 大学時代は、授業にも出ていなかったのですが、フランスに行ったら新しい人生の始まりという感じでした。」 煌びやかなニューライフ。周りには、自分のことを知っているものなど誰もいない。地中海を臨み、国籍の違う仲間たちと、夜な夜なワインをボトルで回し飲みする、スーパーモラトリアムな日々。そんな語学学校生活を経て、野沢さんは、ブルゴーニュのCFPPA(ボーヌ農業促進・職業訓練センター)でディプロマを得た。 ▲ 終始朗らかにご対応くださった野沢さん。お迎えいただきありがとうございました。 しかし、意外にも彼が最も影響を受けた生産者として、名前を挙げるのは 「Domaine de Souch」、1987年創業という異端な歴史を持ちながら、ジュランソンを代表すると評される生産者だ。 彼女は夫亡き後、60歳代でワイン造りを始めた、ビオディナミの先駆者の一人 です。彼女の造る「Jurancon sec(辛口)」や「moelleux(甘口)」をタンクから試飲させていただいた時、そのあまりにピュアで、土地の花や土の風味に溢れ、自然な風味でそして幸せな余韻も永く続くワインに、とにかく圧倒されました。これこそがテロワール、いやブドウがある風土がそのままワインに出ていると。もちろん、彼女の人柄がワインに表れていたのは言うまでもありません。 広大な敷地に、荘厳かつ柔らかい空気纏って佇む、養蚕農家を移築したという日本家屋の母屋が印象的な『くらむぼんワイン』。自家醸造の酒蔵として大正2年に創業した同社は、協同組合となって近隣の農家の葡萄からワインを醸造。 ▲ 吹き付ける強風に「ガタガタ」と大きな音を立てる母屋の縁側。夜中にトイレへ行くときは物凄い恐怖感だそうです。 昭和37年から、農家の株を買い取り「有限会社山梨ワイン醸造」が設立。後に株式会社化を経て、2014年、『株式会社くらむぼんワイン』と社名変更がなされた。 野沢たかひこさんは、同社の三代目に当たる。 「フランスから帰国してワイナリーで働き始めた当初は、日本のような雨が多い 気候では農薬を効果的に散布しなければブドウの収穫が出来ないと考えて、叢生 栽培は行っていましたが、化学農薬・肥料は普通に使っていました。」 そういった、謂わば「農家として普通の栽培」を行っていた野沢さんが出会ったのが、福岡正信著作の「自然農法 藁一本の革命」だった。...

山梨・機山洋酒工業
日本ワインコラム | 山梨 機山洋酒工業 「こだわりってね、僕はないんですよ。 若い頃なんか取材でこだわりはなんですかなんて聞かれると、頭にきて、帰れ、とか言っちゃったりしてね。」 率直にいう。私は困った。 ▲ 機山洋酒工業の何から何までをお二人で手掛ける土屋ご夫妻。同じ大学を出られて、国税庁醸造試験所でもご一緒だったそうです。 日本ワインへの造詣が深くないことを半ばコンプレックス気味に自負している筆者にとって、生産者の方々の「こだわり」は、コラムを書く上で、最も容易かつ明解かつ差別化しやすく、深掘りしやすい大事な切り口である。だから、私は洗練されていようが歪であろうが、「こだわり」を要請してきた。 ▲ 気さくに取材に応じてくださった土屋さん。時折挟まれる「いい話でしょ~!?」という念押しが記憶に残っています。筆者は果たして、「いい話」を、いい話として書き下せたのだろうか。 こだわりって、元々の意味で言うと「とらわれている」ような否定的な意味だと思うのですが、僕には、どうしてもこうじゃないといけないってものがないんですよ。例えば「甲州に拘っているじゃないか」と言われることもあるのですが、それは拘っているわけではありません。(気候土壌への適性だけでなく、歴史的な背景など)あらゆる意味合いで、甲州より優れた品種があるのなら、それは変えていきますよ。今、それがないというだけです。 「スマート」というと軽いだろうか、「理知的」というと形式ばって響くだろうか、軽快に慎重に、外交的に内省的に、朗らかに強かに。 その軽微なアンビバテントは、彼が作るワインにも通底したものがあるような気がしている。安いのに旨い、という話ではない。工業的な緻密性で、クラフト的なテイを有しているという意味においてだ。 ▲ フンコロガシをデザインした、かつての機山洋酒工業のエンブレム 山梨県甲州市塩山。日本三大急流にも数えられる富士川へと流れ込む笛吹川の脇、機山洋酒工業は、北東から南西に太平洋へ向かうこの一級河川によって形成された河岸段丘の上に位置するワイナリーだ。 「(先々代は)元々、石炭業を営んでいました。というのも、山梨においては養蚕が盛んな地域で製糸工業が重要な産業でした。絹糸を手繰る際に高温の水が必要なのですが、その熱源となったのが石炭だったのです。」 石炭業からワイン製造への転換の契機となったのは、昭和5年の世界恐慌。世界経済が急激に冷え込んだことによって、輸出産業としての比重が大きかった製糸工業は衰退し、石炭の需要も急落した。 ▲ 直売スペースには、ワインボトルから造られたグラスやミニボトルがしつらえられている。 そういった状況で、養蚕に代わる産業として注目を集めたのがワイン造りでした。 先々代もその産業の遷移の流れに乗り、ワイン造りを始めた。当時3,000もの零細生産者が生まれるほどに勃興したワイン産業だが、その殆どが今は見る影もない。その中で生き残り、現在まで引き継がれているのが機山洋酒工業だ。 三代目の土屋幸三さんは、メーカーの研究員としての6年のキャリアを経て、1994年の8月に会社を辞め、ワイン造りの家業を継いだ。 元々は街の電気屋さんになりたかったので、(大学は)電気とか通信の学科に行こうと思っていました。ですが、父にその話をすると、 「お前、後継ぐんだろ。」なんて言われてしまいまして。「ダメ」っていうならしょうがないなぁ、なんて思いながら調べたら、その当時は、電気通信の学科と醗酵学科の二次試験の科目が同じだったのです。 1980年代のバイオテクノロジー・ブーム。石油・石炭を燃料・原料とした大量消費と爆発的な成長から、微生物や遺伝子組み替えを媒介した、クリーンで省エネルギーな、より緻密な科学によって興される未来が描かれた時代だ。「アマチュア無線免許」まで取得していた電子工作青年だったという土屋さんだが、その時代を象徴すると言える大阪大学醗酵学科で学問を修め、バイオケミカル事業を手がける企業へ就職した。 ▲ こんなにお値打ちで、こんなに美味しいのですが、まだまだ整然に積み重ねられた在庫が。...
山梨・機山洋酒工業
日本ワインコラム | 山梨 機山洋酒工業 「こだわりってね、僕はないんですよ。 若い頃なんか取材でこだわりはなんですかなんて聞かれると、頭にきて、帰れ、とか言っちゃったりしてね。」 率直にいう。私は困った。 ▲ 機山洋酒工業の何から何までをお二人で手掛ける土屋ご夫妻。同じ大学を出られて、国税庁醸造試験所でもご一緒だったそうです。 日本ワインへの造詣が深くないことを半ばコンプレックス気味に自負している筆者にとって、生産者の方々の「こだわり」は、コラムを書く上で、最も容易かつ明解かつ差別化しやすく、深掘りしやすい大事な切り口である。だから、私は洗練されていようが歪であろうが、「こだわり」を要請してきた。 ▲ 気さくに取材に応じてくださった土屋さん。時折挟まれる「いい話でしょ~!?」という念押しが記憶に残っています。筆者は果たして、「いい話」を、いい話として書き下せたのだろうか。 こだわりって、元々の意味で言うと「とらわれている」ような否定的な意味だと思うのですが、僕には、どうしてもこうじゃないといけないってものがないんですよ。例えば「甲州に拘っているじゃないか」と言われることもあるのですが、それは拘っているわけではありません。(気候土壌への適性だけでなく、歴史的な背景など)あらゆる意味合いで、甲州より優れた品種があるのなら、それは変えていきますよ。今、それがないというだけです。 「スマート」というと軽いだろうか、「理知的」というと形式ばって響くだろうか、軽快に慎重に、外交的に内省的に、朗らかに強かに。 その軽微なアンビバテントは、彼が作るワインにも通底したものがあるような気がしている。安いのに旨い、という話ではない。工業的な緻密性で、クラフト的なテイを有しているという意味においてだ。 ▲ フンコロガシをデザインした、かつての機山洋酒工業のエンブレム 山梨県甲州市塩山。日本三大急流にも数えられる富士川へと流れ込む笛吹川の脇、機山洋酒工業は、北東から南西に太平洋へ向かうこの一級河川によって形成された河岸段丘の上に位置するワイナリーだ。 「(先々代は)元々、石炭業を営んでいました。というのも、山梨においては養蚕が盛んな地域で製糸工業が重要な産業でした。絹糸を手繰る際に高温の水が必要なのですが、その熱源となったのが石炭だったのです。」 石炭業からワイン製造への転換の契機となったのは、昭和5年の世界恐慌。世界経済が急激に冷え込んだことによって、輸出産業としての比重が大きかった製糸工業は衰退し、石炭の需要も急落した。 ▲ 直売スペースには、ワインボトルから造られたグラスやミニボトルがしつらえられている。 そういった状況で、養蚕に代わる産業として注目を集めたのがワイン造りでした。 先々代もその産業の遷移の流れに乗り、ワイン造りを始めた。当時3,000もの零細生産者が生まれるほどに勃興したワイン産業だが、その殆どが今は見る影もない。その中で生き残り、現在まで引き継がれているのが機山洋酒工業だ。 三代目の土屋幸三さんは、メーカーの研究員としての6年のキャリアを経て、1994年の8月に会社を辞め、ワイン造りの家業を継いだ。 元々は街の電気屋さんになりたかったので、(大学は)電気とか通信の学科に行こうと思っていました。ですが、父にその話をすると、 「お前、後継ぐんだろ。」なんて言われてしまいまして。「ダメ」っていうならしょうがないなぁ、なんて思いながら調べたら、その当時は、電気通信の学科と醗酵学科の二次試験の科目が同じだったのです。 1980年代のバイオテクノロジー・ブーム。石油・石炭を燃料・原料とした大量消費と爆発的な成長から、微生物や遺伝子組み替えを媒介した、クリーンで省エネルギーな、より緻密な科学によって興される未来が描かれた時代だ。「アマチュア無線免許」まで取得していた電子工作青年だったという土屋さんだが、その時代を象徴すると言える大阪大学醗酵学科で学問を修め、バイオケミカル事業を手がける企業へ就職した。 ▲ こんなにお値打ちで、こんなに美味しいのですが、まだまだ整然に積み重ねられた在庫が。...

栃木・ココファーム・ワイナリー
日本ワインコラム | 関東・栃木 ココ・ファーム・ワイナリー 我々は一般に 「優れた葡萄産地にあるワイナリーで、優れたワインは造られる。」 と考えることを好む傾向にある。 「ロンドンにある自社畑のリースリングからワイン造りました。」 「ブルゴーニュのピノ・ノワールをパリで醸造しました。」 なんて言われても、なんだか得心がいかない。どんなに完璧な味わいでも、「何か入れてるんじゃないの?」なんて不確かなことを言い始めるのがオチで、どうにも腑に落ちないのである。おそらく。 ▲ 急斜面・強風という状況下でも、こころみ学園の園生は休まず畑に立っている。 欧州を例に出した。日本の場合はどうだろう。 「北海道の葡萄を北海道でワインにしました。」 「山形県の葡萄を山形県でワインにしました。」 いわゆるドメーヌだ。 優れた産地が生んだ葡萄が、その優れた産地でワインになる。 では、これはどうだろう。 「北海道の葡萄を栃木県でワインにする。」 「山梨県の葡萄を栃木県でワインにする。」 栃木県は北関東で、山梨県は中部、あるいは南関東で、北海道は言うまでもない。パリとブルゴーニュの距離の例はさほど大袈裟ではない。 これはどうか。 「栃木県の葡萄を栃木県でワインにする。」 ▲ 元々は松が自生するようなやせた土壌を、川田昇さんが切り拓いた。 栃木県が葡萄の産地として知られているかといえばそうではない。ロンドンの例は流石に誇張だが、実際に葡萄生産量では全国上位10番までにも入っていない。名産と言えば「とちおとめ」「餃子」「レモン牛乳」。「とちおとめ」は果実だが葡萄ではないし、「餃子」は皮と身があっても果実じゃない。「レモン牛乳」はもうよくわからない。 ▲ リースリング・リオンとは思えないほどの厚みと奥行をもった「 のぼ ブリュット...
栃木・ココファーム・ワイナリー
日本ワインコラム | 関東・栃木 ココ・ファーム・ワイナリー 我々は一般に 「優れた葡萄産地にあるワイナリーで、優れたワインは造られる。」 と考えることを好む傾向にある。 「ロンドンにある自社畑のリースリングからワイン造りました。」 「ブルゴーニュのピノ・ノワールをパリで醸造しました。」 なんて言われても、なんだか得心がいかない。どんなに完璧な味わいでも、「何か入れてるんじゃないの?」なんて不確かなことを言い始めるのがオチで、どうにも腑に落ちないのである。おそらく。 ▲ 急斜面・強風という状況下でも、こころみ学園の園生は休まず畑に立っている。 欧州を例に出した。日本の場合はどうだろう。 「北海道の葡萄を北海道でワインにしました。」 「山形県の葡萄を山形県でワインにしました。」 いわゆるドメーヌだ。 優れた産地が生んだ葡萄が、その優れた産地でワインになる。 では、これはどうだろう。 「北海道の葡萄を栃木県でワインにする。」 「山梨県の葡萄を栃木県でワインにする。」 栃木県は北関東で、山梨県は中部、あるいは南関東で、北海道は言うまでもない。パリとブルゴーニュの距離の例はさほど大袈裟ではない。 これはどうか。 「栃木県の葡萄を栃木県でワインにする。」 ▲ 元々は松が自生するようなやせた土壌を、川田昇さんが切り拓いた。 栃木県が葡萄の産地として知られているかといえばそうではない。ロンドンの例は流石に誇張だが、実際に葡萄生産量では全国上位10番までにも入っていない。名産と言えば「とちおとめ」「餃子」「レモン牛乳」。「とちおとめ」は果実だが葡萄ではないし、「餃子」は皮と身があっても果実じゃない。「レモン牛乳」はもうよくわからない。 ▲ リースリング・リオンとは思えないほどの厚みと奥行をもった「 のぼ ブリュット...
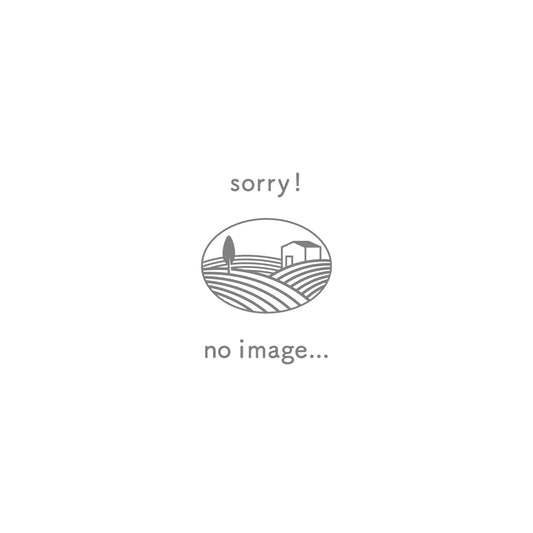
中四国のワイナリー
中四国のワイナリー 中四国はワインの産地としてはそれほど名が通っていないかもしれません。しかし現在、このエリアの9県全てで日本ワインが生産されています。 この中で最も生産量が多いのが岡山県。元々、ハウス栽培の生食用マスカットで定評のある県で、大手ビールメーカーのワイナリーもありますが、 現在は新見市などの内陸部にワイナリーの設立が続いています。 中でも日本では珍しいテラロッサの土壌でぶどうを栽培するDomaine Tettaは海外からも注目されており、ナチュラルなアプローチで滋味深いワインを生むコルトラーダなども興味深いワインをつくります。 倉敷市のGRAPE SHIPなど、元々の名産であるマスカット・オブ・アレキサンドリアを活かしたワインづくりを行う生産者も出て来ています。 お隣の広島県でも内陸部を中心にワインが生産されています。広島三次ワイナリーが有名ですが、他にも海外のコンクールで金賞を受賞するようなワイナリーも登場して来ています。広島県の内陸部は高品質なシャルドネに定評があります。山陰側では島根県が独自の魅力を放っています。実は山梨県の次に甲州の生産量が多い都道府県は島根県(とは言え全国シェア2.5%程度ですが)。出雲大社の畔で内陸の山梨とはまた異なる柔らかな味わいの甲州が生まれています。 また、内陸に入った木次では木次乳業のグループ会社である奥出雲葡萄園が小公子やシャルドネから魅力的なワインを生んでいます。 お隣の鳥取県は砂丘で有名ですが、砂丘近くでぶどうが栽培されており、砂質ならではの香り高いワインが生産されています。 中国地方の最後、山口県のワイナリーはまだまだ少ないですが、瀬戸内海の島でもワインづくりが始まっています。四国のワイナリー数は2022年末の統計で4県計で10軒。高知と香川に3軒ずつ、愛媛と徳島に2軒ずつです。高知県は暑く、秋の台風の影響も受けやすい県ですが、萌芽から収穫までの生産サイクルが他県よりも早く、台風の影響は限定的です。ボルドー液の生産会社が立ち上げた(=石灰質土壌の)ワイナリーが興味深いワインを生産しています。アルバリーニョも注目したいところ。 その他の県でも新規のワイナリーの設立が続いていますが、まだ県の特徴や象徴的なぶどう品種と言ったものが生まれる状況ではありません。生食用ぶどうも交えつつ、安定的なぶどう生産を目指すワイナリーが多いです。比較的天候が安定している、小豆島などの瀬戸内の島々でのワイン生産も増えています。 中四国編 NEW ! NEW ! NEW ! NEW ! その他の中四国のワイン
中四国のワイナリー
中四国のワイナリー 中四国はワインの産地としてはそれほど名が通っていないかもしれません。しかし現在、このエリアの9県全てで日本ワインが生産されています。 この中で最も生産量が多いのが岡山県。元々、ハウス栽培の生食用マスカットで定評のある県で、大手ビールメーカーのワイナリーもありますが、 現在は新見市などの内陸部にワイナリーの設立が続いています。 中でも日本では珍しいテラロッサの土壌でぶどうを栽培するDomaine Tettaは海外からも注目されており、ナチュラルなアプローチで滋味深いワインを生むコルトラーダなども興味深いワインをつくります。 倉敷市のGRAPE SHIPなど、元々の名産であるマスカット・オブ・アレキサンドリアを活かしたワインづくりを行う生産者も出て来ています。 お隣の広島県でも内陸部を中心にワインが生産されています。広島三次ワイナリーが有名ですが、他にも海外のコンクールで金賞を受賞するようなワイナリーも登場して来ています。広島県の内陸部は高品質なシャルドネに定評があります。山陰側では島根県が独自の魅力を放っています。実は山梨県の次に甲州の生産量が多い都道府県は島根県(とは言え全国シェア2.5%程度ですが)。出雲大社の畔で内陸の山梨とはまた異なる柔らかな味わいの甲州が生まれています。 また、内陸に入った木次では木次乳業のグループ会社である奥出雲葡萄園が小公子やシャルドネから魅力的なワインを生んでいます。 お隣の鳥取県は砂丘で有名ですが、砂丘近くでぶどうが栽培されており、砂質ならではの香り高いワインが生産されています。 中国地方の最後、山口県のワイナリーはまだまだ少ないですが、瀬戸内海の島でもワインづくりが始まっています。四国のワイナリー数は2022年末の統計で4県計で10軒。高知と香川に3軒ずつ、愛媛と徳島に2軒ずつです。高知県は暑く、秋の台風の影響も受けやすい県ですが、萌芽から収穫までの生産サイクルが他県よりも早く、台風の影響は限定的です。ボルドー液の生産会社が立ち上げた(=石灰質土壌の)ワイナリーが興味深いワインを生産しています。アルバリーニョも注目したいところ。 その他の県でも新規のワイナリーの設立が続いていますが、まだ県の特徴や象徴的なぶどう品種と言ったものが生まれる状況ではありません。生食用ぶどうも交えつつ、安定的なぶどう生産を目指すワイナリーが多いです。比較的天候が安定している、小豆島などの瀬戸内の島々でのワイン生産も増えています。 中四国編 NEW ! NEW ! NEW ! NEW ! その他の中四国のワイン