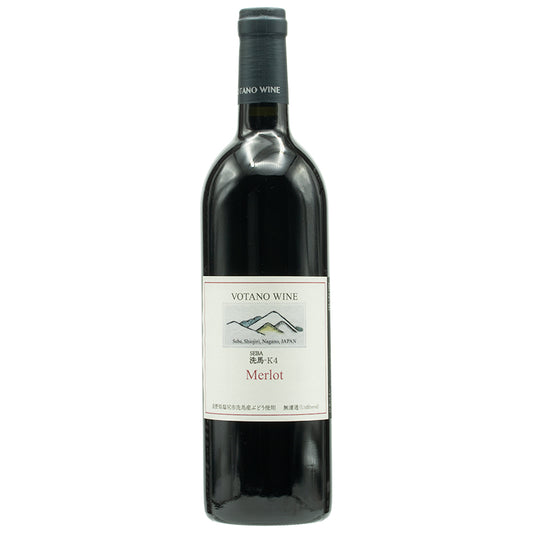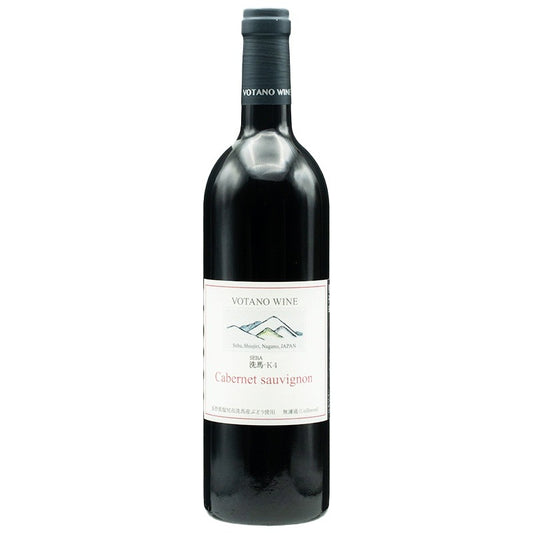▲
写真を眺めるだけでも深呼吸したくなってしまう。畑から見える景色は息を飲む美しさだ。
▲
写真を眺めるだけでも深呼吸したくなってしまう。畑から見える景色は息を飲む美しさだ。
テール・ド・シエル(Terre de Ciel)は、天空の大地という意味のフランス語。長野県小諸市糠地地区にあるワイナリーは標高950m、隣接する畑は標高920-940mに位置しており、日本一標高の高い場所にあるワイナリーです。
 ▲
畑の入り口にある熊の置物はワイン・グローワーの家族を表しているものだそう。
▲
畑の入り口にある熊の置物はワイン・グローワーの家族を表しているものだそう。
日本一標高が高い場所にあるだけあり、気候は冷涼。冷涼な気候に合う、ヨーロッパ系品種を中心に育てている。最初に植えたのはソーヴィニヨン・ブラン。その後、ピノ・ノワール、メルロ、シャルドネ、ピノ・グリと品種を増やしてきた。
畑は西南西に向いており、日中の日照量、日照時間共に十分だ。夏場は34、5℃まで気温は上がり、ブドウの糖度も上がる。一方、太陽が沈むと一気に冷え込むので昼夜の寒暖差があり、ブドウの酸持ちが良い。そして、長野県は秋が長い。年間降雨量は少なく、特に10月中旬以降の雨が少ないので、長い秋の間にブドウが熟すことができる。そこで、後から開墾した畑には、リースリングやシュナン・ブラン、シラー、カベルネ・フラン、サヴァニャンといった成熟に時間がかかる品種を植えている。
 ▲
山の中にあるワイナリーと畑。異なる方向を向く斜面をそのまま活かし、区画がいくつか設けられている。ブドウの木が並ぶ様子も美しい。
▲
山の中にあるワイナリーと畑。異なる方向を向く斜面をそのまま活かし、区画がいくつか設けられている。ブドウの木が並ぶ様子も美しい。
畑には、常時山の下から風が吹き上がる。雨が少ないことに加え、この風によって、湿度が溜まらずブドウが病気になりにくい。また、ここまで標高が高くても風によって冷気が流されるので凍害も起らないという。
そして、何より、人里離れた場所にあることから空気がきれい。健康なブドウが育つ条件が揃っているのだ。
もう一つ面白いのが、霧の発生である。この辺りは風が強く、畑の隣に国有の防風林があるのだが、その先には沢があるそうだ。昼夜の寒暖差の影響で沢から霧が発生し、朝になると畑に霧が立ち込める。その後、太陽と風の力で霧が晴れる。10月頭の収穫の時期になると、夜の冷え込みもグンと強くなる。濃い霧が立ち込め、ブドウに貴腐が付くそうだ。桒原さんは、貴腐が付いたブドウをその他のブドウと一緒に仕込む。そうすることで仕上がるワインの奥行きが増すのだ。実は貴腐ブドウを使う判断をしたのは、もがき苦しんでいた時だった。2020年は残暑が厳しく、シャルドネの酸がどんどん下がっていく一方、糖度が上がってこなかった。このままではアルコール度数も上がらないな…と思い悩んでいた時に、シャルドネに貴腐が付着し始めたそう。ココ・ファーム・ワイナリーでブドウ栽培をしている際にも貴腐ブドウを扱ったことがあり、いい貴腐はブドウにプラスに作用することが分かっていた。実際に貴腐が出たシャルドネを食べてみると美味しく、貴腐が付いたシャルドネを混ぜ込んで醸造することを決め、吉と出たそうだ。


質の高いブドウ栽培を徹底していることから、補酸・補糖は一切行わない。発酵はブドウに付着している野生酵母のみで行い、亜硫酸の添加も一切行わない。その為、悪い菌が活発に動かない環境にする必要があるので、温度管理を徹底して行う。収穫したブドウは5℃に設定した冷蔵室で一晩冷やし、悪い菌を動かさないようにする。搾汁も10-12℃程度に冷やした環境で行う。発酵・熟成の過程でも温度管理を徹底。発酵期間中は温度を上げるが、熟成期間中は15℃以上に温度が上がると悪い菌が発生しやすくなるので、11~12℃程度に管理しているそうだ。発酵・熟成期間は冬場も続く。冬の気温は氷点下になるので、暖房を入れ、微生物の活動がきちんと終わるようにするそうだ。微生物的に安定しているので、ノン・フィルターで仕上げたとしても、予期せぬ微生物による瓶内再発酵が起こらない。