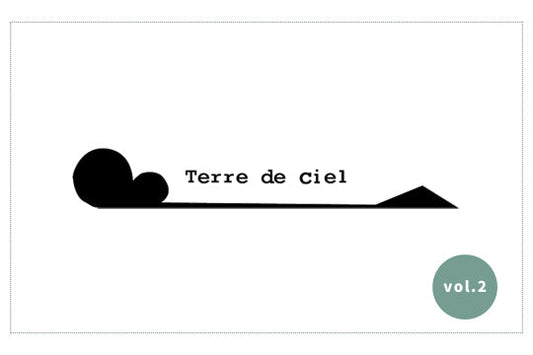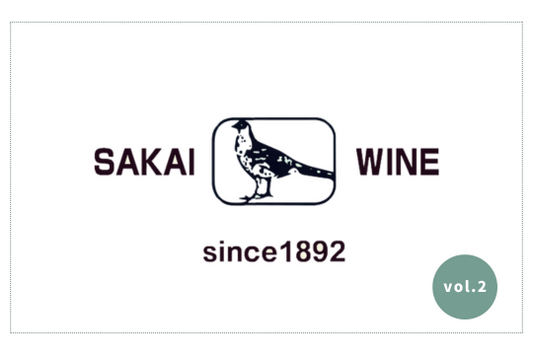日本ワインコラム | 長野 496ワイナリー
ボルドーにやってきた。のではないが、日本のボルドーと言われる場所にやってきた。東京から新幹線で約1時間半。信州が誇る一大ワイン産地、千曲川ワインバレーだ。千曲川の流域に広がる産地で、右岸と左岸で個性の異なるブドウ栽培が盛んな場所だ。今回訪れた496ワイナリーがあるのは左岸側。そこで飯島さんは奥様の祐子さんと共に2014年からワイン用ブドウの栽培を始め、2019年には自社ワイナリーを設立、ブドウと向き合う日々を過ごされている。


496=シクロ=Cyclo=自転車
ワイナリー名の496にはフランス語で自転車を意味する「シクロ」という意味合いが隠されている。実は、飯島さんはもともと自転車競技の選手。個人追い抜き種目のパシュートと呼ばれる競技では、マスターズ部門の世界記録を樹立したという信じられない経歴の持ち主だ。スポーツ選手でこれだけの経歴の持ち主であれば、引退後にスポーツ関連の職に就くことは容易だっただろうと想像する。しかし、飯島さんは40代後半で全く異なる分野のブドウ栽培&醸造家に転身する。このジャンプはどこから来るのだろう?と不思議に思っていた。


飯島さんはきっぱりと仰る。「過去はどうでもいい。今を大事にしている」
と。選手時代には、自転車で地球15周分を走ったそうだ(驚愕!)。もはやそれがどんな距離なのか想像の域を超えているが、永遠とも思える距離を走りぬき、やりきったという感覚があるのだろう。
次は、何かモノを作って、人に喜んでもらいたいという強い思いがあったそうだ。では、何を作るのか?選手時代、海外に遠征に行った時に出されたワインは、「常に楽しい時のわき役」だったという。ワインは幸せの記憶に直結するもの。そして、ワインには「人を繋げる力がある」と言う。
みんなでボトルに入った液体を分け合いながら飲む。ワインの周りには人が集まる。それだけではない。ワインを目的に旅先を選ぶこともあり、ワインを通じた新しい出会いがある。他の農産物で、こんな形で人を結びつけるものはそうはない。ワインで人に喜んでもらいたい、幸せを感じてもらいたい、人との繋がりを大事にしたい。自転車の世界を経験したからこそ見つけられた次の世界だった。
飯島さんは、目標に向かってもくもくと打ち込むタイプだと祐子さんは仰る。これだ!と思ったものに対しては、迷いなく全エネルギーを注ぐ、猪突猛進型。ワインも自転車も長距離走。2つは全く違う畑のように見えるが、飯島さんの向き合い方は変わらない。365日、休みなく畑に出かけて行くそうだ。
畑との出会い — 流れに身を任せたら最高の場所だった
人に喜んでもらいたいという気持ちから始めたワインの道。出来上がったワインを飲んでもらわないと意味がない。お客様の多い関東圏から近い場所にワイナリーを設立したいと思った。
長野県は首都圏からのアクセスがいい。行政も誘致に積極的で、周りの農家達の風通しも良かった。千曲川ワインバレーは、日本有数の日照時間を誇り、降雨量が少なく、標高が高さによる昼夜の寒暖差があり、ブドウ栽培に恵まれた土地だ。ワイナリーの多くは右岸側にある。左岸よりも更に標高が高く、火山性の黒ボク土を土壌とするところが多い。一方の左岸は、右岸よりも標高が低く、粘土質の土壌を持つ。飯島さんも多くのワイナリー同様、移住当時は右岸で農地を探した。もう少しで契約となったが、所有者側の権利関係に不備があることが判明し、破談になったそうだ。そんな折、左岸の農家にお手伝いをしていた祐子さん経由で今の土地に巡りあった。
蓼科山の地下水+強粘土質土壌+寒暖差という好条件が揃うお米の名産地で、畑の目の前は田んぼが広がる。飯島さんの畑は斜面でお米を作ることができないことから田んぼにならず手付かずで残っていたという。
 ▲
畑の前には田んぼが広がる。新緑の稲と整列するブドウ畑のコントラストが美しい。ブドウ畑と田んぼという組み合わせは珍しいが、日本ならではの癒される景色だ。
▲
畑の前には田んぼが広がる。新緑の稲と整列するブドウ畑のコントラストが美しい。ブドウ畑と田んぼという組み合わせは珍しいが、日本ならではの癒される景色だ。
当時、粘土質土壌の左岸は果樹不毛と言われていた。果樹の成長速度は遅く、一本当たりの収量も少なく経済性が悪い。一方、栄養分が豊富な粘土質土壌で収穫された果実の味わいは濃いという利点もあった。要は、栽培は大変だが、収穫されたものの質は高いということだ。畑は丘陵でなだらか斜面となっており、実際に畑に足を運ぶといい印象を持ったそうだ。飯島さんの畑は標高680mの台地の南東のヘリにある。実は同じ台地の北西のヘリには、老舗シャトー・メルシャンが自社管理圃場として設立し、高品質なブドウが栽培されていると有名な椀子ワイナリーがある。
北西のヘリで高品質なブドウが育つのであれば、朝から十分な日照を得ることができる南東向きのこの土地はもっと良いに違いないと踏んだ。確かに強教粘土質土壌ではあるが、斜面で水はけも良いのでブドウ栽培にとっては好条件だ。ワイン用ブドウを育てる上で最高の場所だと感じた。


飯島さんは過去に固執しないと言ったが、祐子さんも「行ってみてダメなら遮断されるはず。それが運命。」という考えの持ち主だ。お二人は、「目に見えない導きによって流れていく」という考えを共有している。最初の畑の契約がうまくいかなかったのはそういう運命。今の畑に出会ったのも運命。流れに抗わず、今できることに目一杯力を注ぐことで新たな流れが生まれてくるのだ。
右岸の方が左岸よりも標高が高いなら、寒暖差も右岸の方があると思われる読者も多いだろう。しかし、実は左岸の方が寒暖差はあるのだ。右岸にあるワイナリーの多くは標高800mを超えるが、ゆるやかな南西向きの斜面に畑があり、西日を受けた畑は夜の間も熱が残る。一方、左岸にある飯島さんの畑は南東向きで、西日が少なく、朝は放射冷却の影響でぐんと冷え込む。そのため、5月~6月の頭まで遅霜のリスクがある。リスクはあるが、リターンは大きい。まず、日中は標高が低い分、右岸に比べて2-3℃温度が高くなり、ブドウが熟して糖度が上がる。そして、夜は気温が下がり、ワインに必要不可欠な適度な酸を維持することが可能なのだ。ブドウ栽培環境は抜群にいいと胸を張る。
飯島さんが目指すワインの味わいは、単体として楽しむものではなく、「食事に合うワイン」だ。みんなで食卓を囲んで飲むワインは、まさに「楽しい時のわき役」としてのワインではないだろうか。飯島さんの思いを感じる。品種は、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、メルロ、ピノ・ノワール、アルモ・ノワール(カベルネ・ソーヴィニヨンとツヴァィケルトレーベの交配種)の5種類。確かにどれも食事と寄り添ってくれる品種である。
テロワールを大事にしたい ― ブドウ栽培編
飯島さんは、ブドウの品質がワインの出来を決定付けると断言する。例えば、ロマネ・コンティで育ったブドウを使えば、普通の醸造家でもかなり美味しいワインを造ることができる。それ位素材が素晴らしいのだ。60点のブドウから100点のワインはできないが、100点のブドウからであればそれが可能になる。
ヨーロッパの銘醸地と言われているような場所と比べると、日本は高温多湿で栽培環境にハンディがあることは認めざるを得ない。だからと言って悪い訳ではない。日本だからこそ出せるテロワールがあると考え、飯島さんはブドウ栽培に時間と労力を惜しみなくかける。
 ▲
畑を紹介して下さる飯島さん。毎日欠かさず畑に通い、休むことなく働かれる姿に、時々奥様が心配になってしまうほど。それくらい全力で向き合っておられるのだ。
▲
畑を紹介して下さる飯島さん。毎日欠かさず畑に通い、休むことなく働かれる姿に、時々奥様が心配になってしまうほど。それくらい全力で向き合っておられるのだ。
実際に育ててみて気付いたことがあると言う。シャルドネとメルロは、栽培環境が異なっても木や枝ぶりの変化は少ないが、ピノ・ノワールは栽培環境に応じて枝ぶりが大きく変化するそうだ。ロマネ・コンティに植わっているピノ・ノワールをこの土地に植えても、決して同じピノ・ノワールにはならないということだ。
教科書上では、ピノ・ノワールは痩せた土地で小ぶりに育てるのがいいと言われるが、飯島さんの畑のピノ・ノワールは巨峰のようなサイズになるとのこと。だけど、これがここのピノ・ノワールなのだと確信している。もし、この土地で小ぶりなピノ・ノワールに育っているのだとしたら、それは単に土壌に栄養がないだけ。飯島さんの畑には以前、朝鮮人参が植わっていたようで、ブドウを植え始めたばかりの頃は、小ぶりでばら房、カビの影響もない、教科書通りの完璧な房に仕上がったそうだ。しかし、全く美味しくない。栄養がなく、旨味が全くないのだ。動物も決して食べようとはしなかったそうだ(彼らは美味しいものをよく知っている!)。実は、朝鮮人参は畑の栄養をかなり吸うようで、土壌診断したところ、土に栄養が残っていなかったことが分かった。栄養のない土で育てたブドウの見た目は教科書通りだけど、これは正解ではない。体感として習得したものだ。
採れたてを食べることが美味しさの秘訣となる早摘み野菜と異なり、ブドウは木でじっくり熟して美味しくなる。だからこそ、根が栄養を吸う土壌環境の整備が何よりも大事なのだ。
 ▲ 畑で育つブドウ。健康に育つブドウはどれも美味しそうだ!
▲ 畑で育つブドウ。健康に育つブドウはどれも美味しそうだ!
その後、土壌改良を進め、今では樹勢もしっかりある、この土地ならではのブドウができるようになったという。手間暇はかかるが、化学肥料や殺虫剤、除草剤を一切使用せず、ボルドー液のみ限定的に使用するのは、土壌の大切さを痛感しているからこそだ。
一方、手を加えなくてもそれなりの品質のブドウができるところが「ワイン産地」なのだと仰る。暑いところで育つシャルドネは酸が足りない。かと言って涼しすぎると糖度が上がらない。飯島さんは、日本に於いては、ご自身の畑の場所が酸味と糖度がバランスするギリギリのラインだと分析されている。
逆に、メルロはこの土地にドンピシャだそうだ。
ピノ・ノワールは雨にめっぽう弱い品種で、日本で育てるのは難しい品種だ。その為、果実の周りにレインガードをする農家が多いが、飯島さんはしない。人間が手を加えれば加えるほど、本来、その土地の持つテロワールとは乖離してしまう。人工物で環境を変えるのではなく、その土地ならではのブドウそのものの力を活かしたいと考えているそうだ。
異なる品種であっても、それぞれ高い品質のブドウが育つ。この土地のポテンシャルの高さが伺われる。
テロワールを大事にしたい — ワイン醸造編
イメージはスマート・フォーマル。あまりカジュアルに着崩さず、フォーマルな着こなしができるほど品質のよいブドウがあるからこそ、醸造過程ではあまり手を加えすぎないことを意識しているそうだ。
土台となるブドウの品質がしっかりしているので、ほぼ補糖や補酸する必要はない。補糖・補酸などをしないということは、ブドウの品質によって味わいに差が生まれることになるが、過度に手を加えないことでガチガチの工業製品とならず、純粋にテロワールを映したブドウの味わいを楽しむことができるのだ。
発酵には市販の培養酵母を使用している。それには理由がある。
培養酵母の場合も野生酵母の場合も、最終的にアルコール発酵を完了させるのは、サッカロマイセス・セレビシエという種類。香りもよく、アルコール度数が高い環境下でも活発に働くことできるという強みがある。ブドウに付着した野生酵母のみで発酵する場合、アルコール度数が低いうちはサッカロマイセス・セレビシエ以外の酵母が優位に活動しがちになるが(特に白ワインの製造工程において)、徐々にサッカロマイセス・セレビシエのみが優位となり、発酵を完了させるという流れになる。
沢山の種類の酵母が活発に動くことで香りの複雑さが増すとも言われるが、高温多湿の日本の環境下では、生息する酵母の種類も数も、乾燥した欧米に比べるとかなり多い。このような環境下では、ある程度管理を行わないと、本来サッカロマイセス・セレビシエ優位によって発酵を終えるはずが、多数生息する酵母のうち、所謂欠陥臭を持つと言われる酵母が優勢になり、オフ・フレーバーをもたらす危険性も高い。野生酵母で発酵していれば全て香りが複雑=いいワインと思うのは短絡的な見方なのだ。
ポテンシャルの低いブドウをスマート(培養酵母を使用して発酵初期からサッカロマイセス優位)に醸造すると、香りや味わいに深みがなく、淡泊になりがちだと飯島さんは言う。だから、テロワールの良さを誇れるほど高品質なブドウを育てることに注力し、ブドウ本来の味わいを伝えるスマートな醸造にこだわっておられるのだ。
 ▲
確固たる考えを持って栽培と醸造について向き合っておられる飯島さん。お話される熱量がすごい!
▲
確固たる考えを持って栽培と醸造について向き合っておられる飯島さん。お話される熱量がすごい!
飯島さんが考えるテロワールを映したワインとは、「品種の特徴が分かった上で、土地の特徴が分かる」ということ。事実、同じブドウ品種、同じ培養酵母で、同じように醸造しても、ブドウの栽培環境が違えば、全く異なるワインが生まれる。それこそが真のテロワールの違いなのだ。化学肥料や殺虫剤、除草剤を用いず、環境負荷も減らした上で、テロワールを反映したワインを醸す。
それによって「食事に合うワイン」が出来上がるという考えだ。
発酵後、熟成期間もなるべく手を加えないことを意識しているそうだ。昨今、亜硫酸の添加を控えるワイナリーが増えているが、ワイン醸造過程における添加物はこれ以外にもある。例えば、色素安定剤や清澄剤として用いられるポリビニルポリピロリドン(PVPP)等。亜硫酸だけではないのだ。飯島さんはこういった添加物もなるべく加えず、ノンフィルターで仕上げている。
高品質なブドウを作っているからこそ(フォーマル)、醸造過程では手をあまりかけないことで(着崩す)、スマート・フォーマルな仕上がりの美味しいワインができるのだ。そして、ロマネ・コンティだけがフォーマルな服を着ている訳ではない。日本には日本独自の、千曲川左岸には左岸独自の素晴らしい栽培環境があり、このテロワールを余すことなく伝えるのが、ワイン産地としての責任であり、それが可能だという自負もある。
過去でもない、未来でもない。今できることが全て。
469ワイナリーは100%自家栽培のブドウで、栽培→醸造→販売まで一貫して行っている。どれも手が届く範囲で行っているので、生産数は決して多くない。しかし、その分、飯島さんの哲学がどの過程に於いても一本通っているのだ。
飯島さんは潔い。そして、決めたことに対して誠心誠意全力で向き合う。インタビューを通じても迷いを感じることが一切なかった。理想の姿を100点として今は何点ですか?という質問をしたら、
これが100点と思ってやっていることの連続だ
と迷いなく答えられた。あまりにも格好良すぎて、鼻血が出そうだ。そう仰った後、こう続けた。
ワイン造りは素人として始めたもので、大きな理想を掲げているわけではない。日々の積み重ねを大事に、 今できることをやっているだけ。そこで満足するしかないし、逆に満足だと思っていないとやれない。 真面目に向き合っているが、そうでないとやっていられないからだ。いい加減なことにこんなに時間を費やせない
と。ストイックさを感じるし、飲むこちら側も襟を正さないといけない!と思わせるくらい、本気で向き合っておられることがひしひしと伝わってくるのだ。
 ▲
ワイナリー内に置かれている496ヴィンヤーズのワイン達。“パシュート”というネーミングもニクイ。
▲
ワイナリー内に置かれている496ヴィンヤーズのワイン達。“パシュート”というネーミングもニクイ。
スポーツはより速く、遠く、高くを目指すというゴールが明確な世界だったが、ワインは多様性の世界で、誰かに評価されたからいいというものでもない。結局、自分がいいと思うものを追い求めるしかない。ある意味孤独な世界だ。だからだろう。地元の方がお土産に469ワイナリーのワインを手に取って下さる機会が増えてきたことをとても喜んでおられた。地元の方が誇りを持ってワインを手に取って下さることが何よりも嬉しい、と。
ものすごい熱量で語って下さった飯島さん。そしてその傍らで、常に次の展開を予測して動かれる祐子さん。自転車選手からワイン造りへのジャンプはかなり凄いと思うが、それに寄り添い、サポートし続ける祐子さんもただ者ではない。思えば、畑の出会いも祐子さんが導いて下さったものだ。
今できることはやりきって、後は天命を待つ。この清々しい姿勢を共有するお二人だからこそ、496ワイナリーならではのテロワールの表現に繋がるのだろう。
皆さんにもぜひ試して頂きたい!
 ▲
飯島さんご夫妻と。貴重なお話、ありがとうございました!!!
▲
飯島さんご夫妻と。貴重なお話、ありがとうございました!!!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。