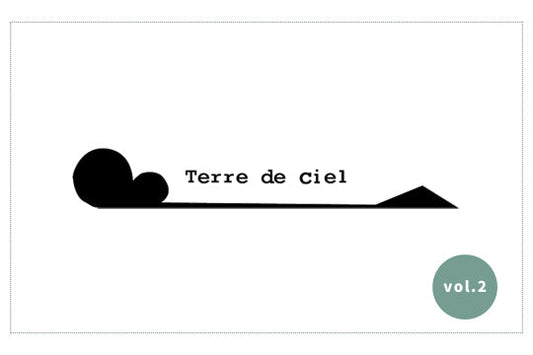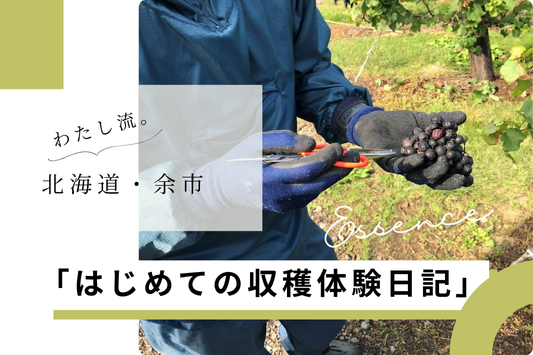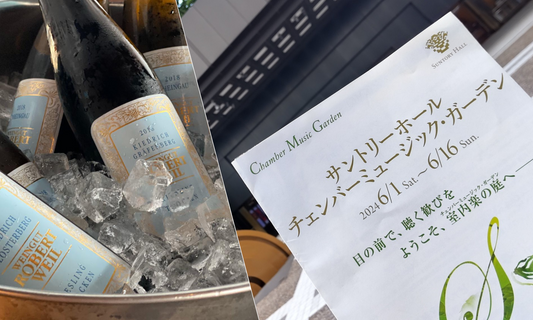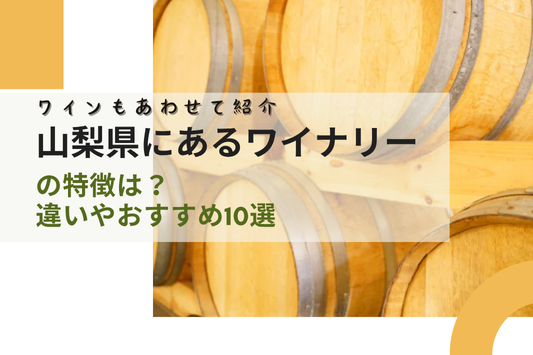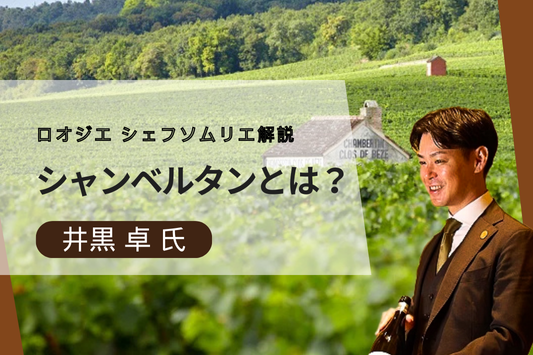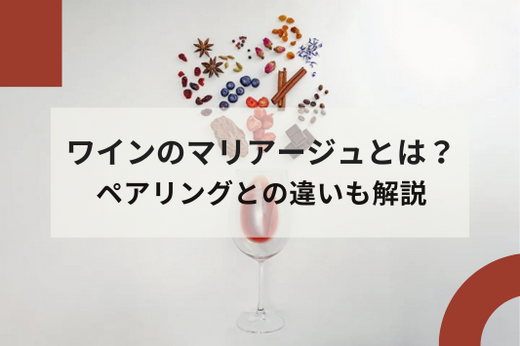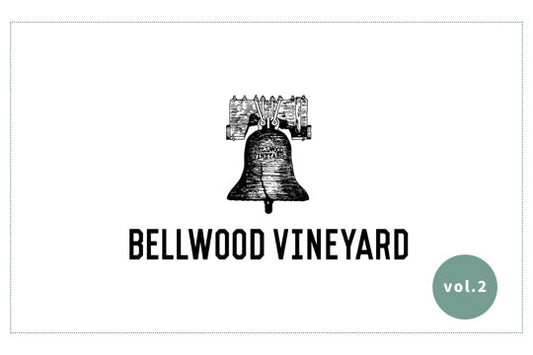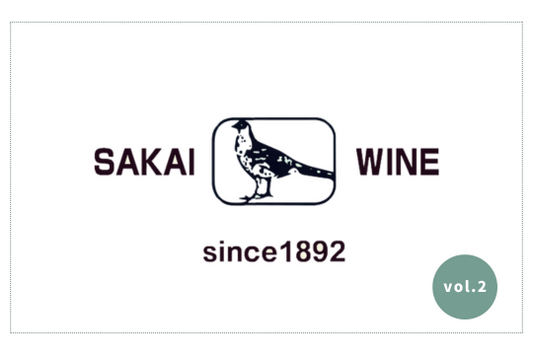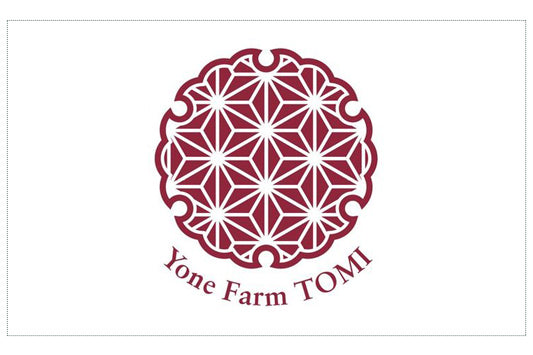個性豊かなスタッフが綴る
わたし流。いまイチオシのワインたち
すべて見る-
― テイスティング セミナー・シャンパーニュ ―
【スタッフ体験レポート】シャンパーニュ・アンリオ セミナー
-
― テイスティング セミナー・シャンパーニュ ―
【スタッフ体験レポート】シャンパーニュ・ゴッセ セミナー
とっておきのワインをあの人へ
ギフト特集
すべて見る
もっとワインを知ろう
ワインの豆知識
すべて見る-
おすすめワインを多数紹介
- TOP - 現地渡航情報を交えて徹底解説!南アフリカワインの魅力
-
違いやおすすめ10選、ワインもあわせて紹介
山梨県にあるワイナリーの特徴は?違いやおすすめ10選、ワインもあわせて紹介
-
料理の組み合わせ方やおすすめワインも紹介
ワインペアリングとマリアージュの違いは?料理の組み合わせ方やおすすめワインも紹介
-
おすすめワインも紹介
ロワールとは?ロワールワインの基礎知識や味わいなどをわかりやすく解説
-
おすすめワイン3選も紹介
カリフォルニアワインの特徴や品種の種類を解説!おすすめワイン3選も紹介
-
おすすめワインも紹介
イタリアを代表する黒ブドウ品種「サンジョヴェーゼ」の特徴とは?おすすめワインも紹介
-
おすすめの銘柄も紹介
イタリアを代表するトスカーナワインの魅力を徹底解説!
-
おいしく飲むポイントやおすすめワイン3選も紹介
自然派ワインの基礎知識を解説!おいしく飲むポイントやおすすめワイン3選も紹介
-
ブルゴーニュワインの王と呼ばれる理由やおすすめの料理も紹介
シャンベルタンとは?ブルゴーニュワインの王と呼ばれる理由やおすすめの料理も紹介
-
具体的な料理の組み合わせやペアリングとの違いも解説
ワインのマリアージュとは?具体的な料理の組み合わせやペアリングとの違いも解説
さらなる魅力を再発見
日本ワインコラム
すべて見る
ワインとの楽しい日々
Staff Blog ~僕の、私の、ワインのある暮らし
すべて見る
現地取材|ワイン産地から届ける、作り手の声