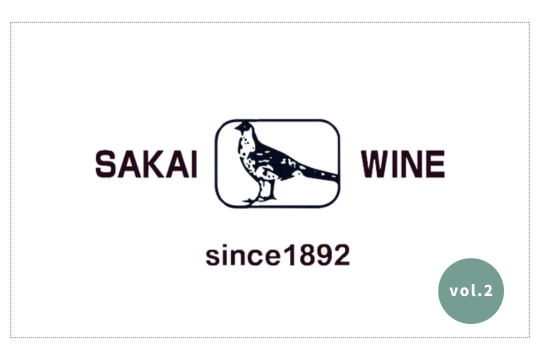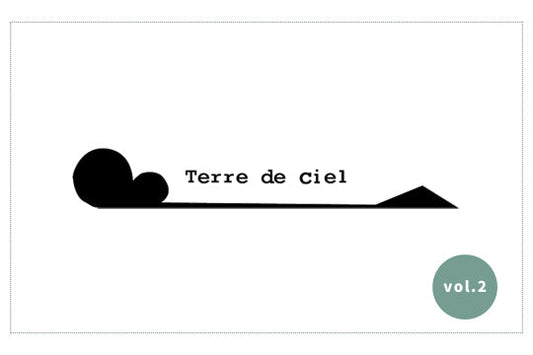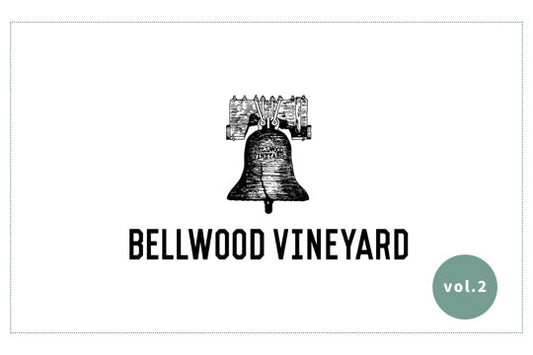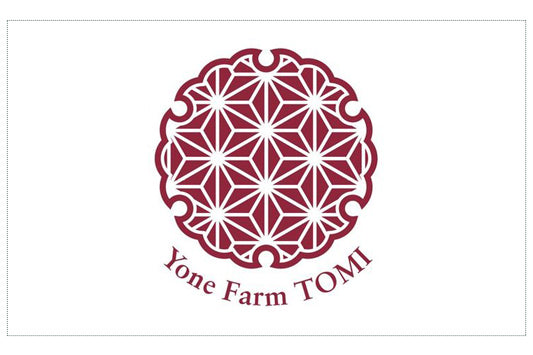日本ワインコラム |酒井ワイナリー/ Vol.2
初めて酒井ワイナリー5代目当主の酒井一平さんを取材したのは約5年前。クロード・レヴィ=ストロースが唱えた構造主義や、同氏の代表作『野生の思考』の中で紹介されている「ブリコラージュ(日曜大工)」という概念を織り交ぜながら、ご自身のワイン造りについて語ってくれた。
今回も、ちょっと小難しい…(すみません!汗)、もとい、哲学的で思索的な印象はそのままに、更なるステージへ足を踏み入れている姿をみせてくれた。他のワイナリーの方々と話をしていると、酒井さんを「超人的」と評されるのをよく耳にする。点在する耕作放棄地を管理するだけでも大変なのに、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを栽培。そして、東北最古のワイナリーの当主という立場もあってか、様々な役職にも付いている。確固たる信念があるからこその行動だとは思うが、なかなかできないことだ。
今回は、そんな「超人的な」酒井さんの考え方の軸となる部分や現在の様子、そして今後の展望や課題について話を伺った。


『その土地の普通』を追い求めて
酒井ワイナリーは、1892年創業の東北で最も長い歴史を持つワイナリーだ。2004年に酒井さんが5代目を継いで20年強が経過している。今でこそ、「酒井ワイナリー=自然な造りのワイン」というイメージを持っておられる方が多いと思うが、化学農薬、殺虫剤、化学肥料、除草剤無しでブドウを育て、野生酵母で発酵し、無清澄・無濾過、亜硫酸は極少量ないし無添加でワインに仕上げる、という全行程が確立したのは、5代目になってからである。このスタイルに行きついた背景には何があるのだろうか?
 ▲ ワイナリーの中に貼られている酒井ワイナリーの歴史。
▲ ワイナリーの中に貼られている酒井ワイナリーの歴史。
昔、(ドメーヌ・オヤマダの)小山田さんが主宰していた若手勉強会に参加した際に、自分で醸造したワインを持って行ったことがあるんです。『どうやって造ったの?』と聞かれたので、『普通に造りました』と答えたら、『普通って何?』って聞かれたんです。その時に絶句してしまって。自分の言う『普通』って何なんだろう?と凄く考えるようになりました。そこから、様々な書物を読んだりして自分なりに思考を深めたんです。
こんな禅問答がある勉強会に恐ろしさを感じなくもないが、この出来事をきっかけに、構造主義を始めとする哲学書や自然科学の本を読み漁るというところが、酒井さんが酒井さんたる所以なのかもしれない。
 ▲ 深い思考を重ねた上で、ワイン造りに向き合う酒井さん。
▲ 深い思考を重ねた上で、ワイン造りに向き合う酒井さん。
『その土地における普通のワインとは何だ?』という問いを突き付けられたと考え、そこから、『その土地における文化的普遍性とは何か?』と考えを深めました。そして、自分の中で辿り着いた答えが、『その地域における自然の有り様』だったのです。自然は一定ではなく、万物流転で変化し続けますが、その中でその土地特有のものが生まれます。
 ▲
酒井さんのインスタより。畑の草刈りをしている時にヨシキリの巣を発見したとのこと。畑には多様な生き物が生息しているのだ。
▲
酒井さんのインスタより。畑の草刈りをしている時にヨシキリの巣を発見したとのこと。畑には多様な生き物が生息しているのだ。
その上で、ブドウ栽培における酒井さんの考えが続く。
だから、例えば自分の畑は『ブドウ畑』とは思っていません。牧草も植えているし、桜を始めとした色んな木が植わっています。あらゆる生き物の力に頼った畑なのです。畑にブドウと人間しかいないというのは不自然、つまりその土地の農作物ではなくなり、普遍性から離れる。だから除草剤や殺虫剤を用いて、微生物を始めとする生き物を殺すことはしない。たとえ、出来上がるブドウがどんなにきれいでも。畑の環境も森に近づけたいと思っています。
ワイン醸造においても、この考えが根底にある。
「ワインを野生酵母で発酵するのは、野生酵母で造った方が美味しいからという理由ではなくて、その土地で全てを自給することで初めて、その土地のブドウやワインの文化ができると考えているからです。ルイ・パスツールの発見によってワインは高品質且つ安定的なものになったかもしれないが、同時に優生的な思想を生み出した。ここから離れるべきだと考えています。」
因みに、ルイ・パスツールは「細菌学の父」と言われる偉大な人物で、アルコール発酵が酵母によるものだと発見したり、ワインの腐敗を防ぐため、微生物を殺菌する低温殺菌法を生み出したりした人物で、現代のワイン造りの父と言える人物だ。酒井さんの「優生的な思想から離れるべき」というのは、微生物をすべからく悪と考える思想にNOと言いたいということだろう。
「ワインはその土地を知る最良の方法の一つ」と酒井さんは言う。ヴィンテージ差もあるし、土地と品種の相性もある。造り手の思想も反映されやすい。そして、土地の歴史を感じるものでもある。例えば、赤湯は今でこそデラウェアの生産量は隣の高畠町より少ないが、長く日本一を誇っていた。土地の微生物を含め、栽培環境とデラウェアを始めとするブドウ栽培がマッチしているのだ。
全ては循環する ー ミッシングリンクは動物だった
酒井ワイナリーの近辺には3つの山がある— 「名子山」、名子山の東側にある 「十分一山」、名子山の西側にある 「大沢山」だ。この3つが、赤湯の「鳥上坂」と言われているブドウの産地。酒井ワイナリーでは、それぞれの山に自社畑がある。因みに、酒井ワイナリーが展開する「バーダップ・ワイン(BIRDUP WINE)」は「鳥上坂」に由来する名称だ。
酒井ワイナリー バーダップ赤 2022

| 原産国 | 日本 / 山形県・南陽市 |
|---|---|
| 品種 | マスカットベーリーA |
| 度数 | 12% |
-
 赤ワイン
赤ワイン酒井ワイナリー バーダップ赤 2022
赤ワイン日本/山形県通常価格2,420 円 (税込)通常価格単価 あたりマスカットベーリーA マスカットベーリーA
売り切れ
酒井ワイナリー バーダップワイン 白 2023

| 原産国 | 日本 / 山形県・南陽市 |
|---|---|
| 品種 | 甲州、デラウェア、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
-
 白ワイン
白ワイン酒井ワイナリー バーダップワイン 白 2024
白ワイン日本/山形県通常価格2,420 円 (税込)通常価格単価 あたり甲州他 甲州他
丸みのあるやさしい酸が全体を引き締めて、飲み心地の良いワイン売り切れ
前回訪問時にお邪魔した急斜面の「名子山」の自社畑は(→詳細はこちらから)、今年の大雪で大きなダメージを受け、現在復旧中とのことで、今回は、「名子山」の西側に位置する「雨霊沢(うるいざわ)」と「大沢山」の2つの畑にお邪魔した。
機械化が可能な雨霊沢
ワイナリーからピックアップトラックで山を登る。ガタガタと車体が揺れるような場所もあるが、酒井さんは全く気にせず、グイグイ車を飛ばす。そして現れたのが、標高250-270mに位置する雨霊沢の畑だ。元々は温泉施設のキャンプ場だった所で、酒井ワイナリーとしては、「狸沢(むじなざわ)」の次に垣根栽培を導入した畑でもある。
 ▲ 雨霊沢の畑からの景色。吸い込まれそうな美しさだ。
▲ 雨霊沢の畑からの景色。吸い込まれそうな美しさだ。
ブドウの樹齢は12、3年目。カベルネ・ソーヴィニヨンを主体に、カベルネ・フラン、メルロ、マルベック、シラー、プティ・ヴェルド、タナといった黒ブドウが植わっている。病気が萬栄しないよう、列毎に品種を変えて植えているそうだ。様々な品種がそこかしこにあるので、森の中にブドウが自生しているような雰囲気もある。山の斜面の中腹に位置し、雪融け水が湧き出る名子山の畑とは異なり(→酒井さんの水に対する考え方はこちらから)、雨霊沢は丘の上に位置する畑で乾燥しやすい。そのため、マルベック、タナ、シラーといった温暖な気候を好む品種との相性がいいのではないかという仮説を持っているそうだ。


畑は緩やかな斜面。南西向きということもあり日射は強いが、風通しが良い。日中は山の下からの吹上風が、夜は山からの吹き下し風が通り、夏は35℃を越えるような環境だが、今のところ高温障害はない。夏でも夜温が20℃程までしっかり下がるので、ブドウの生育に合っているのだ。一方、昼夜の寒暖差により朝露が出るので、カビが出やすくなるのが問題。また、三方を山に囲まれている環境から虫が発生しやく、特にコウモリガによる被害が大きいという。幸い、ボルドー液(有機栽培でも使用可能な殺菌剤)で大抵のカビの問題は解決できるのと、斜面が穏やか=機械化が可能なので、乗用モアで虫の住処となる草を刈ることができるのは有難い。そんな中、今、一番頭を悩ましているのは、晩腐病だ。カビ菌が原因で、ブドウが熟す頃に急速に病気が広がり、果実が腐敗してしまうのだ。大抵のカビはボルドー液で対処できてきたが、晩腐病は例外だそう。対策として、最近、ビニールのフルーツガードを導入したそうだ。
 ▲ フルーツゾーンにビニールがかけられているのが分かる。
▲ フルーツゾーンにビニールがかけられているのが分かる。
なお、収穫はカベルネ・ソーヴィニヨンのタイミングに合わせて同時に行われる。そして、「狸沢」のブドウも合わせた混醸でワインに仕上げられ、それぞれの畑から一文字取った「雨狸(あめだぬき)」として展開中だ(名前がカワイイ!)。
酒井ワイナリー 雨狸 2022

| 原産国 | 日本 / 山形県・南陽市 |
|---|---|
| 品種 | 欧州系の数種類のぶどうの混醸 |
急斜面の大沢山
雨霊沢から更に山を登り、大沢山は370mと標高の高い場所に位置する。畑はかなりの急斜面!日本のコート・ロティと呼びたくなるほどの角度だ。元々慣行栽培でデラウェアが植わっていたところを改植して、今は3年目の幼木となるメルロ、シラー、プティ・ヴェルド、アルバリーニョ、プティ・マンサン、その他白ブドウを栽培中だ。
大沢山の畑に来ると、視界の向こう側に十分一山も見え、赤湯という場所の特異性が良く分かる。名子山、十分一山、大沢山が囲むようにある平坦部では稲作が行われている。この場所は太古の時代は海底火山のカルデラで、広大な湿地帯だ。カルデラの斜面にあたる部分がこれらの山々で、海底火山の名残でミネラル分が多い土壌環境になっているのだ。
 ▲
大沢山の畑からの景色。真ん中に見えるのが白竜湖で周辺は湿地帯になっている。その奥に見えるのが十分一山で、パラグライダーの世界大会も開催されたことがある名所だ。
▲
大沢山の畑からの景色。真ん中に見えるのが白竜湖で周辺は湿地帯になっている。その奥に見えるのが十分一山で、パラグライダーの世界大会も開催されたことがある名所だ。
 ▲
手前のビニールハウスの骨組みだけが残っているのが、酒井さんの畑。近隣の畑も含め、急勾配なのが良く分かる。
▲
手前のビニールハウスの骨組みだけが残っているのが、酒井さんの畑。近隣の畑も含め、急勾配なのが良く分かる。
「景色がいい場所は、ブドウにとって最高の場所なんです。ただ、人間にとって厳しいだけで(笑)」、と酒井さんが教えてくれた通り、大沢山の畑は急斜面で、機械化は難しい。畑に入っても、ズルズルっと転がっていきそうな角度なので、手作業でも足場が覚束ない。しかし、南東向きの斜面は陽当たりが良く、風通しも抜群、水はけも最高なのだ。
この畑は長く除草剤や農薬が使用されてきた畑だ。この斜度だし、薬に頼りたくなる気持ちは本当によく分かる。だが、酒井さんは頼らない。
薬を撒いたところは、地表が洗い流されてしまって何もない状態。今は土造りをしながら栽培しているような感じなので、ブドウの成長はゆっくり。畑の上の方は山からの土の流入が多少あるが、畑の中腹は土が浅く、有機物の塊もないのでブドウ樹が全く育たないし、病害虫の発生も多い
と言う。ゆっくりかもしれないが、土造りを行うことで初めて、大沢山という土地のブドウができるということだろう。今後の成長が楽しみな畑なのである。


偉大な羊たち
除草剤を用いず、下草を生やしてブドウ栽培をしている酒井さんのスタイルは、所謂「草生栽培」というジャンルに入る。しかし、刈り取った草の取り扱い方が少し違う。
 ▲
酒井さんのインスタより。ブドウ畑等で刈られた草をサイレージにしたものを羊たちが美味しそうに食べている!
▲
酒井さんのインスタより。ブドウ畑等で刈られた草をサイレージにしたものを羊たちが美味しそうに食べている!
酒井ワイナリーには現在、11頭の羊がいる。名子山の畑では、羊が自由に歩き回ることで、除草剤と肥料の役割を果たしていたのは、前回のコラムでお伝えした通り。機械化が可能な雨霊沢も、まだ幼木の大沢山の畑も羊たちが出勤することはないそうだが、畑で刈られた草は羊たちのご飯として運び出される。そして、その草を食べた分だけの糞を畑に肥料として還元しているという。ブドウの搾りかすも、そのまま畑に撒くのではなく、一旦羊たちの餌として与え、反芻運動による発酵を経た糞を肥料として畑に戻す。
「自然界では、草が刈られた状態で黒くなっていくことは殆どない。動物の餌にする方が自然だと考えている」、と酒井さん。
作物を収穫するという行為は、畑からの収奪行為でもある。収奪したものを戻さない限り、畑は痩せる一方で継続性がない。「今までは農業に動物が足りていなかった」、と酒井さんは指摘する。動物がいることで、収穫物の残渣や周辺の草が餌に変わるだけでなく、畑に有益なものを戻すことが可能となり、循環型農業が完成するのだ。
また、「ブドウの枝が成長して地面に垂れ下がったりすると、羊がブドウの葉を食べることがあります。植物は人間が葉っぱをちぎる場合と、動物に食べられた場合を区別しているそうです。どうやら動物の唾液に反応しているようですが、動物にかじられると免疫が反応し、苦味成分を出したりして自分を守ろうとするんです」、と酒井さん。 動物がいることで、土壌改善のみならず、ブドウそのものも強くなる。いいこと尽くしなのだ。
点在する畑は線になり、やがて面になる
「5年前に来てもらった時とやっていることは変わっていないですよ」と酒井さんは言うが、管理する場所は増えている。2005年に始めた自社畑は、今では16ヶ所、9haまで広がったという!その内、ブドウが植わっているのは6haで、その内の3haには苗木が植わっているという状態だ。この畑を2人+αで管理していると聞くと、何かの間違いなのではないかという気さえするが、どういった経緯があるのだろうか?
元々、初代が赤湯鳥上坂にブドウ園を開墾したのは1887年。以降、畑の開墾を続け、かなりの広さを所有していたそうだが、戦後の農地開放で姿は激変。名子山の畑以外の殆どを失うことになったそうだ。その名子山は大叔父が管理していたが、管理が難しくなり、2005年に酒井ワイナリーが買い取ることで自社畑がスタートする。その後は、契約農家や近隣のブドウ農家が引退するタイミングで農地を買ったり借りたりして畑を広げてきた。「初代の土地を取り戻していっているようなもの」と酒井さんは言う。ただ、無作為に土地を取り返しにいっている訳ではない。
 ▲
ビニールハウスの近くにある薄い緑色をした場所も、元々はブドウ畑だったそう。だんだんと山からブドウ畑がなくなっている…
▲
ビニールハウスの近くにある薄い緑色をした場所も、元々はブドウ畑だったそう。だんだんと山からブドウ畑がなくなっている…
今は点在しているが、徐々に隣接した畑を手にすることができるようになり、少しずつ固まりになってきた。点が線になり、面になれば、次のステージにいける。確かにもっと人手は必要だが、畑が繋がれば機械化も進むし、かかる手間はだいぶ減る。畑が点在している状態はピンチのように思えるかもしれないが、チャンスでもあるんです。
説明を聞いていると、物事の捉え方や見据える時間軸が違うと気付く。
「匿名性のある高品質なワインを目指している」、と酒井さんは言葉を重ねる。
相対的なものにはなると、否が応でも競争の中に入ってしまい、造り手も肩ひじが入ってしまう。ワインを多品種の混醸で仕上げているのもこの考えによるものだ。
「品種の区別はつかないけど、赤湯っぽい、酒井ワイナリーっぽいものを造りたい」、と語ってくれた。
自社畑の収量が増えていけば、「赤湯」として展開しているワインに加え、山や畑毎に仕込むワインも作れる。そうすれば、赤湯の中の環境の違いを表現できるし、細かくストーリーを届けられる。消費者にも、畑まで足を運んでもらえれば、更に感情移入してワインを飲んでもらえる。「面」で広がるからこそ、細分化が可能な世界になるのだ。
酒井ワイナリー 赤湯 NV

| 原産国 | 日本 / 山形県・南陽市 |
|---|---|
| 品種 | 欧州系の数種類のぶどうの混醸 |
今後も赤湯で生き物と共に暮らすために
車がない時代のブドウ農家は、収穫物を背負って山を登り降りしていたそうだ。「それに比べれば、全然楽」と酒井さんは言うが、比べる時代が…。やはり物事を捉える時間軸が長い気がする。昔は鳥上坂にある山々は全てブドウで覆われていたが、今は全盛期と比べると1/3から1/4まで減り、後5年程で更に景色は変わると予測されている。農家の高齢化が進むためだ。急斜面の畑を維持するのはコストがかかるし、危険も伴うので、後継ぎがいないのも理解できるが、急激に変わる景色には心が痛む。

急斜面での作業は恐ろしく大変なのは事実。危ないし。でも、それ以上の何かがあるのも事実。間違いなく、ブドウの品質は高い。そして景色もいい。暑い時に吹く風の気持ちよさは格別。人手と資金に余裕があれば、もっと広げていきたいが、今は、自分の9haの畑を形にすることに注力したいと思っている
と酒井さんは前を向いた。
その為には、一人当たりの管理面積を広げていく必要がある。機械化できるところは機械化するが、手間のかからない品種への切り替えが大事だと言う。
「例えば、耐病性があって薬の散布回数を減らせるようなブドウ。耐暑性があるもの。狸沢の畑にリースリングを植えていたが、昨今の暑さに耐えられなくなってきている。そして、収量を上げても品質が維持される品種。こういったものに切り替えていくことで、一人当たりの面積も増えるし、収量も増える。」
9haの畑は、ブドウ栽培に限る必要もない。
「近年の若者のアルコール離れは顕著。これは世界的な潮流で、ワイナリーとしては考えていかないといけない問題。うちはワイナリーで、今後もワインを造り続けていくが、『赤湯という場所で生き物と関わりながら暮らしていく』という軸で考えると、ブドウ以外を栽培して生計を立てることも含まれる。畑の一部を羊の牧草地とすることもあるし、果樹や野菜といった作物を育て販売することもある。」
「ブドウと人間しかいない環境は不自然」という考え方の酒井さんにとっては、自然な流れだ。赤湯という場所に根差しているからこその言葉。数年後、羊以外の動物が畑を闊歩しているかもしれないし、ブドウ以外の作物も展開しているかもしれない。多様性が増した畑から得られる酒井さんのワインの味わいは、きっとパワーアップしているに違いない。
 ▲
こうやって畑までの道のりを運転しながら、変わりゆく赤湯の景色を毎日見続けている酒井さん。酒井さんの赤湯への愛をひしひしと感じるインタビューでした。お忙しいところ、お時間頂き、ありがとうございました!
▲
こうやって畑までの道のりを運転しながら、変わりゆく赤湯の景色を毎日見続けている酒井さん。酒井さんの赤湯への愛をひしひしと感じるインタビューでした。お忙しいところ、お時間頂き、ありがとうございました!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。