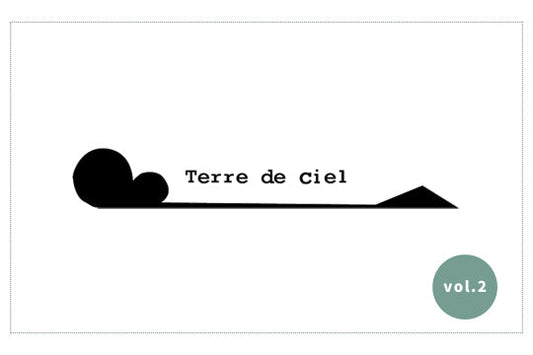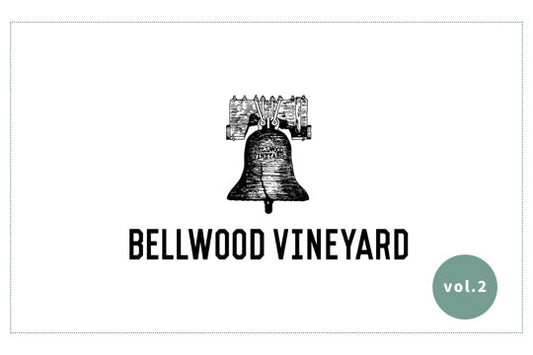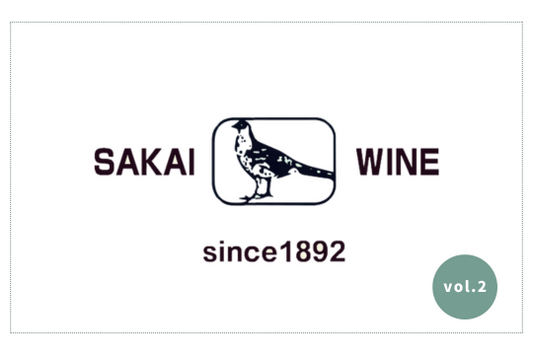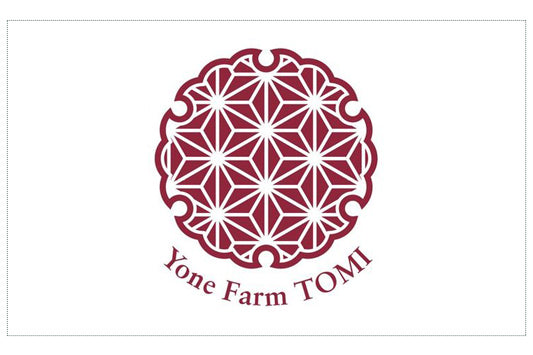日本ワインコラム | ソラリスシリーズ vol.2
マンズワイン最高峰のプレミアムワイン「ソラリス」シリーズを手掛ける小諸ワイナリー。営業部の島田さんと渡辺さんの計らいもあり、前回から約1年と間を空けず再訪することができた。翌週から梅雨入りするのだが、我々がお邪魔した日は快晴。暑かったぁ~!湿度はなく、日陰に入れば涼しいものの、標高が高い分紫外線は強く、日差しが痛いほど。そんなアツイ日に、チームの皆さんから激アツな話を沢山伺った。
 ▲ 前回同様、ソラリス愛、チーム愛溢れる話を沢山シェアして下さった島田さん。
▲ 前回同様、ソラリス愛、チーム愛溢れる話を沢山シェアして下さった島田さん。
 ▲ 新たにソラリスチームに加わった渡辺さんは、苦労も笑いに変えてしまう、ワイン愛とガッツの塊のようなお方。
▲ 新たにソラリスチームに加わった渡辺さんは、苦労も笑いに変えてしまう、ワイン愛とガッツの塊のようなお方。
ソラリスシリーズが生まれた背景やワインの美味しさの秘密については、前回のコラムに纏めているので参照頂きたい。確かに素晴らしい環境下でワイン造りが行われているが、条件全てに於いて恵まれているとも言いきれない。そんな中でも世界と肩を並べるワインを輩出している背景には、「制限」という存在や「基準」の不在に対してチームが真摯に向き合っていることも大きいと思われ、Vol.2となる今回はそこにフォーカスを当てたい。また、番外編として、小諸ワイナリーに訪れた際に足を運びたいスポットも紹介していく。
制限があることの難しさ~徹底的に考えるからこそ広がる可能性
小諸は冷涼な気候で、降雨量が少なく日照時間が長い、そして寒暖差が大きい内陸性の気候で、日本ではワイン用ブドウ栽培に向いている場所である。しかし、ソラリスシリーズを造る小諸ワイナリーがベンチマークとして捉えるのは世界の銘醸地だ。そうすると、否が応でも気候の違いや歴史の短さなどの様々な壁にぶち当たる。しかし、「難しい!」と嘆いて匙を投げるのではない。難しいからこそ挑戦し、高みを目指しているのだ。
有機という制限に挑戦する理由
世界に比べて圧倒的に降雨量が多い日本で有機栽培を行うことは極めて難しい。そんな中、前回のコラムの「有機栽培に挑戦する」という段落でも紹介した通り、2010年から有機栽培に挑戦し、現在は畑の40%程度が有機に移行済だ。有機JASの認定を受けているのは、市場にアピールしたいからではない。「JAS認定という制限があることで、ブドウ栽培に対して深く考えざるを得ないから認定を受けている」そうだ。病気の兆しが現れたらすぐ薬を撒いていては栽培者として成長しない。そもそも病気にならないためにできることを模索する。
「考え抜いた先にしか可能性は広がらない」
というのが栽培・醸造責任者の西畑氏がチームに説く姿勢だ。



▲(中央)徹底的に管理してもコウモリガの幼虫が樹に入り、食害を引き起こすことも。見つけたら即駆除するそう。
▲(右)最近導入された自動芝刈りロボット。草食の羊から「めぇちゃん」と名付けられた。戦力になるかどうか…?
島田さんはこうも言う。
「我々が自社で管理する畑の広さは12haのみ。全て有機にしたところで、周辺環境に与えるインパクトは微々たるもの。それよりも、有機でもブドウ栽培できるということを他の農家に示し、業界全体に影響を与えることの方が重要」と。
その観点で、日本固有品種のマスカット・ベーリーAを有機栽培し、そのワインが「Japan Wine Competition 2024」で金賞を受賞したことは意義深い。慣行栽培を続ける周辺農家に対しても、有機で高品質のものができるという結果を見せることができたのだ。一つ一つ結果を積み重ねることで、いつか大きな変化が生まれる。そんな予感を感じさせる話だ。
ないものは作る
ヨーロッパに比べ、日本ではワイン用ブドウの苗木を手に入れるのは難しい。ワイナリーの数が増える中、苗木不足も指摘されている。ワイン用ブドウは、フィロキセラという虫対策のため、フィロキセラに耐性のある北米系品種を台木とし、その台木にヨーロッパ系の品種を接いで1つの苗木にする。マンズワインの小諸ワイナリーでは、台木も栽培し、苗木作りまで行っている。昨年、3,000本ほど接いだというのだから、大規模だ!


▲ (右)台木のブドウの花の香りはとっても華やか!
分からないものは見つけにいく
小諸にワイナリーを開設して50年以上。日本の他のワイナリーに比べれば歴史は長いが、2000年以上の歴史があるヨーロッパの銘醸地とは雲泥の差がある。そんな中、徹底的に考え抜き、実践を繰り返すことで、ワインの味わいは1から2、2から4、4から8と、指数関数的に向上し、今では世界と戦えるワインとなった。しかし、一足飛びに越えられないものがあるー「テロワール」だ。
ヨーロッパでは「テロワールを表現したワイン」という言葉をよく耳にする。積み上げてきた歴史があるからこそ説得力のある言葉として、西畑氏以下チームは自分達のワインに用いることはなかった。出来上がったワインを「テロワールを表現した」と片づけてしまうのは「逃げ」である、と。


▲ (右)「ソラリス 千曲川 信濃リースリング クリオ・エクストラクション 2021」が「ヴィナリ国際ワインコンクール2023」の最高得点賞&グランド・ゴールドを受賞。国際的な評価が上がっている。「信濃リースリングの開発から40年近い時間が経つ。品種を確立するにはこれくらい長い年月がかかるということだ」と松宮さん。
自分達が造るワインの質に自信が深まる中、一定の条件を設けて複数醸造を重ねた上で共通化できる味わいを「テロワール」と呼んでもいいのではないか?という思いが強くなる。そして誕生したのが「ル・シエル」というキュヴェだ。「ル・シエル」は小諸ワイナリー近くの同一区画内で育つシャルドネ、信濃リースリング、ソーヴィニヨン・ブランの3品種を同日に収穫し、混醸(一緒に搾って発酵)して造る。一般的なブレンドは、品種毎に収穫・醸造し、最後に合わせるので、醸造責任者の意図が色濃く反映されるが、フィールド・ブレンド(混醸)は人為的介入が抑えられ、畑で育つブドウの味わいがダイレクトに反映される。2020年から始まったこのシリーズ。何年か後にチームから「小諸のテロワールは…」と説明される日も近いはず。楽しみだ。
制限(基準)がないことの難しさ~自らに厳しく品質を高める
前段では、制限を受け入れつつ、可能性を広げる取組みを紹介した。今度は逆に、制限(基準)がないことで生じる難しさにどのように対応しているかを紹介したい。
気候に合う品種が分からない
ヨーロッパのワイン法では、原産地呼称の認定を受ける品種が規定されているが、日本にはそういった規定はない。前回のコラムの「土地に合う品種を探し続ける」という段落でも紹介したが、小諸ワイナリーの敷地内には、1区画内に32品種が並ぶ品種園がある。ワイナリー開設時、小諸という気候に合う品種を探すべく育て始めたものだ。
 ▲
情報が全くない中で品種園を始めたことから、今では採用されないような畝の向きになっていたり、質より量を重視した仕立て方を採用していた後があったり…と、手探りで進めていた様子が随所に残る。
▲
情報が全くない中で品種園を始めたことから、今では採用されないような畝の向きになっていたり、質より量を重視した仕立て方を採用していた後があったり…と、手探りで進めていた様子が随所に残る。
50年という月日が流れ、小諸ではシャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、信濃リースリング、メルロ、東山はカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロが栽培適地だということが分かってきた。
 ▲ 2016年から広げたソーヴィニヨン・ブランの畑。暖かい年であっても、トロピカルフルーツ香だけでない、チオール化合物由来の青っぽい香りも表現されるようになり、自信を深めている品種だ。
▲ 2016年から広げたソーヴィニヨン・ブランの畑。暖かい年であっても、トロピカルフルーツ香だけでない、チオール化合物由来の青っぽい香りも表現されるようになり、自信を深めている品種だ。
 ▲ ソラリスシリーズが始まる前から、その品質の高さに注目していたという小諸にあるメルロの畑。
▲ ソラリスシリーズが始まる前から、その品質の高さに注目していたという小諸にあるメルロの畑。
しかし、気候変動もあり、今後もそうとは限らない。前回のコラムで、温暖化対策の一環でプティ・マンサンを試験栽培中と紹介していたが、昨年、初ヴィンテージが販売された。高温多湿な日本でも高品質なブドウができるのではないかと目を付けたのが約20年前。検討を重ね、2017年に苗木から栽培し、2019年に植え付けし、有機栽培で育ててきたものだ。
 ▲
マンズワインHPより。プティ・マンサンの醸造を担当した小山氏。小諸ワイナリー栽培・醸造責任者である西畑氏の後任となるべく、取材の前週にフランス、ディジョンに向けて出発した。現地の「今」を沢山吸収して戻られる日を、首を長くしてお待ちしています!
▲
マンズワインHPより。プティ・マンサンの醸造を担当した小山氏。小諸ワイナリー栽培・醸造責任者である西畑氏の後任となるべく、取材の前週にフランス、ディジョンに向けて出発した。現地の「今」を沢山吸収して戻られる日を、首を長くしてお待ちしています!
一方、苦戦を続けているのがピノ・ノワール。小諸と東山の両方で栽培を続け、ソラリスシリーズでスパークリングワインを展開しているが、赤ワインとしてはGOが出ていない。小諸では、ワイナリーより更に高地へ登り、標高900mに位置する「飼場」地区で2014年から栽培している。ブドウが色付く頃までは順調に成長するものの、その後の成熟度合いに納得できない(単に求めるレベルが高いだけなのかもしれないが…)。根が土壌深くまで育つよう耕起作業を行うなど、対策を取り始めたとのこと。西畑氏は、「最終的には切ってもいい。だけど、やれることはやった上で判断する」と言い切る。
 ▲ 冷涼な小諸の中でも、更に標高の高い場所で育つピノ・ノワール。ソラリスの赤として登場する日が待ち遠しい。
▲ 冷涼な小諸の中でも、更に標高の高い場所で育つピノ・ノワール。ソラリスの赤として登場する日が待ち遠しい。
しがみつかないが、すぐに諦める訳ではない。やれることは全てやった上で、潔く判断する。この清々しい精神がただただカッコいい。
収量制限といった規定もない
ヨーロッパのワイン法では、収量規制も明確だ。この場所でこの品種を育てるのであれば、この収量に抑えないと品質が保てない、という長年の経験値が明文化されているのだ。もちろん毎年気候は異なり、質に差はあるので、規定が実態に即していない年もあるだろう。だが、よりどころがあるとないとでは、生産者にかかる精神的負担は大きく違う。
前回のコラムの「最高レベルの収量制限」で紹介した通り、マンズワインでは、質の高いブドウ房のみを選び、他の房を落とすことで、残した房へ養分を集める摘房作業を行っている。トップキュヴェでは一つの枝に一房だけ残す徹底ぶりだ。また、収穫時にも、手作業で病気の実などを排除していく。 そこまでやっても終わらない。選果台ではスタッフによる徹底的な選果が実施されるが、最後の砦として、選果台の端に西畑氏が仁王立ちになり、ブドウを実際に嗅いで、少しでも違和感があれば、バサっとブドウを捨てるらしい!!鬼軍曹、西畑である。
 ▲ 手前にあるのが選果台。両側にスタッフが並んで選果する。
▲ 手前にあるのが選果台。両側にスタッフが並んで選果する。
 ▲ 鬼軍曹と呼んでスミマセン!実物は熱い気持ちを持ちつつ、穏やかな語り口で周りを魅了する素敵な方です!
▲ 鬼軍曹と呼んでスミマセン!実物は熱い気持ちを持ちつつ、穏やかな語り口で周りを魅了する素敵な方です!
この鬼軍曹、鬼スタッフ達は、契約農家のブドウにも容赦ない。今でこそ契約農家と密なコミュニケーションを取り、二人三脚でブドウ栽培を行っているが、初期からそうだったわけではない。果樹栽培経験の長いブドウ農家の常識とワイン用ブドウ栽培の常識が相容れないこともあり、衝突も起きたそう。その昔、契約農家毎に行われる選果で、農家の目の前でばっさりブドウが廃棄されることもあったというのだからシビアな世界だ。裏を返せばプロフェッショナル同士として認め合っているからこその行動。スタッフも契約農家も立場は同等。自分にも他者にも厳しく律し、質を維持しているのだ。
最低限のもので時代に沿った味わいを最大限に表現する
マンズワインは大手だ。醸造設備もある程度のものは揃えられる。しかし、「設備は決して最新鋭というわけではない」と島田さんは言う。選果用のレーザーを使ったオプティカル・ソーティングがある訳でもないし、機材もコンピュータ制御されていない。水も蛇口を自分でひねって調整する。ではどういったところに秘密があるのだろう?
まず徹底しているのが、醸造施設内の衛生管理。機材の洗浄は当たり前だが、床に流れ落ちた水分もキレイに拭き上げる。菌の発生を徹底的に抑え、汚染を防ぐ。床に水分が残っていると、鬼軍曹西畑が現れ、こっぴどく叱られるそうだ。
 ▲
醸造所内を手際よく動き周るチームの皆さん。
▲
醸造所内を手際よく動き周るチームの皆さん。
目指すスタイルに合わせ、ワイン醸造の手法も徐々に変化させている。例えば、醸造所には1万L級の大きなタンクもあるが使用せず、3,000-4,000Lくらいの大きさのものを用い、小分けで仕込んでいる。ヘッドスペースにガス充填するタイプのステンレスタンクもあるが、落し蓋形式のステンレスタンクを新たに導入したそう。酸化を防ぎつつ、仕込む容量も柔軟に対応できるし、充填用のガス代もかからない。タンクも日々進化しているのだ。
 ▲
数多くのステンレスタンクが並ぶ。
▲
数多くのステンレスタンクが並ぶ。
 ▲ 蓋が落し蓋形式になっているのが分かる。
▲ 蓋が落し蓋形式になっているのが分かる。
ワインを移動させるポンプも進化している。昔はスクリュー形式でブドウを優しく扱うことが難しかったが、今は血液透析などにも用いられるチューブポンプを用いている。
 ▲
卵の黄身が割れないくらい優しくワインを扱うことができるというチューブポンプ。
▲
卵の黄身が割れないくらい優しくワインを扱うことができるというチューブポンプ。
樽との付き合い方にも変化が。ヨーロッパ産を使い続けているが、リスクヘッジも兼ねて多種多様なメーカーのものを取り揃えている。ヘッドまで焦がしたものを試したこともあるが、今はミディアムトーストで落ち着いているそう。ブドウの質が高くなってきたからこそ、樽はブドウの風味を助けるものと位置付けし、新樽または1年樽を使うソラリスシリーズでも新樽比率を下げつつある。また、昔はバリック(225L)で仕込んでいた白ワインは、今では450-500Lに切り替え、樽の風味を柔らかく抑えるようにしているそうだ。なお、樽熟成の間、蒸発する水分をワインで補填する作業がある。補填する量は極めて少ないことから、別の種類のワインを用いる造り手も数多くいるが、ソラリスでは徹底して同じワインを用いて補填する。また、補填の際には、「樽ぎりぎりまで入れるが、こぼすな!こぼしたら徹底的に洗浄せよ!」という厳しい指示が西畑氏から出ているそう…ワインがこぼれたところから汚染が始まるからだそう。
 ▲ 様々なメーカーの樽が並ぶ様子。
▲ 様々なメーカーの樽が並ぶ様子。
 ▲ ワイン補填後も、樽はキレイな状態なのが分かる。
▲ ワイン補填後も、樽はキレイな状態なのが分かる。
「一つ一つの作業を考えて行うこと、そして細かいことを繰り返すこと」、と島田さんは言う。
シンプルに聞こえるが、徹底することは難しい。これをチーム全員で共有し実践しているからこそのソラリスシリーズの味わいなのだ。
歴史の長さを誇るマンズワイン、そして世界の銘醸地と互角に戦うソラリスシリーズは、日本ワインのトップランナーと言っても過言ではないだろう。だからこその難しさは常に付きまとう。なにせ前例がないのだから。
だから、一人一人がとことん考える。
そして、徹底的に実践する。
もし不具合が見つかれば、どうすればいいのか更に考えて実践する。
たとえ長く時間を費やしたものであっても、時には潔く諦める。
その費やした労力は決して無駄にはならず、自らの血肉となるし、後進のための道にもなる。
荒波に一人で立ち向かうのは心が折れてしまいそうだが、チームであればできそうな気がする。畑の広さや施設の規模を考えると10人という職員の数は多くないが、結束力はピカ一だ。この結束力があるからこそ、世界という荒波に真っ向から勝負できるのだろう。
常に新しい取り組みにチャレンジしているソラリスシリーズのチームの皆さん。
次にまたお会いできる日を楽しみにしています!



~番外編:ワイナリー内外を歩き、信州の風土を感じる~
現在、日本には約500のワイナリーがあると言われているが、「産地形成できているとは言えない」と島田さんは言う。例えば、ブルゴーニュという場所。細かく見ると様々な違いはあるが、長い歴史を経て、共通認識として語られる栽培環境がある。一方の小諸。マンズワイン小諸ワイナリーと最寄りのワイナリー「テール・ド・シエル」では、栽培環境は非常に異なり、小諸という区切られた場所でも一括りする難しさがある。だからこそ現地に足を運び、肌で環境を感じてもらいたい、というのが島田さんの願い。東京からであれば、新幹線で1時間半程度だ。
直ぐにチケット予約して出発して頂きたいところだが、「そんな時間ないよ~」という方。こちらを読んで雰囲気を味わって頂きたい!
 ▲ すっきりした青空と遠目に山々が広がる景色。この空気を吸うためだけでも訪れたくなる。
▲ すっきりした青空と遠目に山々が広がる景色。この空気を吸うためだけでも訪れたくなる。
弁天の清水で自然の恵みを感じる
ワイナリーから徒歩10分程にとっておきの場所がある。小諸市は浅間山の南麓に位置していることから標高が高く、街全体が坂で起伏に富んだ場所だ(隣の「佐久平」も十分に坂が多い場所ではあるが、地元の人から見ると「平」な場所だそう。坂に対する耐性が違う。笑)。木漏れ日の中を周辺の山々を拝みつつ歩き続けると、民家が並ぶ狭い路地に入る。
 ▲ 映画「トトロ」にでてきそうな場所。暑くても木漏れ日の下では涼しい。
▲ 映画「トトロ」にでてきそうな場所。暑くても木漏れ日の下では涼しい。
 ▲ 棚田も美しい。新米が楽しみだ…
▲ 棚田も美しい。新米が楽しみだ…
そして到着したのが、浅間山を水源とした湧き水がでる「弁天の清水」。硬水が多い浅間山系の中で唯一、軟水が湧き出る場所だ。水量も多く、地元の方も普段から容器片手に水を汲むなど、生活の一部として愛されている。


「小諸は近くに川があり、夏には蛍も見られる。ワインを語る際に水に着目することが多くないが、これだけ自然豊かな場所だということが分かると思う」、と島田さん。
ワイナリーでは洗浄のために水を沢山使うが、地下水を利用しているとのこと。前回の東山の「鴻ノ巣」と呼ばれる堆積岩の地層訪問に引き続き、今回は天然の湧き水と来た。美味しい空気と合わせると、生物にとって不可欠な「土、水、空気」という重要な構成要素が豊かな場所だと気付かされる。こんな贅沢な環境にあるからこそ、最高峰のブドウが育つのだろう。



ワイナリーの中で信州を感じる:万酔園
ゆっくり時間を割いて、街全体を散策するのが望ましいが、哀しいかな、「タイパ」が語られる世の中だ。そんな忙しない現代人でも、小諸ワイナリー内の本格的な日本庭園「万酔園」に足を運べば、小諸や信州の風土を存分に感じられる。
 ▲ 「万酔園」という名前は、マンズワインの親会社であるキッコーマンの「マン」という音を掛け合わせた上で、「万人の方に庭園の美しさに、目でも酔って欲しい」という思いを込めて付けられた。
▲ 「万酔園」という名前は、マンズワインの親会社であるキッコーマンの「マン」という音を掛け合わせた上で、「万人の方に庭園の美しさに、目でも酔って欲しい」という思いを込めて付けられた。
 ▲ 海外のワイナリーに庭園が併設されていることに着目したキッコーマン創業家である茂木家が11年かけて作った庭園だけあり、見応えが素晴らしい!
▲ 海外のワイナリーに庭園が併設されていることに着目したキッコーマン創業家である茂木家が11年かけて作った庭園だけあり、見応えが素晴らしい!
庭園には信州の要素があちらこちらに埋っている。例えば、庭園全体は、浅間山の傾斜を模して、高低差のある三層式。170種類、11,000本の樹木を全国から取り寄せ、山の景色を再現している。日本アルプスや浅間山を表現した樹々があり、大きくうねる千曲川に模して配置された川は、日本海をイメージした池に流れ着く。



▲ (右)その原木で造られたワイン。2023年は1本のみ。「わざわざワインを仕込むなんて、西畑にはカワイイところがあるんですよ」と、松宮さんは優しい眼差しで語る。
そして、庭園の地下にはセラーが広がっている。通常は非公開だが、ワイナリーツアーや特別なイベントでは開放されるようなので、ぜひ庭園と合わせて訪れてほしい。
 ▲ セラー入口で満面の笑みをみせてくれた島田さん。
▲ セラー入口で満面の笑みをみせてくれた島田さん。
ライブラリー、テイスティングルーム、そしてVIPルームがあり、年代物のワイン、100年前のフランスの修道院にあったと言われるステンドグラス、龍眼を模したシャンデリア、ポル・ロジェからもらったピュピトル(シャンパンを造る過程で澱を瓶口に集めるための道具)、ワインに関する国内外の貴重な書籍、松本民芸家具、などなど、見所に溢れている。ワインの歴史や文化的要素を感じることができる場所だ。
 ▲ テイスティングルームには年代物のワインが並ぶ。
▲ テイスティングルームには年代物のワインが並ぶ。
 ▲ ライブラリーには国内外の貴重なワインに関する書籍が並ぶ他、龍眼を模したシャンデリアも。
▲ ライブラリーには国内外の貴重なワインに関する書籍が並ぶ他、龍眼を模したシャンデリアも。


様々な楽しみ方ができるのが小諸ワイナリーの魅力。ワイナリースタッフによる畑、万酔園、地下セラーの案内とテイスティングが楽しめるツアーもあるようなので、ぜひオススメしたい!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。