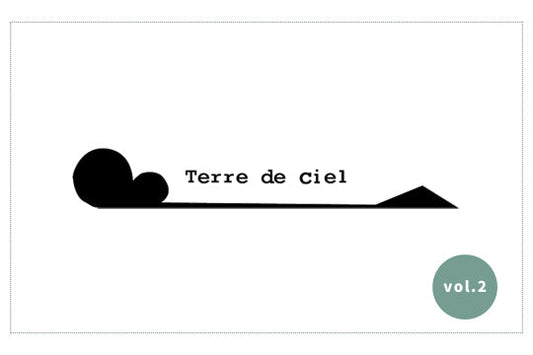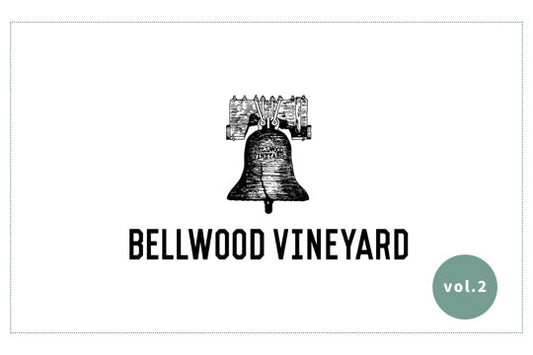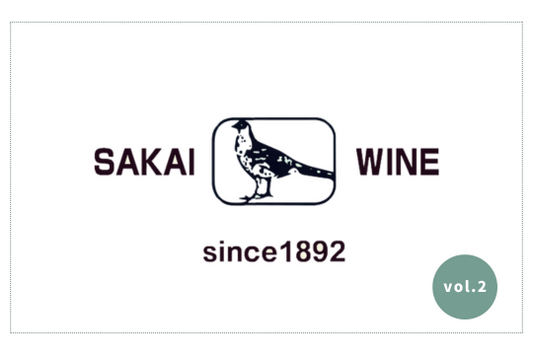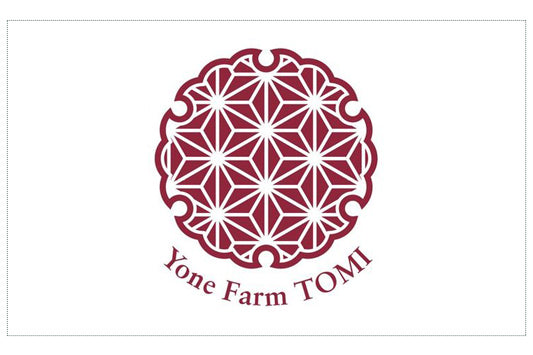日本ワインコラム |高畠ワイナリー
夏休みが始まるこの時期。一年で一番暑いとされる大暑入りが前日に発表されただけあり、インタビュー当日も朝から異常に暑い!!東北地方だから暑さはマシだろうなんて思うのは大きな間違い。山形県は四方を山で囲まれた山形盆地により、熱が溜まりやすい環境にある。そして、1933年に40.8℃という気温を出し、2007年までの74年間、日本の観測史上最高気温を誇った場所でもあるのだ。
そんな山形盆地から南に下り、置賜というエリアにあるのが、今回のインタビューのお相手の所在地、高畠町だ。『まほろば(「周囲を山に囲まれた平地で、住みよい美しいところ」という意味)の里』と呼ばれる町で、平坦部では稲作が、山間部ではブドウなどの果樹が栽培される実り豊かな土地である。しかーし、置賜も盆地なので、夏は暑い!朝からお邪魔したが、一瞬にして滝汗が流れる…。
今回は、そんな暑さをものともしない、高畠ワイナリーの皆さんが目指すワイン造りについて話を聞いてきた。
 ▲ 赤い屋根が目を引く建物。
▲ 赤い屋根が目を引く建物。
 ▲ ワイン樽を使った看板を見るだけで、ワインが飲みたくなる。笑
▲ ワイン樽を使った看板を見るだけで、ワインが飲みたくなる。笑
ワイナリー名に込められた思い
高畠は四方を山々に囲まれた置賜盆地の南部に位置する。山間部を利用する形でブドウ栽培が始まったのは、明治時代。欧州系ブドウが試験栽培されたが、ヨーロッパとの栽培環境の違いや当時の技術力では栽培が難しく、広がりは見せなかった。しかし、明治から大正にかけて始まったデラウェアの栽培が大成功。今では、日本一のデラウェアの産地として知られるほどに成長している。成功のカギとなったのが高畠という栽培環境だ。夏から秋にかけて盆地特有の昼夜の寒暖差が大きく、ブドウ栽培に適している。また、4月から10月のブドウ生育期間の降水量は800-900mmと比較的少ない。更に、海底から隆起した山間部の地層には、海洋生物の化石が多く、ミネラル分も豊富。排水と保水のバランスが良いのだ。
 ▲
羊のようなモコモコした白い雲と水色の空、緑が美しい田んぼ、そして遠目の山々!なんて美しい景色…。
▲
羊のようなモコモコした白い雲と水色の空、緑が美しい田んぼ、そして遠目の山々!なんて美しい景色…。
そんな生食用ブドウ栽培の歴史が長い置賜地区で、初の「観光ワイナリー」として1990年に誕生したのが、高畠ワイナリーだ。当時の親会社(南九州コカ・コーラボトリング)が塩尻市で「太田葡萄酒」を運営していたが、住宅街で手狭になったこともあり、酒造免許を移転する形で高畠ワイナリーが誕生したのだ。設立当初は、高畠町産のブドウと海外からの輸入原料を合わせたワイン造りだったが、徐々に地元産原料に軸足を移し、現在は63軒の契約農家を中心にブドウを仕入れる他、自社畑での栽培にも力を入れるようになっている。
 ▲
皆さん、こちらの会社のポロシャツをお召しになっていました!なんかいいな~。
▲
皆さん、こちらの会社のポロシャツをお召しになっていました!なんかいいな~。
ブドウの栽培環境がワインの味わいに与える影響が大きいのは周知の事実だが、地名を名称に付しているワイナリーの数はそこまで多くはない。そんな中、高畠ワイナリーが「高畠」という地名を明確に打ち出しているのは、「高畠」の認知度を上げたい、ブドウ産地として盛り上げたい、そして観光の拠点としても活性化していきたいという思いの表れ。『「高畠」を世界のワイン産地の一つにする』という大きな使命を掲げ、ワイン造りに向き合っているのだ。
長く続く契約農家との関係
ワイナリーで仕込むブドウの量は年間約460トンと大量だ。もっとも、農業法人としてではなく、醸造を軸に事業がスタートしたという経緯もあり、国産原料のうち、自社ブドウは4%程度で、殆どは契約農家を中心とする買いブドウでワインを仕込んでいる。共存関係が始まったのは、1991年。昔から生食用のブドウ栽培を続ける農家の知見を活かしたいと、「高畠ワインブドウ部会」を立ち上げ、契約農家と共に醸造用ブドウの栽培に取り組んだ。目を付けたのは、デラウェア栽培で昔から培われてきた雨除けハウス(サイドレス)の棚仕立て。側面がオープンになっているので、雨除けしつつ適度な水分ストレスを与えると共に、通気性を確保できる栽培方法で、質の高いブドウが収穫できると分かり、現在も採用している。27名でスタートした契約農家との共存関係は、今では63軒まで増加。長い時間をかけ、信頼関係を築いていることが分かるだろう。
 ▲
高畠ワイナリーHPより。上面のみビニールが張っているのが分かる。
▲
高畠ワイナリーHPより。上面のみビニールが張っているのが分かる。
問題が全くないという訳ではない。

2024年は特に雪が多くて、サイドレスハウスが壊れたところも多かった。では、高齢化している農家が大枚をはたいてハウスを修理するかというと、そうとも限らない。これを機に農家を引退する人が多い
と営業部長の木村さんが実情を教えてくれた。
農家と二人三脚で歩んできた高畠ワイナリーにとって、農家の高齢化や離農は難しい課題だ。そのような背景も多少影響しているのだろう、高畠ワイナリーでは自社畑を拡充しつつある。次章で詳しく見てみたい。
大量生産と真逆のワイン造りを目指して~自社畑での取り組み
高畠ワイナリーは2012年、大量生産と真逆のワイン造りを掲げ、自分達で手間暇をかけてブドウを栽培し、自社ブドウから質の高いワインを造ろうと「Garagiste Winery(ガレージステ・ワイナリー)構想」を立ち上げた。中でも、上質なボルドースタイルの赤ワイン造りを目指し、準備を進めてきている。畑ではどういった取り組みをしてきたのだろう?原料栽培担当の四釜さんに色々と話を伺った。
 ▲
「好きな作業は、今後を考えながら行う剪定。嫌いな作業は、終わりの見えない誘引。一日で色んな畑に行くことができるので、意外に草刈りも好き」、と話してくれた四釜さん。優しい笑顔と控え目な人柄に温かみを感じる。
▲
「好きな作業は、今後を考えながら行う剪定。嫌いな作業は、終わりの見えない誘引。一日で色んな畑に行くことができるので、意外に草刈りも好き」、と話してくれた四釜さん。優しい笑顔と控え目な人柄に温かみを感じる。
教科書がない難しさを乗り越えて
ワイナリーの前に広がる4haの自社畑では、主に「露地×垣根仕立て」で、以下ブドウ品種を栽培している。
白ブドウ:シャルドネ、ヴィオニエ、ピノ・グリ
黒ブドウ:カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、ピノ・ノワール、カベルネ・フラン
 ▲ ワイナリー入口には自社畑の場所が分かる看板がある。
▲ ワイナリー入口には自社畑の場所が分かる看板がある。
 ▲
高畠ワイナリーHPには、自社畑の位置関係が詳しく掲載されている。
▲
高畠ワイナリーHPには、自社畑の位置関係が詳しく掲載されている。
畑は、シルバー2名のサポートを得つつ、四釜さん+1名で管理。広い場所を少ない人数でカバーするのは大変な作業だ。もともと栽培に興味がおありだったのだろうか?
「会社から『やれ』って言われたから始めたんです」、と四釜さん。
「そうだったけ?そんなことなかったと思うけどな~。それに、四釜の実家はブドウ農家なんですよ」、と高橋社長は鷹揚に答える。
 ▲ 暑い中、一緒に畑を案内して下さった高橋社長。
▲ 暑い中、一緒に畑を案内して下さった高橋社長。
むむ?認識が少し違うような…笑。確かに、四釜さんのご実家はデラウェアを主体に栽培するブドウ農家で、ブドウ栽培に馴染みはあったが、醸造用ブドウ栽培の経験はない。四釜さんは振り返る。

生食用のデラウェア栽培には、長い歴史を経て完璧なマニュアルがあるけど、醸造用ブドウにはない。ましてや垣根栽培は見たこともやったこともなかったので、正に手探り。県内には、垣根栽培を長く続けるタケダワイナリーは存在するけど、同じ山形県とはいえ栽培環境は大きく異なります。例えば、タケダワイナリーのある上山に比べて、高畠は雪深く、冬には1.5m近く積もる。
「垣根栽培を始めてみたものの、雪の重さでブドウ樹が倒れてしまったことも。こういった経験を経て、今はフルーツゾーンを1m前後まで高くして雪の重さに対応できるような仕立てを採用しているが、栽培を始めた頃は、本当に苦労しました。」
会社のバックアップはあるものの、皆の期待を背負って、未知の領域に切り込んでいくのは不安も大きかっただろう。四釜さんは淡々と振り返っておられたが、聞いているこちらは、胃がぎゅーっとなる。
徹底的な土造りを
ワイナリー直ぐそばに、2007年植樹のピノ・ノワールの畑がある。地力の強い土壌で、「どろどろしていたほど」と四釜さんは振り返る。土に栄養がありすぎると樹勢が強くなり、ブドウは実を付けるよりも枝を伸ばそうとしがち。そこで、もともとあった土を掘り出した上で、南陽市の山砂や保湿調整機能に優れた高畠石の砕石などを運び入れ、全面60㎝盛り土した他、地下に排水用の暗渠も通し、水はけの良さを確保したそうだ。25a程の広さの土を全て入れ替えるのは、かなりの重労働…社員で頑張ったというのだから、目が点になる。確かに水はけの良さは確保できたのだが、今度は土が痩せすぎてしまったという。そこで木の皮でできたバーク材を入れて土造りを続けて、今に至るそうだ。
 ▲
今年は雨が少なく、草刈りの回数も少ないそう。このまま順調に収穫まで成長してほしい!
▲
今年は雨が少なく、草刈りの回数も少ないそう。このまま順調に収穫まで成長してほしい!
 ▲
社員一丸となって行った土壌改良のおかげで、「どろどろしていた」とは想像できない。
▲
社員一丸となって行った土壌改良のおかげで、「どろどろしていた」とは想像できない。
暗渠はピノ・ノワールの畑以外にも、カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランなどの畑にも導入済。また、2011年と2017年に整備した畑には、ドリップ・イリゲーション(点滴灌漑)を完備し、ブドウの根元にゆっくりと灌水できる環境を整えている。今年のように雨が極端に少ない年には、なくてはならない存在だ。
 ▲ 地表近くにある黒い線がドリップ・イリゲーション。
▲ 地表近くにある黒い線がドリップ・イリゲーション。
栽培リスクの高い品種にチャレンジする
自社畑では、契約農家にはリスクが大きくて依頼できない品種の栽培にも挑戦している。その筆頭が、晩熟型で天候に左右されやすい、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロといったボルドースタイルの品種で、2017年に植樹した。その後、カベルネ・ソーヴィニヨンは2020年に畑を拡張した他、樹齢24年のカベルネ・ソーヴィニヨンを2023年に伐根した上で、今年の春に600本以上の苗木を植樹するなど、栽培量を増やしている。上質なボルドースタイルの赤ワインを造ると掲げた方針が、着々と実を結びつつあるのだ!
 ▲
今年の春に苗木を植樹したカベルネ・ソーヴィニヨンの畑!成長が楽しみだ。
▲
今年の春に苗木を植樹したカベルネ・ソーヴィニヨンの畑!成長が楽しみだ。
もちろん難しさもある。
カベルネ・ソーヴィニヨンは樹勢が強く、剪定しても想定していた方向に枝が伸びてくれない難しさがある。カベルネ・フランも樹勢は強いが、枝が真直ぐ伸びるので管理はしやすい。ただ、着色に難しさがある。温暖化の影響で、これまでは4年に1度着色が難しいくらいだったのが、最近は3年に1度いい年がある程度
と四釜さんは吐露する。昨今の異常な暑さを受け、カベルネ・フランの除葉は控えめに行うなど、対策を打っているそうだ。また、垣根栽培で育てていたカベルネ・フランとメルロのうち、一部が雪の重さで潰れてしまったため、サイドレスハウスの棚栽培に切り替えたところも。ビニールハウスは温度が上がりやすく、カベルネ・フランの色付きに悪影響が出やすいので、短いビニールを使って風が抜けるような工夫も加えているそうだ。地道な試行錯誤に頭が下がる。
 ▲
サイドレスハウス×棚栽培のカベルネ・フラン。写真右上を見ると、ビニールに隙間があり、風通しを確保しているのが分かる。
▲
サイドレスハウス×棚栽培のカベルネ・フラン。写真右上を見ると、ビニールに隙間があり、風通しを確保しているのが分かる。
 ▲ たわわに成長しています!美味しそう…
▲ たわわに成長しています!美味しそう…
実験的に栽培してみて数を増やしている品種があるー2017年に植樹し始めたヴィオニエだ。「社長の想いが強すぎて」と周りから揶揄されながらも、「結構周りからも『美味しい』と評価が高いんですよ!」と意に介していない高橋社長。ほのぼのした関係に、思わず周りも笑顔になる。ヴィオニエはシャルドネよりも皮が厚く、雨が降っても病気になりにくいという良さがある一方、房が付かない枝があるなど、収量が少ない難しい品種でもある。垣根栽培を続けてきたが、次は棚栽培にトライし、収量の様子をみたいと四釜さんは意気込む。畑を始めた頃のおっかなびっくりの試行錯誤とは質が異なるが、色んな可能性を模索して実験しながら血肉に変えていくというスタイルは変わらない。
 ▲
雨が原因で、果実がカビで腐敗してしまう晩腐病対策として、フルーツゾーンにビニールをかけるレインカットを導入している。
▲
雨が原因で、果実がカビで腐敗してしまう晩腐病対策として、フルーツゾーンにビニールをかけるレインカットを導入している。
有機の畑にチャレンジする
実は、高畠は約50年も前から有機栽培が行われてきた、日本における有機栽培の先駆け的な場所だ。高畠ワイナリーも1997年から契約農家と共に無農薬栽培の研究をスタートし、2003年に「高畠ワイン有機ぶどう研究会」を設立。3年間の有機栽培への転換期を経て2006年に念願の有機JASの認定を受け、国内初の有機認定デラウェアワインを醸造している。


高温多湿な日本で有機栽培を行うことは難易度が高い。農薬が撒けない=虫との戦いだ。
メンバーの契約農家が徐々に研究会から脱退する中、2017年に高畠ワイナリーが畑を引き受けた。有機肥料しか与えられないので、ブドウ樹の成長はゆっくりだし、虫との戦いにくじけそうにもなる。だけど、「プライドの問題」だと皆さん口にされた。やり始めたからにはとことん向き合う!プライドを持って畑と向き合っているのだ。
 ▲
ネズミがブドウの樹をかじって歯を研ぐとのこと(やめて~)。対策として、樹の下の方をガードしている。
▲
ネズミがブドウの樹をかじって歯を研ぐとのこと(やめて~)。対策として、樹の下の方をガードしている。
 ▲
小さなカエルを発見!かわいい…と思ったが、「カエルがいる=虫がいる」ということだそう。有機栽培の難しさを痛感する。
▲
小さなカエルを発見!かわいい…と思ったが、「カエルがいる=虫がいる」ということだそう。有機栽培の難しさを痛感する。
大量生産と真逆のワイン造りを目指して~醸造所での取り組み
海外原料も含めた大量のワインを醸造してきた歴史もあり、醸造所は大きい。1990年の創設後、90年代後半に3回増設し、施設を広げてきた。3度目の増設と同じ1998年に入社したのが、製造部長の松田さん。入社当時は赤ワインブームだったこともあり、ひたすら赤ワインの充填を行ったり、デラウェアを使った甘口のワインを造ったりしていたと振り返る。そんな時代を経て、2012年の「ガレージステ・ワイナリー構想」の立ち上げ以降、上質で凝縮感のある「ボルドースタイルのワイン」を造るため多種多様な設備を導入。現在も進行形の様々な改革についてお話を伺った。
 ▲
松田さんはオリンピックを目指していたこともあるほどの陸上成績を持つアスリートでもある。今も地元の高校のコーチを行う指導者だ。
▲
松田さんはオリンピックを目指していたこともあるほどの陸上成績を持つアスリートでもある。今も地元の高校のコーチを行う指導者だ。
徹底した選果を心掛ける
収穫の時期になると、醸造所には大量のブドウが運ばれる。契約農家から納品されたブドウは、色や糖度などをベースに細かくランク分けを行い冷蔵庫で保管する。四釜さんは、このランク分けを主導するため、自社農園の収穫には立ち会えないそうだ。ブドウ栽培のフィナーレに立ち会えないのは寂しい気もするが、そんな悠長なことを言っていられないくらいにブドウが運びこまれるのだろう。一方の松田さんは、ランク分けされたブドウを次々に醸造に回し、冷蔵庫のスペースを確保する。年間約80種類のワインが造られているのだ。
赤ワインの品質向上に劇的な変化をもたらしたのが、2020年に導入した選果機能付き除梗機だ。腐敗果や未熟果はもちろん、ブドウの茎などを取り除くことができ、青臭さがなくなった。2021年には除梗機の後に手選果も加えてみたところ、更に品質が上がった。以降、松田さんは除梗機+手選果の二段階の選果を徹底しているそうだ。
 ▲ 今年の稼働を待つ選果機能付き除梗機。
▲ 今年の稼働を待つ選果機能付き除梗機。
 ▲
高畠ワイナリーHPより。選果を見学していた際、「手伝えと駆り出された」、と笑って教えてくれた高橋社長。社長であっても一緒に汗を流す。どこまでもフラットな関係がいいな~。
▲
高畠ワイナリーHPより。選果を見学していた際、「手伝えと駆り出された」、と笑って教えてくれた高橋社長。社長であっても一緒に汗を流す。どこまでもフラットな関係がいいな~。
小ロットでの仕込みを可能に
選果を徹底し、細かくランク分けされたブドウを小ロットで醸造できるよう、小型のタンクの導入を進めてきた。2014年に導入した温度管理が可能な密閉型小仕込みタンクを皮切りに、タンク全体に温水/冷水を循環し、発酵温度を管理する設備を導入した他、赤ワイン醸造用の小仕込みタンクや卵型の小仕込みタンクなどを導入。ロット毎に仕込むことで味わいの幅が広がり、ブレンドの進化が図れた他、「小仕込専用タンク」×「温度管理」を導入したことで、長期熟成タイプの赤ワインの仕込みが可能となってきたのだ。
 ▲
タンク全体に温水/冷水を循環させるチラーは、設備屋さんの手作りだそうだ。
▲
タンク全体に温水/冷水を循環させるチラーは、設備屋さんの手作りだそうだ。
 ▲
小型タンクは高さがあるものを採用することで、酸素との接地面積が減り、酸化が少なくなる。卵型も酸素の接地面積が少ない他、果皮が浮きにくいという効果もある。
▲
小型タンクは高さがあるものを採用することで、酸素との接地面積が減り、酸化が少なくなる。卵型も酸素の接地面積が少ない他、果皮が浮きにくいという効果もある。
瓶内二次発酵への挑戦
高畠ワイナリーでは、2006年から炭酸ガス注入方式によるスパークリング・ワイン「嘉Yoshi」を、2014年ヴィンテージからは、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵にチャレンジした「醗泡 プリーズ・デ・ムース」も販売してきた。後者は、「ジャパン・ワイン・チャレンジ 2024」で2つのトロフィーを受賞した実績があるが、瓶内発酵期間が4年8ヶ月と長く、手作業で澱下げを行うことから、価格帯は高め。ハレの日用のスパークリング・ワインだ。
 ▲ たまご型タンクの前にあるのがジャイロパレット。
▲ たまご型タンクの前にあるのがジャイロパレット。
一方、2022年ヴィンテージからスタートした「穣Minori」は、瓶内発酵期間を10ケ月(2023ヴィンテージは1年2ケ月)に短縮した他、澱下げをジャイロパレットという機械を導入することで効率化を図り、価格を抑えて展開している。因みに2023年ヴィンテージは、定評のある高畠のシャルドネ100%で仕込まれている。驚くなかれ、高畠ワイナリーは全国のシャルドネ収穫量の約10%を占める程、毎年大量のシャルドネを仕込んでいるのだ。その中からフルーティーで凝縮感のあるブドウを選定して造ったそう。是非お試しを!
高畠ワイナリーの一覧は🍇こちら
データを取得する
ワイナリーの一角には、アルコール度数や、糖度、酸、PH値などのデータを測定する機械が置かれている。ラボに送ることなく、ワインの品質をその場で正確にモニタリングできるので、品質管理の観点で非常に重要な要素となっている。
 ▲ 瞬時にデータが取得できるのが嬉しい!
▲ 瞬時にデータが取得できるのが嬉しい!
また、目指すスタイルのワインのデータを取ることも可能だ。赤ワイン好きを公言する松田さんは、特に「濃くて強いけど、今すぐ楽しめる」赤ワイン造りを目指している。「オーパスとマルゴーが融合したような赤ワインを造る!と言ってきたのだけど、温暖化の影響でボルドーでも果実が熟しやすくなってきているせいか、2019年のマルゴーが正に自分が目指してきたワインを造ってしまった。なので、今はオーパスとラトゥールが融合した赤ワインと言っている。笑」と明かしてくれた松田さん。
自分達が目指すワインを真摯に研究することで、取るべきアクションも明確になる。毎年、オーパスとマルゴーとラトゥールを買って研究しているそうだ。ぜひ、その研究会にお邪魔したい。笑
品質管理に心を砕く
醸造で一番気を付けていることは何か?と松田さんに質問したところ、「洗浄」と即答された。
 ▲ 機材は細かく分解して、洗浄、滅菌する。
▲ 機材は細かく分解して、洗浄、滅菌する。
 ▲
樽もキレイな状態をキープ。番号が大きいほど新しく導入した樽だそう。
▲
樽もキレイな状態をキープ。番号が大きいほど新しく導入した樽だそう。
毎年約60樽購入するが、樽を汚すなと口酸っぱく言っている。樽の洗浄は当たり前。ワインを補填する際、口元は必ず除菌をするし、口周りが赤く染まらないように必ずふき取る。瓶詰めの際の洗浄、滅菌も徹底的に行うため、週初めにCIP洗浄を行い、瓶詰日の朝に熱殺菌を行ってから充填する。 「ワインが触れるところは全て滅菌する。ワインが腐るのが一番怖いから。」と松田さんは言う。
 ▲ 精密濾過機。
▲ 精密濾過機。
 ▲ オゾン燻蒸で空間を洗浄できる洗瓶・充填設備。
▲ オゾン燻蒸で空間を洗浄できる洗瓶・充填設備。
ワインの品質が安定するよう、清澄にも留意する。発酵前に、果汁に含まれる不純物を取り除くために珪藻土を用いた濾過を行ったり、瓶詰め前にはフィルターや遠心分離機を使って微生物や不純物を濾過したり、と品質管理に心を砕いている。
一瞬でも何か悪いと思ったら、お客さんは買ってくれなくなる。俺だったら買わない
と松田さんは気を引き締める。
微生物との関係なしには成り立たないワイン造りにおいて、衛生管理や微生物の管理が品質管理をする上で不可欠という訳だ。

積極的に設備投資してきた高畠ワイナリー。
「醸造を始めた頃、山形にはワイン造りを学ぶところがなくて苦労した」
と松田さんは振り返るが、今は経験に裏打ちされた知識と技術がある。
「松田はああ見えて、意外に緻密な男なんです」
と、高橋社長も松田さんに全幅の信頼を寄せている。
また、営業部長の木村さんが「設備投資は相当行っている会社だと思います。でも、それだけの価値があったと納得するほど、ワインの質はぐんと上がっています」、と自信にあふれた笑顔を見せてくれた。これこそ、設備投資のあるべき姿なのだろう。
夢の途中を楽しむ
2008年に「高畠ワイナリー100年構想」を発表し、『100年かけても世界の銘醸地に並ぶ「プレミアムワイナリー」となる』という高い目標を掲げた。2012年の「ガレージステ・ワイナリー構想」立ち上げからは、その歩みを急ピッチで進めているように思えるが、その歩みはまだ続いていく。


そんな中、2024年に世界3大ワインコンクールの一つであるIWSC(インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション)の白ワイン生産者トロフィーにノミネートされたことは、大きな自信になった。受賞したのは、醸造責任者の松田さんが白ワインの指標に挙げている中の一つである、シャブリの「La Chablisienne(ラ・シャブリジェンヌ)」。受賞こそ逃したが、ラ・シャブリジェンヌと肩を並べて戦えるまでになったのだ。
今年、創業35周年を迎えた高畠ワイナリー。これからの更なる進化が楽しみで仕方ない!


読者の皆さま、高畠ワイナリーは観光ワイナリーとして一般公開しています。施設の中は試飲スペースも含め、色々と楽しめる展示が沢山あるので、ぜひ一度足を運んでみて下さい!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。