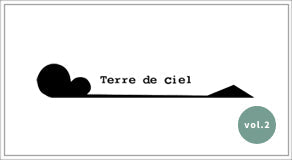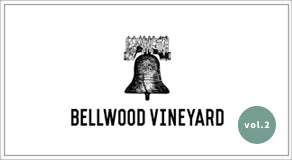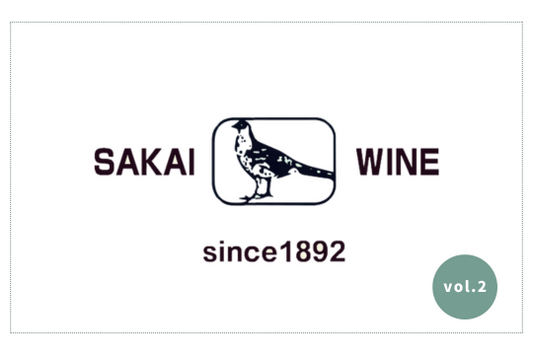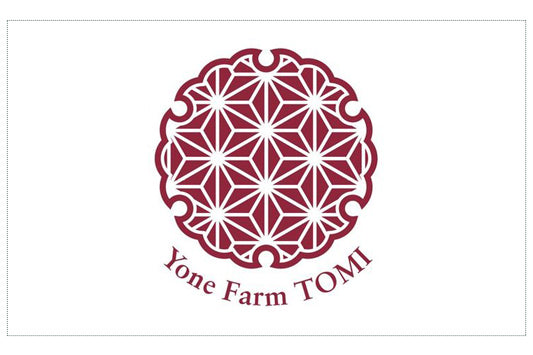日本ワインコラム |アクアテラソル馨光庵(けいこうあん)
なにせ絶妙なのだ。
独立独歩のようで繋がっている。信頼と尊敬の隣に緊張感がある。
2023年9月、東御市鞍掛にオープンしたワイナリー、アクアテラソル馨光庵を舞台にした主人公たちの関係だ。代表を務める平井さんと醸造責任者の中田さんの話を聞くと、いい意味で「人生何が起こるか本当に分からないなぁ」という気になる。
 ▲
ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。
▲
ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。
 ▲
左側が平井さん、右側が中田さん。
▲
左側が平井さん、右側が中田さん。
始まりの前夜
ビジネスパートナーであり、師弟関係でもある平井さんと中田さん。ワイナリーを建てる前までは全く別の人生を歩んでいた。
平井さんの歩み
 ▲
チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。
▲
チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。
平井さんは東京の司法書士事務所を経営するビジネスマンであり、ワインラバーでもあった。ワインへの気持ちが高まり、2018年に事務所を後進にゆずり、52歳で長野県に移住。千曲川ワインアカデミーでワイン造りを学び、信州うえだファームで農業研修を受け、就農する。東京での安定した生活を捨てられたのは、ワイン愛の強さ故かもしれないが、好奇心の強さ、柔軟な考え方、思い切りの良さといったところにも秘密がありそうだ。また、人との出会いを縁に変えるチャーミングな人柄を忘れてはいけない。
農業研修先でのカーヴ・ハタノの波田野氏との出会いが転機となる。「波田野さんの造るワインが本当に美味しくて、衝撃が走った!ワイン造りの師匠ではあるが、自分は波田野さんの大ファンで追っかけ。家のセラーは波田野さんのワインだらけで、垂直で全て揃えている」、と豪語するほど。好きになったら一直線。ツンデレなんて言葉は辞書にないほど、好き光線が出る。この光線を浴びた人は、平井さんを好きにならずにはいられないのだ。
中田さんの歩み
 ▲
中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。
▲
中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。
一方の中田さんも東京出身。祖父の代まで農家を営む家で生まれた。農家になりたいという夢を追いかけ、2012年、ヴィラデスト・ワイナリーへの就職を機に長野県東御市に移住。ワイナリースタッフも、併設のレストランで提供する野菜栽培を担っていたそうだ。そして、当時ヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めていたのが波田野さんだった。「波田野さんも自分も移住組。若造の頃から公私共に本当にお世話になって、心から信頼している先輩」だと言う。
波田野さんが独立後、中田さんがヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めたが、2019年に独立する----野菜農家として。えぇっっ‼ワイナリーじゃないの~!?と思ってしまうが、元々野菜農家になりたかった本人にとっては当然の選択だ。中田さんにとって、玉ねぎもブドウも同じ農作物。ただ、独立後もシャルドネの一枚畑は持ち続け、カーヴ・ハタノで委託醸造していたという。 「ワイン」ではなく、「農業」からスタートしているからこその選択だ。周りと比較せず、夢を持ち続け、臨機応変に動く。どっしりしつつ軽やかなのだ。
それぞれの歩みが重なる~ワイナリーの始動
別々の道を歩んでいた2人を結びつけたのは、波田野さん。ある日、野菜農家として汗を流していた中田さんに天の一言が下り、平井さんと中田さんが急接近するのだ。
(波田野)「ちょっと遊びの話なんだけど、とある人ともう一軒ワイナリーを建てようと思っててさ。お前、醸造長やるだろ?」
(中田)「え?あ…はい!」
これで決まったらしい。「とある人」とはもちろん平井さんのこと。平井さんの熱意をくんだ波田野さんが一役を買ってくれたのだ。「手にしたものは地域のために活かしなさい」と波田野さんから常々言われていたそうだが、野菜農家として独立したはずの中田さんが即決するとは…恐るべし師弟関係!
 ▲
アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。
▲
アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。
思いが詰まったワイナリー建設
 ▲
ワイナリー入口。ワイン樽もしっくり馴染む外観。屋根の勾配や入口付近の陰影も美しい。
▲
ワイナリー入口。ワイン樽もしっくり馴染む外観。屋根の勾配や入口付近の陰影も美しい。
ワイナリーは、東御市鞍掛出場地区の見晴らしのいい場所に立つ。波田野さんと中田さんの知り合いで、地区の顔とされる方から紹介された所だ。周囲には古墳が多数残り、古くから人が住む災害の少ない場所ということが分かる。建物の建設は、波田野さんの長い知り合いの大工店「馨香庵」にお願いすることに。周囲の雰囲気に溶け込むよう、古材をふんだんに使い、新築ながら昔からここに建っていたかのような風貌に仕上がった。
自分達も建設に関わった分、思い入れは強い。ブドウの収穫日が刻一刻と近づく中、ワイナリー建設が遅れ、醸造免許の取得が間に合わないかも…という事態になり、「朝、野菜を収穫して、ブドウの世話をしてから、ヘルメットをかぶってワイナリーの大工仕事もした」と中田さんは振り返る。波田野さんと中田さんは大工作業を趣味にしているそうで、梁を担いだり、土壁を塗ったりするのもお手の物だそう。多才すぎ!
 ▲ ワイナリーの窓から見える景色にも癒される。
▲ ワイナリーの窓から見える景色にも癒される。
 ▲ 立派な梁。これを担いだなんて…
▲ 立派な梁。これを担いだなんて…
絶妙な三角関係で成り立つワイン造り
3人が力を合わせて肉体労働もこなした甲斐もあり、2023年9月、無事にワイナリー「アクアテラソル馨光庵」はオープンする。代表は平井さん、醸造責任者は中田さん、アドバイザーは波田野さんという布陣だ。ワイナリー名の「アクアテラソル」はアクア(水)、テラ(大地)、ソル(太陽)というラテン語を組み合わせたもの。「馨光庵」は大工店へのリスペクトと、ワインの「馨(かおり)」が漂う場所という意味も込められている。
 ▲
アクアテラソル馨光庵のパンフレット。
▲
アクアテラソル馨光庵のパンフレット。
アクアテラソル馨光庵のパンフレット。3者の名前が刻まれる。因みに、パンフレットが置かれている立派なテーブルも波田野さんと中田さんの合作!
「自分のようなオジサンはロマンからワイン造りを始めるけど、若い世代は現実からスタートする」と平井さんが言えば、「自分は製造業としてワイン業界に入っているけど、ロマン派と交じり合うことで相乗効果が生まれる」と中田さん。違う視点があるからこそ広がる世界なのだ。勝手なイメージだが、夢やロマンという潤いを与え、アイディアの源となる平井さんはアクア(水)、安定感や包容力があり、地力を持ってアイディアを開花させる中田さんはテラ(大地)、尊敬や憧れの目で見上げられ、アイディアを成長させる波田野さんがソル(太陽)、という気もする。生物を育てる三大要素がバランスよく配備されているのだ。
ワインの展開方法もユニークだ。平井さんと中田さんは個別に畑を管理し、醸造はアクアテラソル馨光庵で行った上で、平井さんのワインは「アクアテラソル馨光庵」として、中田さんのは「NAKADA WINES」として販売されている。それぞれ、詳しく見ていこう。


平井さんの造るワイン
上田、東御、御代田にある合計約1haの畑には、様々な品種が植わっている。
ロゼの伝道師になる
長野に移住する前に1ヶ月半かけてフランスとイタリアを周遊した平井さん。フランスでは、王道のボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュではなく、ブルターニュ、ロワール、プロヴァンスを周ったそう。そして、プロヴァンスで口にしたロゼの美味しさに開眼!
世界的に大人気のロゼだが、なぜか日本での人気はそこまで高くない。そのため日本でロゼを造っても難しい戦いになるのは分かっていた。が、好き光線が出たら突き進むのが平井さんである。「ロゼの伝道師になる」と決め、移住と同時にシラー、ムールヴェルドル、グルナッシュ、サンソー、カリニャンを植えた。シラーとムールヴェルドルの苗木は買えたが、残りの3品種は出回っていないので、生産者と交渉して枝を分けてもらったそう。プロヴァンスのロゼを目指すのであれば、この5品種を入手することはマストだったのだ。

「Cariño Mio」(写真右)は、プロヴァンスのロゼと同じ美しいサーモンピンク色!尚、ロゼ造りにはそぐわないと判断した房は収穫せず畑に残し、後日赤ワインに仕上げているそう。少量のため一般販売していないようだが、お味が気になる!
日本では、ロゼ造りを目指して黒ブドウ栽培する人は少数派。赤ワイン用に栽培するので、ロゼは赤ワイン醸造の過程でできる副産物的な位置付けのものが多い。一方、平井さんはプロヴァンスのロゼを目指して栽培している。タンニンの成熟よりも酸味や果実味を重視するので、収穫は赤ワインよりも早い。醸造もプロヴァンスのロゼに倣ったダイレクトプレス方式(白ワイン醸造と同様に、黒ブドウを破砕・圧搾したあと、果汁のみを発酵させる方法)。キレイなサーモンピンク色とフレッシュな味わいを持つロゼに仕上がるのだ。
小さいワイナリーだからこそのチャレンジを大事に
白ブドウはシャルドネの他、イタリア系品種のトレッビアーノやヴェルメンティーノ、高温多湿の日本でも減農薬栽培が可能と睨んでプティ・マンサンやアルバリーニョを栽培している。
 ▲
東御にあるアルバリーニョ、シャルドネ、トレッビアーノ、ヴェルメンティーノが育つ畑。標高はこの地域では低めの540mだが、酸落ちしにくい品種を植えているので、酸持ちが良い。除草剤不使用、殺虫剤も殆ど使わない。
▲
東御にあるアルバリーニョ、シャルドネ、トレッビアーノ、ヴェルメンティーノが育つ畑。標高はこの地域では低めの540mだが、酸落ちしにくい品種を植えているので、酸持ちが良い。除草剤不使用、殺虫剤も殆ど使わない。
 ▲ トレッビアーノは非常に樹勢が強く、房も大きい。
▲ トレッビアーノは非常に樹勢が強く、房も大きい。
トレッビアーノは苗木を買えたが、苗木のなかったヴェルメンティーノは個人輸入し、1年間の検疫を経て栽培に挑戦している。近辺で栽培している人はいないので環境に合うのか未知数だが、攻めの姿勢を忘れずにワイン造りに向き合いたいという気持ちから選んだ品種だ。プティ・マンサンとアルバリーニョも含め、来年以降初収穫とのこと。楽しみだ。
 ▲
シャルドネとトレッビアーノはブレンドして白ワインとして展開中。晩熟のトレッビアーノに合わせてシャルドネを遅摘みし、シャルドネの完熟した果実味にトレッビアーノの酸味が加わった爽やかな一本に仕上がっている。
▲
シャルドネとトレッビアーノはブレンドして白ワインとして展開中。晩熟のトレッビアーノに合わせてシャルドネを遅摘みし、シャルドネの完熟した果実味にトレッビアーノの酸味が加わった爽やかな一本に仕上がっている。
 ▲ シードルは、りんご3種と洋ナシをブレンドしたものに、ゲヴュルツトラミネールの皮を浸漬して造っている。酵母を拡大培養させた上で瓶内二次発酵しているので、酵母の働きが良く泡立ちもキレイに。昨年に引き続き好評とのこと!要チェックだ!
▲ シードルは、りんご3種と洋ナシをブレンドしたものに、ゲヴュルツトラミネールの皮を浸漬して造っている。酵母を拡大培養させた上で瓶内二次発酵しているので、酵母の働きが良く泡立ちもキレイに。昨年に引き続き好評とのこと!要チェックだ!
自己満足に終わりたくない
平井さんの醸造の師匠は中田さん。波田野さんの一番弟子でもあり、信頼は厚い。
醸造1年目は、プロヴァンスのロゼを片手に「こんな感じのサーモンピンクのロゼを造ってよ!いい香りの美味しいやつ!」と中田さんにお願いしたそう。さすがロマン派。無邪気なお願いだ(笑)。しかし騙されてはいけない。会話のトーンの軽さとは裏腹に、平井さんの覚悟は重たいのだ。


「一番怖いのは、我流でとんでもないものを作って、これでいいと納得すること。だから5年間は中田の下で徹底的に基礎を習得すると決めた。だから、一切口答えしない。」
と平井さんは言う。司法書士事務所の経営までやっていた人が、親子ほど年齢差のある人に対して一切口答えしないというのは、なかなかできない。ぐっと堪えることも多いだろう。
「やっぱりワインが好きだから。それに中田はすごい!論理的で、頭の中が整理されている。自分もワインラバーだから感覚的に理解できるところもあるが、醸造は奥深い。作業タイミングや機械のオペレーションなど、難しいことも多い。今年は醸造3年目。あと3回しか中田に教えてもらえない。1年目は細かく教えてくれたが、2年目になると口出しが減った。こっちから聞かないと引き出せなくなってきている。」
という。フラットな関係だから可能な修行期間なのだろう。
真面目な口調になったと思ったら、「親離れの時期が近づいてきて、ドキドキしている」なんて可愛らしい言葉も。こういうところがチャーミングなのだ。
中田さんが造るワイン
まず理解しておく必要があるのが、中田さんは「ワインも造っている野菜農家」であるという点だ。「なかだ農醸」という屋号で、①野菜栽培、②ワイン用ブドウ栽培、③トレリス施工の3本柱で活動している。本職は野菜農家で(①)、12-3月の閑散期には、日本全国を周ってワイン用ブドウのトレリス(ブドウの仕立て)デザイン、設計、施工に加え、ブドウ栽培の指導なども行う(③)。そして、なかだ農醸で育てたワイン用ブドウ(②)は、アクアテラソル馨光庵に委託し、アクアテラソル馨光庵の醸造責任者として自ら醸造の上、なかだ農醸に返却。ワインはNAKADA WINESとして販売されている(や、ややこしい…笑)。因みにアクアテラソル馨光庵の醸造責任者としては、NAKADA WINES以外にも7社の委託醸造を手掛けているので、フル稼働だ。
 ▲
なかだ農醸の野菜セットも食べてみたい!
▲
なかだ農醸の野菜セットも食べてみたい!
色んなキャップを被る中田さんの活動範囲は広い。好奇心の塊のような人である。そして何より凄いのが、興味のあることは徹底的に調べ、机上の空論にはせず、自ら実証しているところだ。詳しくみてみよう。
ブドウの香りを犠牲にしないためのノン・ボルドー栽培
高温多湿な日本でブドウ栽培をする場合、病気対策は欠かせない。有機栽培でも用いられているボルドー液はカビ対策に欠かせない薬の一つだが、中田さんは用いない。パッションフルーツやグレープフルーツといった特徴香を放つチオール成分は、ボルドー液に含まれる銅に触れると香りが消えてしまうのが理由だ。中田さんのワインは、ブドウ品種由来の香りを大事にし、醸造由来の香りでお化粧することは殆どない。そのため、ブドウの香りを削ぐような行動を極力避けているのだ。


チオール成分は、ソーヴィニヨン・ブランに多く含まれるが、シャルドネにも含まれている。「Chardonnay Block1」は、ステンレスタンクを使いマロラクティック発酵も行わない。樽や乳酸といった醸造由来の香りを付けず、ブドウそのものの香りを大事にしている一本で、ボルドー液を使用しないからこそ、チオール系の香りも残る仕上がりに。
興味があった自根栽培
シャルドネの畑は自根だそうだ(驚愕)!
通常、ワイン用ブドウはアメリカ原産のブドウ樹を台木とし、シャルドネといったヴィニフェラ系の樹を接ぎ木してワイン用ブドウの苗木とする。ヴィニフェラ系のブドウ根に寄生し枯死させるフィロキセラという害虫対策として、世界的にも一般的な手法だ。中田さんは、接ぎ木されていなかった昔のワインの味わいに興味を持ち、「独立したらやってみたかった」と言う。フィロキセラを持ち込まないように誰の目にも触れない場所に畑を持ち、3~4年間外部との接触を一切絶って畑を立ち上げたそう。飛翔型のフィロキセラもいるので、今後も安泰とは言い切れないが、今のところ問題なく育っている。
 ▲
畑でブドウを見ながら話しをする中田さんは、本当に楽しそう。
▲
畑でブドウを見ながら話しをする中田さんは、本当に楽しそう。
荒唐無稽な話にも聞こえるが、決して中田さんは向こう見ずな人ではない。東御を見渡せば、樽の効いたボディーのしっかりしたシャルドネワインが沢山存在する。同じようなものを造っても埋もれるだけ。であれば、自根&ノン・ボルドー栽培のシャルドネで、樽なしのフレッシュな果実味を楽しむスタイルで勝負しようと考えたのだ。自根栽培にはリスクを伴うが、管理可能な範囲。ビジネスポテンシャルもあると判断した。緻密な検証を経た上での大胆な決断なのだ。
定説に惑わされないブドウ栽培
中田さんの畑では、他の事業者とは少し異なる景色が広がる。垣根仕立てのブドウ栽培では、ブドウの新梢が伸びてくると「誘引」と呼ばれる作業がある。通常、垣根を作るワイヤーは2重で張られ、伸びた新梢はワイヤーの間に収め、テープで固定するという作業を行うが、中田さんは違う。ワイヤーは1重のシングルワイヤーで、新梢が伸びてきたら反対側に枝を持っていくだけ。
 ▲
ポールの間に張られているワイヤーが1本なのがよく分かる。
▲
ポールの間に張られているワイヤーが1本なのがよく分かる。
「独立したら絶対シングルワイヤーにしようとアイディアを温めていた。ダブルワイヤーの場合、ワイヤーの間に新梢を収めようとして枝を折ってしまったり、クリップで止めるという作業も発生したり、手間暇がかかる。シングルワイヤーであれば音楽聞きながら気分よく作業できる。」
作業効率の良さだけではない。 「目指しているのはアロマティックな白ワイン。白ブドウは果実への強い直射日光は不要なので、通説の南北畝にはせず、東西畝にして果実の香りを残すようにしている。とは言え、東西畝は南北畝に比べて日当たりは劣るので、光合成効率を上げたい。シングルワイヤーにすることで垣根の厚みは薄くなり影も減るし、葉一枚毎の光合成率は上がり、ブドウの糖度も上がる。」という訳だ。
 ▲
ワイヤーは、トマトやキュウリを誘引する際に使われているもの。また、果実部分の雨除けは野菜栽培で防寒用に使われるトンネルの骨組みで、どれもホームセンターで購入可能だという。野菜を栽培しているからこそ生まれるアイディアだ。
▲
ワイヤーは、トマトやキュウリを誘引する際に使われているもの。また、果実部分の雨除けは野菜栽培で防寒用に使われるトンネルの骨組みで、どれもホームセンターで購入可能だという。野菜を栽培しているからこそ生まれるアイディアだ。
出来上がりのワインを想像して造った畑
NAKADA WINESの一番人気「note」は、5品種のブドウを一つのタンクで混醸して仕上げるワインだ。2023年ヴィンテージは、ゲヴュルツトラミネール、リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワール、ジーガレーベ(ゲヴュルツトラミネールを片親に持つ交配種)のブレンド。尚、2024年はリースリングを単独で仕込んだので、Noteにはヴィダル・ブランが代わりに加わるそうだ。因みに、中田さんが育てる黒ブドウ品種はピノ・ノワールのみ。ブルゴーニュやシャンパーニュ、アルザスという冷涼な地域のワインが好きというのもあるが、畑の気候や環境に合う品種を育ててワインに仕上げるというドメーヌ的な考えに沿った結果だ。ゆくゆくは、ピノ・ノワール単体の赤ワインもリリースされる予定とのこと。楽しみに待ちたい。
4枚ある畑のうち、1枚は最初からnoteの味わいをイメ―ジし、noteのブレンド比率を考えながら様々な品種を植えていったそう。収穫年の気候によって品種やブレンド比率は異なるが、当初の想定に近い味わいに仕上がって満足しているというのだから、その想像力に脱帽する。
 ▲
遊びの要素が強いとして、「note」のラベルは斜体にしているそう!「note」(写真右)はライチや白桃といったフルーティで甘さを感じる華やかな香りが広がるが、味わいはドライ。一方、Noteの香りのイメージを味わいに反映させて造った「note Cuvée S」(写真右から2番目)は、やや甘口~甘口に仕上げたもの。ピノ・グリ(写真左)は 2022年までnoteのブレンドに入っていたが、2023年に単独で仕込まれた。
▲
遊びの要素が強いとして、「note」のラベルは斜体にしているそう!「note」(写真右)はライチや白桃といったフルーティで甘さを感じる華やかな香りが広がるが、味わいはドライ。一方、Noteの香りのイメージを味わいに反映させて造った「note Cuvée S」(写真右から2番目)は、やや甘口~甘口に仕上げたもの。ピノ・グリ(写真左)は 2022年までnoteのブレンドに入っていたが、2023年に単独で仕込まれた。
通説に囚われない、伸びやかな発想にハッとさせられるが、その発想は一夜にして生まれるものではない。深く考えながら基礎をしっかり身に付けたからこそ生まれるのだろう。しっかりした土台がないと跳ねることはできないのだ。
完成形が見えない方が面白い
それぞれ異なるスタイルのワインを造る平井さんと中田さん。性格も物事へのアプローチも異なるからこそ、2人の間に広がるのは無限に伸びる直線だ。そこに波田野さんという点が加わることで図形となり、様々な形の三角形に変化する。
もし、タイムマシーンがあったとして同じことを繰り返すか聞いてみた。平井さんは言う。

やらないかもしれないな~(笑)。あ、でも後悔は全然してないし、楽しくやってますよ!ただ、体力的に過酷な仕事だから、ベストなコンディションでやりたいと思うだけ。59歳という年齢を考えると、今のペースを維持できるのは後10年くらいじゃないかな…先を見据えて、少しずつ中田にバトンタッチしていけたらな、とも思っている。
自分の選択に全く後悔はしていないが、現実も見据えての嘘偽りのない言葉だと思う。
そんな平井さんに対し、
自分はウイスキーの世界に行くと思う!発酵の香りのワインに対してウイスキーは蒸留の香りとのお付き合い。前職で、嬉々として蒸留酒造りのための残業をしていたくらい、精油や香水のような香り高い世界は魅力的

と中田さんが言えば、
「そうそうウイスキーはいいよね~。僕もワインよりウイスキーの方が好きかもしれない。ここも将来蒸留所になるかもしれないね」と、びっくり発言の平井さん。
ただ者ではないお二人。話を聞けば聞くほど、今が最終形ではなく、常に進化していくことが予見される。どんどん新しいワインがでてくるに違いない。もしかしたらワイン以外の蒸留酒もラインナップされるかも?

平井さん、中田さん、色々とお話をお聞かせ下さり、ありがとうございました!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。