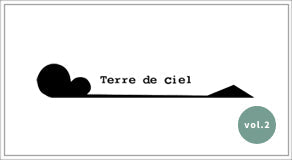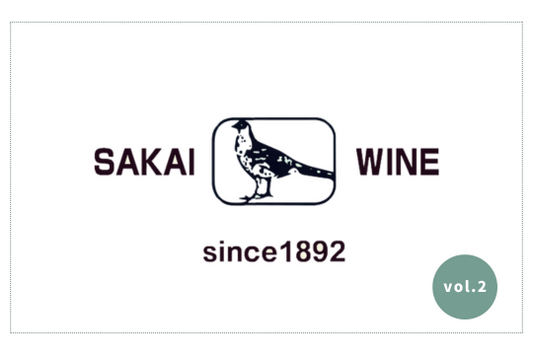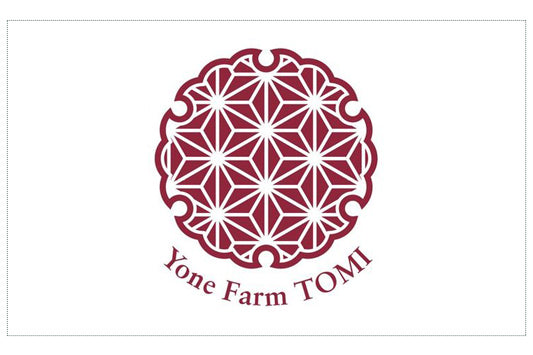日本ワインコラム | 山形・ベルウッド ヴィンヤード ワイナリー vol.2
山形県上山市の久保手地区にあるベルウッド・ヴィンヤード。前回お邪魔したのは、ちょうどワイナリーが完成した年だったので、約5年前になる。あの時と変わらぬ、ぱっと目を引くスタイリッシュな鈴木さん。そして、木材とテーマカラーの黒を掛け合わせ造られたワイナリーの洗練された雰囲気も変わらない。


大きく異なるのは外の景色。前回は初冬に訪問したが、今回は猛暑真っ只中。一歩外に出れば汗ぐっしょりで、人間は日差しの強さに負けそうになるが、その分、逞しく成長しているブドウの生命力の強さを感じる。5年という年月を経て、細かったブドウの樹も大きく成長し、青々とした葉っぱを茂らせ、元気一杯だ。鈴木さんもちょっとのことでは動じない、ある種余裕さえ感じる佇まいだ。いい意味での脱力感はありつつ、スパっと行動に移す軽やかさがある。鈴木さんの造るワインに感じる洒脱さは、やはり鈴木さんの人柄が滲み出ているのだろう。
好き→アンテナが伸びる→センスが磨かれる
鈴木さんの周りは、どこを切り取っても洒落ている。ご本人の風貌はもちろんのこと、持ち物、ワイナリー内のディスプレイ、ワインのラベル、そしてその味わいさえも。近寄りがたさのある尖ったオシャレではなく、居心地のよさを感じるオシャレだ。
 ▲
ワイナリー内には、鈴木さんの審美眼に選ばれたアウトドアグッズが飾れている。
▲
ワイナリー内には、鈴木さんの審美眼に選ばれたアウトドアグッズが飾れている。
前回訪問時に、
「独立してからは、何を置くにしても、周囲には自分の好きなものだけを置くように、それだけは曲げたくないと思っています。ラベルにしても何にしても、ひとつひとつを、自分を表現する一部として考えているのです。」
と答えられていたように、やはりご自身の「好き」が集まった空間には、ジャンルが違っても統一感があるし、どれを取っても「鈴木さん」を感じるのだ。
きっと、ワインも「好き」を大事にして始められたのかと思いきや、意外な歴史を教えてくれた。

「山形県朝日町出身で、高校卒業後、仙台の専門学校に進学したのですが、留年して…卒業後もなかなか進路が決まらなくて。そしたら、親が知らない間に朝日町ワインに履歴書を送っていて、「ここに入れ」と言われるままに就職したんです(苦笑)。」
なんともビックリだ。若かりし頃の鈴木さんは、「やりたいことがわからない」というモヤモヤした不安みたいなものがあったのだろうか…それにしても、ご両親のアシストがなければワインの道に進んでいなかった訳なので、感謝してもしきれない。きっと、鈴木さんの好みをある程度理解した上で、半ば強引に道を作ってくれたのではないだろうか。
 ▲
本当、ワインの道に進んでくれた良かったです~!!
▲
本当、ワインの道に進んでくれた良かったです~!!
鈴木さんのぶっちゃけはここで止まらない。「折角朝日町ワインに就職したんですが、余暇の遊びが楽しくて、そっちで生計を立てようかと思ったこともある」、と言うではないか‼破天荒ぶりに思考停止になりそうになるが、見逃してはいけないのが、趣味を仕事にしようと思う程上達したという点だ。鈴木さんは、好きになるとアンテナがぐぃ~んと人一倍伸びるのだ。有難いことに、ワインの道は残った。「趣味にお金を使い果たした(笑)」ということもあるそうだが、それだけではない。スタートがどうであれ、毎日ワイン造りに向き合う内に、「好き」が蓄積されたのだろう。そして、アンテナが伸びた。その結果、ご自身が製造に携わったワインが、コンクールで金賞を受賞するまでセンスが磨かれたのだ。そうなると、自分のセンスを追求して試したくなるものだ。19年間働いた朝日町ワインを卒業し、2017年に自分で栽培から醸造まで手掛けるスタイルに移行する。こうして、誕生したのがベルウッド・ヴィンヤードなのだ。
自分を枯渇させないから可能な挑戦
鈴木さんの牧歌的な口調も影響しているかもしれないが、鈴木さんからは苦しさが感じられない。もちろん、夏場は朝4時台に起床、5時台には畑に出て、日が暮れる19時30分頃まで畑仕事、その後事務仕事が21時頃まで続くというのだから、フル回転だ。「手が回りきらない」と呟かれるが、疲弊感はないし、何となく楽しそうなのだ。なぜだろう?
10から10+αの結果を引き出す
ワイナリーのすぐ隣に1ha弱の自社畑が広がる。周囲は平らな田畑が広がるが、畑は独立峰のような形で隆起した小高い丘になっている。もともと耕作放棄地だった場所を、2017年の独立と同時に垣根仕立てで複数の欧州品種を植樹した場所だ。もう一つの畑は、ワイナリーから500mほど離れた場所にある10a弱の畑。後継者のいないデラウェアの畑を引き継ぎ、棚仕立てで有核栽培している。無理をすれば畑を広げられるかもしれないが、鈴木さん、今ある畑をきっちり管理することに重点を置いている。
 ▲
ワイナリー横の垣根仕立ての畑。中央にある柿の木が木陰として活躍しているそう。ここにアウトドアグッズを持ってきてもいいな~、と鈴木さんの妄想は広がっていた。
▲
ワイナリー横の垣根仕立ての畑。中央にある柿の木が木陰として活躍しているそう。ここにアウトドアグッズを持ってきてもいいな~、と鈴木さんの妄想は広がっていた。
 ▲
ワイナリーから車で数分の場所にある棚仕立てのデラウェアの畑。
▲
ワイナリーから車で数分の場所にある棚仕立てのデラウェアの畑。
例えば、下草。今年は雨が少なく草刈りの頻度は少なく済んでいるとのことだったが、下草もキレイに刈られ、湿気が溜まらないようになっている。逆に、今年は日照りが続いているとのことで、水分ストレスがかかり過ぎると判断したら水やりをこまめに行えるよう、水道も完備。畑の西側は竹藪が隣接していたそうで、陽当たりに影響が出たり、コウモリガを始めとする害虫の被害が出やすくなっていたりしたので、伐採した上で、ブドウ畑の周りも含めて草刈りするなどの対応も怠らない。
 ▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。メルロの横に広がる竹藪を伐採した様子
▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。メルロの横に広がる竹藪を伐採した様子
また、ブドウの細やかな観察も怠らない。湿度の多い日本でのブドウ栽培はカビ菌との戦いでもある。果実の周りに葉っぱが残り過ぎていると通気性が悪化することから、タイミングを見計らった徐葉は欠かせない。また、樹勢が強いブドウは新梢の成長が早い。新梢が伸び放題になると通気性が悪くなり、病気に繋がるし、枝の成長に栄養が取られ過ぎると、果実の成熟に影響が及ぼされるので、適切なタイミングでの新梢のトリミングが必要になる。
北向き斜面の畑に植わるピノ・グリとピノ・ノワールは、ちょうど2回目のトリミングが終わったタイミングだった。果実が凝縮するよう、摘房作業も行う。メルロは房にある両肩を落とし、日光が適度に当たるようにしたところだったし、樹勢の強いデラウェアについては、一枝に4-5房付いている果実を2房程度まで落とす房落としの作業を終えていた。
 ▲
こうやって一房一房成長を見守っているのだ。
▲
こうやって一房一房成長を見守っているのだ。
鈴木さんの畑には無駄なものがなく美しい。守備範囲を広げ過ぎないことで目が届く範囲が広がるし、作業を一つ一つ丁寧に行える。だから、ブドウの質が上がるのだろう。ブドウの状態を細かく見ているからこそ、10の場所から10+αの結果を得られるのだ。
効率化を図り、自分を楽にする
近隣のワイナリーでもよく話題に上った晩腐病は、ベルウッド・ヴィンヤードでも頭の痛い問題だ。高温多湿の環境は、原因のカビ菌が繁殖しやすい。ブドウが熟す頃に急速に病気が広がり、果実が腐敗してしまう上、病原菌は越冬し、翌年に二次感染も引き起こす厄介な存在だ。「毎年、菌が蓄積してしまうんですよね…」、と鈴木さんは言う。対策として、フルーツガードを導入し雨除けを行っている他、最小限の消毒作業も行う。
 ▲
ブドウの上にフルーツガードがかけられているのが分かるだろう。果実の周りも除葉されており、湿度が溜まりにくく、房に日光が当たるようになっている。
▲
ブドウの上にフルーツガードがかけられているのが分かるだろう。果実の周りも除葉されており、湿度が溜まりにくく、房に日光が当たるようになっている。
「実は、減農薬するぞ!と掲げて最小限の薬にしている訳ではないんです。薬の散布は一本一本手作業で行っているのですが、この作業が辛すぎて…ずっとやっていると自分の気持ちが落ちてしまうからやりたくない。とは言え、回数を減らしすぎると、今後はブドウが病気になってしまう。」
 ▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。畝間は乗用の草刈り機を使っているが、株の間は広い敷地を歩きながら刈払機で丁寧に対応されている…骨の折れる作業でもある
▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。畝間は乗用の草刈り機を使っているが、株の間は広い敷地を歩きながら刈払機で丁寧に対応されている…骨の折れる作業でもある
こう胸の内を明かしてくれた。やらないといけないことでも、嫌々やるとパフォーマンスは落ちるし、長続きしない。そうであれば、嫌いな作業を楽しめる方法を見つけたり、効率化を図ったりするのが鈴木さんだ。農薬散布は、古いSSを入手したそうで、今後は一本一本の作業が不要になると喜んでいた。
この他にも、夏場は頻繁に行う必要がある草刈りも大変なので、乗用タイプで株元まで対応できる草刈り機に変える予定とのこと。ツライと感じる作業は、躊躇せず手放し機械化する。日本では、「苦労=美徳」と考える傾向がある。確かに苦労した先に見える景色はあるが、疲弊して自分が潰れては意味がない。鈴木さんはこのバランスの取り方が上手だから、軽やかなのだろう。
余裕があるからチャレンジできる
5年前に訪問した際は、垣根栽培の畑の南向き斜面にメルロ、カベルネ、北向き斜面にピノ・ノワール、ピピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランが植わっていた。どれも植樹から3年以内の若木だったが、ちょうどピノ・ノワール、ピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランが初収穫されたタイミングだった。今回訪問してみると、どのブドウ樹も立派に成長していて、嬉しくなる。
加えて、畑には新顔も!2024年に畑の東向き斜面に植えられたプティ・マンサンとアルバリーニョが元気よく枝を伸ばしていた。この品種を選んだ理由を聞いた。


「白系品種がソーヴィニヨン・ブランのみだったので、幅を増やしたかったんです。じゃあ、シャルドネか?とも思ったのですが、昨今の温暖化の影響でシャルドネだと暑すぎて酸落ちしてしまう。耐暑性があって、高温多湿でも耐病性がある白品種は何かと考えていくと、プティ・マンサンとアルバリーニョに行きついた。この2品種であれば、樽熟成の可能性もあると見込みました。」
 ▲
畑の土壌は粘土質を基調に、風化した白い礫が混ざっている。
▲
畑の土壌は粘土質を基調に、風化した白い礫が混ざっている。
上山市は蔵王連峰の裾野に広がる周囲を山で囲まれた盆地にあり、昼夜の寒暖差が大きく、比較的降雨量も少なく、水はけのよい土壌で、ワイン用ブドウの栽培環境として非常に恵まれた場所だ。しかし、最初にブドウを植えて8年が経つ中で、気候の急激な変化を感じ、対策の必要性を感じているのだろう。新植作業は思い立ったらすぐできるというものではない。植える場所の確保・整備、苗木の手配等、時間も手間もかかる作業だ。緊急ではないが、先を見通した重要度の高い課題に取り組むには、日々の業務を終えた上での余裕がないと始まらない。ヘルパーさんがいるにしても、中心的な作業は鈴木さん一人という環境下だ。無意識かもしれないが、鈴木さんは「余力」をきちんと確保することで、アイディアの実装をスムーズに行っているように思える。
自社畑に限らない
鈴木さんは、独立した時から自社ブドウだけではなく、買いブドウも原料として用いることを視野に入れていた。因みに、昨年仕込んだ24トンの内、5-6トンが自社ブドウということなので、買いブドウが大半を占めている。ベルウッド・ヴィンヤードがある上山市久保手地区は、もともとデラウェアの産地で、ブドウ栽培の歴史が長い。また、大手のワイナリーに提供するためにワイン用ブドウを栽培してきた農家も多く、技術力も高い。高品質なワイン用ブドウが手に入る環境にあるのだ。
 ▲
ワイナリー内にディスプレイされている、コレクション・スーペリオール(厳選したブドウで造る上級シリーズ)とキュヴェ・デ・ザミ(知人の栽培家による厳選したブドウで造るハイエンドシリーズ)は買いブドウで仕上げられたもの。
▲
ワイナリー内にディスプレイされている、コレクション・スーペリオール(厳選したブドウで造る上級シリーズ)とキュヴェ・デ・ザミ(知人の栽培家による厳選したブドウで造るハイエンドシリーズ)は買いブドウで仕上げられたもの。
更に、ちょうど鈴木さんが独立する前に、上山市で「ワインの郷プロジェクト」が発足したのもタイミングが良かった。ブドウ栽培、ワイン醸造、販売の各方面からワイン産業を推し進め、地域を活性化しようとする機運が高まったのだ。ベルウッド・ヴィンヤードもこのプロジェクトの支援を受ける形で船出したが、これを機にワイン用ブドウを栽培する人も増えたという。「買おうと思ったらもっと買える」、と鈴木さんは言うように、原料は潤沢にあるのだ。とは言え、「買える環境=いつでも買える」という訳ではない。信頼関係がないと始まらない。鈴木さんの発言は、近隣農家と良好な関係を築いていることの表れなのだ。
 ▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。写真は去年の様子だが、まさに取材日は同じ蕎麦まきの日だった。
▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。写真は去年の様子だが、まさに取材日は同じ蕎麦まきの日だった。
実は、取材をしている最中、近隣農家の皆さんが鈴木さんのために、ワイナリー横の空白地帯(鈴木さんの土地)に蕎麦の種を撒いてくれていた。彼らはベルウッド・ヴィンヤードにブドウを卸している契約農家でもあるとのこと。この気取らないフランクな関係は、鈴木さんの実直なお人柄があってこそ築けるのだろう。楽しそうにしている鈴木さんには声をかけやすいし、一緒に何かしたくなるのだ。
遊び心と緻密さがおりまざった醸造所
必要なものが必要なだけ揃っているワイナリーは、整然としていて美しい。が、ところどころ遊び心が散りばめられていて、「抜け感」のある、鈴木さんらしい醸造スペースになっている。
 ▲
パレットまでも黒で統一&ワイナリーのロゴ入り!美は細部に宿るのだ。
▲
パレットまでも黒で統一&ワイナリーのロゴ入り!美は細部に宿るのだ。
ブドウはボランティアさんと一緒に手収穫する。収穫時にしっかり選果を行った上で、醸造所内の冷蔵庫で一旦保管し、しっかりと冷やすことで酸化や腐敗を防止する。その後、除梗・破砕機にかけられ、白ワインの場合は果汁と果皮を半日接触させた上で、プレス機に。発酵は、赤ワインやオレンジワインの場合は、容量に合わせて8種類の開放型のタンクを使い分ける。白ワインは、容量の異なる3種類の温度調整が可能なステンレスタンクを用いる。なお、ステンレスタンクは落し蓋形式で、酸化が抑えられる仕組みだ。
 ▲
プレス機と除梗破砕機。
▲
プレス機と除梗破砕機。
 ▲
落し蓋形式のステンレスタンク。
▲
落し蓋形式のステンレスタンク。
この醸造スペースで、ふと目に入ったのがバスケット・プレス。シャンパーニュ地方などでよく用いられる代物だ。こちらも使っているのかと思いきや、「前掛けを掛けるのに使っている」というびっくり発言が(笑)。高級な前掛け置きである。その他にも、いつのまにか壊れていたという、正しく時間表示されないオシャレな掛け時計が飾られていたり、壁の一部にワインのエチケットがランダムに張られていたり、楽しさがある空間になっている。
 ▲
ワインのエチケットが無造作に飾られている。
▲
ワインのエチケットが無造作に飾られている。
 ▲
少し分り難いが、写真右奥の鈴木さんの後ろにあるのがバスケット・プレス。またの名を、高級前掛け置きという。
▲
少し分り難いが、写真右奥の鈴木さんの後ろにあるのがバスケット・プレス。またの名を、高級前掛け置きという。
大らかさを残しつつ緻密なのが鈴木さんだ。醸造所の一角には、発酵前後でワインの亜硫酸濃度やpH、アルコール度数を図ることができる分析検査機も確保し、ワインの品質管理には心を砕いている。
 ▲
実験室さながらの様子。細かく品質管理を行っている。
▲
実験室さながらの様子。細かく品質管理を行っている。
熟成に注力する
ゆくゆくは拡充したい
醸造所には、フレンチオークとアメリカンオークの樽が並ぶ熟成スペースも確保されており、一定の温度・湿度で管理されている。スペースを有効活用し、赤ワインやオレンジワインの発酵時にタンクを持ってきて、発酵温度が上がり過ぎないように調整することもあるそう。
長期熟成させたい自社畑シリーズのドメーヌ・クロッシュは、1-2年程かけて樽熟成する。2024年ヴィンテージからは、カベルネ・ソーヴィニヨンなど2年熟成するスタイルのものが増えてきたため、少し手狭になってきたと感じているそう。「長期熟成タイプのワインを増やしていきたい」、と鈴木さんは意気込みを語ってくれた。ゆくゆくは、上段でご紹介した、蕎麦を撒いていたワイナリー横のスペースを活用することも検討しているとのこと。蕎麦畑が醸造所に変貌を遂げる日も近いかもしれない。
 ▲
長期熟成タイプのワインが増えると共に、樽も今後増えていくのだろう。
▲
長期熟成タイプのワインが増えると共に、樽も今後増えていくのだろう。
ダム熟成を始める
2024年から山形県と連携し、前川ダム(上山市にある治水ダム)の管理用トンネルを活用したワイン熟成の取組みをスタートしたそう。トンネルの中は年間を通じて10℃程度に保たれ、外部からの光も遮断されるので、ワインの長期熟成に最適だ。また、空調設備も不要なので、電力を使う必要もない。脱炭素のエコな取組みなのだ!山形のワイナリーでダム熟成を行っているのは、ベルウッド・ヴィンヤードのみとのこと。
 ▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。昨年に引き続き、今年もワインが無事にダムに運び込まれた。
▲
ベルウッド・ヴィンヤードのインスタより。昨年に引き続き、今年もワインが無事にダムに運び込まれた。
長期熟成させたい自社畑シリーズのドメーヌ・クロッシュと、知人の栽培家による厳選したブドウで造るハイエンドシリーズのキュヴェ・デ・ザミがダム貯蔵入りしている。2024年に搬入したものは、来年春以降にリリースされるようなので、首を長~くして待ちたい!
------
鈴木さんと話をしていると、ゆったりした気分になる。馴染みの喫茶店のマスターやバーテンダーと話しているような感覚に近い。近すぎず遠すぎない、ちょうどいい距離感。くすっと笑える話と、押し付けないちょっとした気遣いに心が温かくなる。前回の訪問で、鈴木さんの言っていた言葉が思い出される。
「ワインを飲んでくれる方々との繋がりも持てたらと。自分のワインをどんなふうに飲んでくれているのか、直接感じたいと思いました。」
人との対話を大事にされているのがよく分かる言葉だ。この思いは、ワインのラベルでも表現されている。ラベルそのものが切手になっていたり、ラベルに切手や押印が付されていたり。ワインを媒体に、鈴木さんからお便りが届くというスタイルなのだ。2024年に直接お客様と繋がる、サポーター会員制度をスタートさせたのも、直接繋がりたいという思いからなのだろう。
 ▲
ブドウの味わいを素直に感じられる発泡ワインのシリーズのコレクション・ヴァン・ペティアンは、ラベルそのものが切手。下段にワイナリー、中段に鈴木さんとブドウ、上段に上山市久保手地区のシンボル的な鷹取山が描かれている。
▲
ブドウの味わいを素直に感じられる発泡ワインのシリーズのコレクション・ヴァン・ペティアンは、ラベルそのものが切手。下段にワイナリー、中段に鈴木さんとブドウ、上段に上山市久保手地区のシンボル的な鷹取山が描かれている。
 ▲
コレクション・スーペリオールは、ラベル右上に切手と押印があるスタイル。
▲
コレクション・スーペリオールは、ラベル右上に切手と押印があるスタイル。
独立した時の気持ちがそのまま鮮度よく残っている鈴木さん。今年はどんなお便りが鈴木さんから届くのだろう…ワクワクして待ちたいと思う。
 ▲
鈴木さん、ぶっちゃけ話も含め、色々とお話をお聞かせ下さり、ありがとうございました!
▲
鈴木さん、ぶっちゃけ話も含め、色々とお話をお聞かせ下さり、ありがとうございました!
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。