日本ワインコラム
THE CELLAR ワイン特集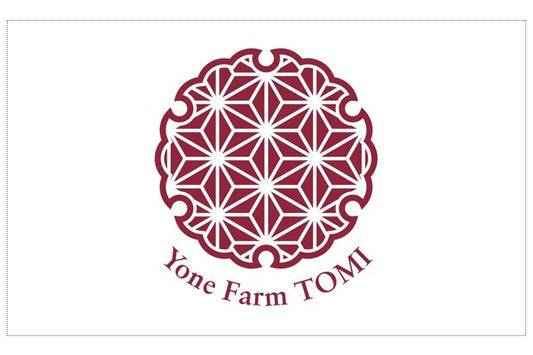
長野・ヨネファーム東御
日本ワインコラム |ヨネファーム東御 インタビューのお相手、米倉さんとは、地元で大人気のやきそば・ワンタンのお店「開花亭」で待ち合わせ。到着時には既に長い行列だったが、食い意地の張った我々にとって行列なんて怖くない。米倉さんへのご挨拶も早々に、熱々の焼きそばとワンタンを汗タラタラで食すところからのスタートとなった。こんな素敵なお店での待ち合わせを提案して下さったくらいだし、さぞかし何度も来店しているかと思いきや、2回目という米倉さん。普段はきっと、畑仕事が忙しくて、のんびりランチとはいかないのだろう… ▲ くしゃっとした目元が印象的。優しい笑顔の米倉さん。 2018年に東御市でワイン用ブドウ栽培を開始した米倉さんは、3ヶ所に跨る約5haの畑で多種多様なブドウ品種を一人で栽培するスーパーマンだ。口数は少なめ。反射神経的に言葉を発するのではなく、自分の中で納得したことだけを話すからだろう。だからこそ、発せられる言葉には強い意志を感じる。そんな米倉さんの現在とこれからについて色々とお話を伺った。 広がる畑の管理 米倉さんがワイン業界に足を踏み入れたのは50歳を目前にした頃。その前から15年間毎月ワイン会を開催し、友人達と世界各地のワインを楽しんだり、ブルゴーニュ、ローヌ、カリフォルニアといった銘醸地を訪問し、栽培・醸造を体験したりと、趣味以上仕事未満の熱量でワインと関わってきたが、とうとう仕事にする決意を固め、25年勤務した通信系会社を退職。2015年に東京、神楽坂でワインバー&ショップをオープンしたが、ワインとの関係が深まる中でワイン造りへの興味が増し、開店数年で再度転身を図る。長野県東御市が募集していた千曲川ワインアカデミーの3期生として、2017年に移住するのだ。そして、信州うえだファームの研修生として農業研修も受け、2019年に独立する。 ▲ ヨネファーム東御のインスタより。千曲川ワインアカデミーの同期との一枚。いい関係性なのが見て取れる素敵な一枚だ。 米倉さんのブドウ畑は、長野県東御市の3つの場所(鞍掛金井、祢津御堂、海善寺)に跨る。東御市は降水量が少なく、冷涼ながら日照時間は長い。また、畑は540mから780mと標高が高い場所にあり、昼夜の寒暖差のあるワイン用ブドウ栽培に恵まれた場所だ。 独立後すぐに植栽開始したのは鞍掛金井。0.5haの広さに白赤6種類のブドウが植わっている。その後、巨峰が植わる海善寺の畑の管理も開始し、2019年には、東御市がワイン用ブドウ団地として立ち上げた祢津御堂での植栽を開始する。広さ4.1haの畑で、赤白11種類のブドウを栽培している。これだけではない。畑に足を運ぶことが難しくなった千曲川ワインアカデミー同期の0.7haの畑の管理もお手伝いしているというのだから、どこにそんな体力があるのか…⁉と目が点になる。 持続可能なブドウ栽培を目指して 「できるだけ薬は使いたくはないけど、ブドウができないと話にならない」、と米倉さんは語る。東御市はワイン用ブドウ栽培に適した場所ではあるが、「日本の中で」という前提が付く。高温多湿な日本は、世界の銘醸地と比べてブドウが病気にかかるリスクは格段に高い。ブドウ栽培を始めてから3年目までは年3回程度の農薬散布で問題なかったが、4年目になると一気に病気が蔓延して大変な事態に陥ったそうだ。リュー・ド・ヴァンの小山さんも同じことを語っていたが、若木は菌やウイルスの蓄積がなく、無農薬でも大きな問題にはならないことが多いが、年数を重ねるにつれ、病原物質が蓄積され病気が発生しやすくなるのだ。 こういった経験も踏まえ、ビジネスと環境の両立の観点から減農薬栽培を主軸に据え、農薬散布量はJAの防除暦で推奨される量の半分程度に抑えているそうだ。 ▲ 祢津御堂にある米倉さんの畑の様子。眼下に市街地が見え、遠くには八ヶ岳、霧ヶ峰、北アルプスといった美しい山々の絶景が!また、畑の前にはビジターセンターである「ワインテラス御堂」があり、ワインの試飲・販売スペースもある。 気候変動の影響だろうか、極端な空模様になることが増えた昨今。これまでとは異なる対策が求められつつある。2024年は猛暑に加え、8月後半から9月にかけて雨が断続的に降り続く難しい年で、収穫前に一気に晩腐病というカビの病気が広がったそうだ。特に黒ブドウへの影響が大きく、収量は予定の半分程度、メルロに至っては9割方がダメになってしまった。今後も異常気象が続くと言われており、農家にとっては困難な時代だ。米倉さんの畑では雨除けは特に必要としてこなかったが、今年からは祢津御堂のメルロについては、フルーツゾーンだけの雨除けを始める予定だそう。薬に頼らない対策を色々と考えておられるのだ。 ▲ 祢津御堂の畑は、緩やかな斜面だ。広いスペースなので草刈りだけでも本当に大変… 一つに絞るのはもったいない 3つの畑では、白ブドウ6品種(シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、セミヨン、ルーサンヌ、ヴィオニエ)、黒ブドウ9種類(シラー、ムールヴェルドル、グルナッシュ、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、ピノ・ノワール、巨峰)と、多種多様なブドウを育てている。これらはフランスの主なワイン品種であると同時に、世界的にも認知度が高い。 「品種それぞれに美味しさがある。1つに絞るのはもったいないし、決められない」、と米倉さんは言う。ワインに対する深い愛情を感じる言葉だ。これまでは、各品種の収量が少ないということもありブレンドすることが多かったが、いざブレンドしてみると、ブレンドしたからこそ得られる美味しさや組み合わせによる新たな発見もあり、手応えを感じている。 例えば、「メランジュ・ボルドレーズ」というキュヴェでは、ボルドー・ブレンドとして、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルドといった品種がブレンドされているし、「メランジュ・ローダニアン」は、ローヌ地方のワインを彷彿とさせる、シラーとムールヴェルドルのブレンドに仕上がっている。品種や比率は毎年変わるが、こういった楽しさが提供できるのは、多品種を育てているからこそ。 ▲ 千曲川ワインアカデミーの同期と立ち上げたブランド「トロワジエーム」の名を冠したオンラインストア、「トロワジエーム・ワインズ」より。左が「メランジュ・ボルドレーズ」、右が「メランジュ・ローダニアン」。 それ以外にも、「品種毎に収量が毎年異なるので、天候リスクを分散させ、味わいを補完し合える」というビジネス面での有難い側面もある。例えば、「クアチュオール」というキュヴェの白ワインは、セミヨン、ヴィオニエ、シャルドネ、ルーサンヌのブレンド。2023年は各品種ほぼ同等比率のブレンドだったが、2024年はシャルドネが80%以上を占めた。ブレンド比率は異なるが、「クアチュオール」という世界観はそのままに。生産者の意図を感じながら、毎年異なる味わいを楽しめるワインなのだ。 ▲ 「トロワジエーム」より。「クアチュオール」の美しい色調にうっとりする。 困難は一つずつクリアしていく...
長野・ヨネファーム東御
日本ワインコラム |ヨネファーム東御 インタビューのお相手、米倉さんとは、地元で大人気のやきそば・ワンタンのお店「開花亭」で待ち合わせ。到着時には既に長い行列だったが、食い意地の張った我々にとって行列なんて怖くない。米倉さんへのご挨拶も早々に、熱々の焼きそばとワンタンを汗タラタラで食すところからのスタートとなった。こんな素敵なお店での待ち合わせを提案して下さったくらいだし、さぞかし何度も来店しているかと思いきや、2回目という米倉さん。普段はきっと、畑仕事が忙しくて、のんびりランチとはいかないのだろう… ▲ くしゃっとした目元が印象的。優しい笑顔の米倉さん。 2018年に東御市でワイン用ブドウ栽培を開始した米倉さんは、3ヶ所に跨る約5haの畑で多種多様なブドウ品種を一人で栽培するスーパーマンだ。口数は少なめ。反射神経的に言葉を発するのではなく、自分の中で納得したことだけを話すからだろう。だからこそ、発せられる言葉には強い意志を感じる。そんな米倉さんの現在とこれからについて色々とお話を伺った。 広がる畑の管理 米倉さんがワイン業界に足を踏み入れたのは50歳を目前にした頃。その前から15年間毎月ワイン会を開催し、友人達と世界各地のワインを楽しんだり、ブルゴーニュ、ローヌ、カリフォルニアといった銘醸地を訪問し、栽培・醸造を体験したりと、趣味以上仕事未満の熱量でワインと関わってきたが、とうとう仕事にする決意を固め、25年勤務した通信系会社を退職。2015年に東京、神楽坂でワインバー&ショップをオープンしたが、ワインとの関係が深まる中でワイン造りへの興味が増し、開店数年で再度転身を図る。長野県東御市が募集していた千曲川ワインアカデミーの3期生として、2017年に移住するのだ。そして、信州うえだファームの研修生として農業研修も受け、2019年に独立する。 ▲ ヨネファーム東御のインスタより。千曲川ワインアカデミーの同期との一枚。いい関係性なのが見て取れる素敵な一枚だ。 米倉さんのブドウ畑は、長野県東御市の3つの場所(鞍掛金井、祢津御堂、海善寺)に跨る。東御市は降水量が少なく、冷涼ながら日照時間は長い。また、畑は540mから780mと標高が高い場所にあり、昼夜の寒暖差のあるワイン用ブドウ栽培に恵まれた場所だ。 独立後すぐに植栽開始したのは鞍掛金井。0.5haの広さに白赤6種類のブドウが植わっている。その後、巨峰が植わる海善寺の畑の管理も開始し、2019年には、東御市がワイン用ブドウ団地として立ち上げた祢津御堂での植栽を開始する。広さ4.1haの畑で、赤白11種類のブドウを栽培している。これだけではない。畑に足を運ぶことが難しくなった千曲川ワインアカデミー同期の0.7haの畑の管理もお手伝いしているというのだから、どこにそんな体力があるのか…⁉と目が点になる。 持続可能なブドウ栽培を目指して 「できるだけ薬は使いたくはないけど、ブドウができないと話にならない」、と米倉さんは語る。東御市はワイン用ブドウ栽培に適した場所ではあるが、「日本の中で」という前提が付く。高温多湿な日本は、世界の銘醸地と比べてブドウが病気にかかるリスクは格段に高い。ブドウ栽培を始めてから3年目までは年3回程度の農薬散布で問題なかったが、4年目になると一気に病気が蔓延して大変な事態に陥ったそうだ。リュー・ド・ヴァンの小山さんも同じことを語っていたが、若木は菌やウイルスの蓄積がなく、無農薬でも大きな問題にはならないことが多いが、年数を重ねるにつれ、病原物質が蓄積され病気が発生しやすくなるのだ。 こういった経験も踏まえ、ビジネスと環境の両立の観点から減農薬栽培を主軸に据え、農薬散布量はJAの防除暦で推奨される量の半分程度に抑えているそうだ。 ▲ 祢津御堂にある米倉さんの畑の様子。眼下に市街地が見え、遠くには八ヶ岳、霧ヶ峰、北アルプスといった美しい山々の絶景が!また、畑の前にはビジターセンターである「ワインテラス御堂」があり、ワインの試飲・販売スペースもある。 気候変動の影響だろうか、極端な空模様になることが増えた昨今。これまでとは異なる対策が求められつつある。2024年は猛暑に加え、8月後半から9月にかけて雨が断続的に降り続く難しい年で、収穫前に一気に晩腐病というカビの病気が広がったそうだ。特に黒ブドウへの影響が大きく、収量は予定の半分程度、メルロに至っては9割方がダメになってしまった。今後も異常気象が続くと言われており、農家にとっては困難な時代だ。米倉さんの畑では雨除けは特に必要としてこなかったが、今年からは祢津御堂のメルロについては、フルーツゾーンだけの雨除けを始める予定だそう。薬に頼らない対策を色々と考えておられるのだ。 ▲ 祢津御堂の畑は、緩やかな斜面だ。広いスペースなので草刈りだけでも本当に大変… 一つに絞るのはもったいない 3つの畑では、白ブドウ6品種(シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリング、セミヨン、ルーサンヌ、ヴィオニエ)、黒ブドウ9種類(シラー、ムールヴェルドル、グルナッシュ、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルド、ピノ・ノワール、巨峰)と、多種多様なブドウを育てている。これらはフランスの主なワイン品種であると同時に、世界的にも認知度が高い。 「品種それぞれに美味しさがある。1つに絞るのはもったいないし、決められない」、と米倉さんは言う。ワインに対する深い愛情を感じる言葉だ。これまでは、各品種の収量が少ないということもありブレンドすることが多かったが、いざブレンドしてみると、ブレンドしたからこそ得られる美味しさや組み合わせによる新たな発見もあり、手応えを感じている。 例えば、「メランジュ・ボルドレーズ」というキュヴェでは、ボルドー・ブレンドとして、メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・ヴェルドといった品種がブレンドされているし、「メランジュ・ローダニアン」は、ローヌ地方のワインを彷彿とさせる、シラーとムールヴェルドルのブレンドに仕上がっている。品種や比率は毎年変わるが、こういった楽しさが提供できるのは、多品種を育てているからこそ。 ▲ 千曲川ワインアカデミーの同期と立ち上げたブランド「トロワジエーム」の名を冠したオンラインストア、「トロワジエーム・ワインズ」より。左が「メランジュ・ボルドレーズ」、右が「メランジュ・ローダニアン」。 それ以外にも、「品種毎に収量が毎年異なるので、天候リスクを分散させ、味わいを補完し合える」というビジネス面での有難い側面もある。例えば、「クアチュオール」というキュヴェの白ワインは、セミヨン、ヴィオニエ、シャルドネ、ルーサンヌのブレンド。2023年は各品種ほぼ同等比率のブレンドだったが、2024年はシャルドネが80%以上を占めた。ブレンド比率は異なるが、「クアチュオール」という世界観はそのままに。生産者の意図を感じながら、毎年異なる味わいを楽しめるワインなのだ。 ▲ 「トロワジエーム」より。「クアチュオール」の美しい色調にうっとりする。 困難は一つずつクリアしていく...

長野県・アクアテラソル馨光庵
日本ワインコラム |アクアテラソル馨光庵(けいこうあん) なにせ絶妙なのだ。 独立独歩のようで繋がっている。信頼と尊敬の隣に緊張感がある。 2023年9月、東御市鞍掛にオープンしたワイナリー、アクアテラソル馨光庵を舞台にした主人公たちの関係だ。代表を務める平井さんと醸造責任者の中田さんの話を聞くと、いい意味で「人生何が起こるか本当に分からないなぁ」という気になる。 ▲ ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。 ▲ 左側が平井さん、右側が中田さん。 始まりの前夜 ビジネスパートナーであり、師弟関係でもある平井さんと中田さん。ワイナリーを建てる前までは全く別の人生を歩んでいた。 平井さんの歩み ▲ チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。 平井さんは東京の司法書士事務所を経営するビジネスマンであり、ワインラバーでもあった。ワインへの気持ちが高まり、2018年に事務所を後進にゆずり、52歳で長野県に移住。千曲川ワインアカデミーでワイン造りを学び、信州うえだファームで農業研修を受け、就農する。東京での安定した生活を捨てられたのは、ワイン愛の強さ故かもしれないが、好奇心の強さ、柔軟な考え方、思い切りの良さといったところにも秘密がありそうだ。また、人との出会いを縁に変えるチャーミングな人柄を忘れてはいけない。 農業研修先でのカーヴ・ハタノの波田野氏との出会いが転機となる。「波田野さんの造るワインが本当に美味しくて、衝撃が走った!ワイン造りの師匠ではあるが、自分は波田野さんの大ファンで追っかけ。家のセラーは波田野さんのワインだらけで、垂直で全て揃えている」、と豪語するほど。好きになったら一直線。ツンデレなんて言葉は辞書にないほど、好き光線が出る。この光線を浴びた人は、平井さんを好きにならずにはいられないのだ。 中田さんの歩み ▲ 中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。 一方の中田さんも東京出身。祖父の代まで農家を営む家で生まれた。農家になりたいという夢を追いかけ、2012年、ヴィラデスト・ワイナリーへの就職を機に長野県東御市に移住。ワイナリースタッフも、併設のレストランで提供する野菜栽培を担っていたそうだ。そして、当時ヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めていたのが波田野さんだった。「波田野さんも自分も移住組。若造の頃から公私共に本当にお世話になって、心から信頼している先輩」だと言う。 波田野さんが独立後、中田さんがヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めたが、2019年に独立する----野菜農家として。えぇっっ‼ワイナリーじゃないの~!?と思ってしまうが、元々野菜農家になりたかった本人にとっては当然の選択だ。中田さんにとって、玉ねぎもブドウも同じ農作物。ただ、独立後もシャルドネの一枚畑は持ち続け、カーヴ・ハタノで委託醸造していたという。 「ワイン」ではなく、「農業」からスタートしているからこその選択だ。周りと比較せず、夢を持ち続け、臨機応変に動く。どっしりしつつ軽やかなのだ。 それぞれの歩みが重なる~ワイナリーの始動 別々の道を歩んでいた2人を結びつけたのは、波田野さん。ある日、野菜農家として汗を流していた中田さんに天の一言が下り、平井さんと中田さんが急接近するのだ。 (波田野)「ちょっと遊びの話なんだけど、とある人ともう一軒ワイナリーを建てようと思っててさ。お前、醸造長やるだろ?」 (中田)「え?あ…はい!」 これで決まったらしい。「とある人」とはもちろん平井さんのこと。平井さんの熱意をくんだ波田野さんが一役を買ってくれたのだ。「手にしたものは地域のために活かしなさい」と波田野さんから常々言われていたそうだが、野菜農家として独立したはずの中田さんが即決するとは…恐るべし師弟関係! ▲ アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。 思いが詰まったワイナリー建設...
長野県・アクアテラソル馨光庵
日本ワインコラム |アクアテラソル馨光庵(けいこうあん) なにせ絶妙なのだ。 独立独歩のようで繋がっている。信頼と尊敬の隣に緊張感がある。 2023年9月、東御市鞍掛にオープンしたワイナリー、アクアテラソル馨光庵を舞台にした主人公たちの関係だ。代表を務める平井さんと醸造責任者の中田さんの話を聞くと、いい意味で「人生何が起こるか本当に分からないなぁ」という気になる。 ▲ ワイナリー外観。下見板張の外壁と瓦葺き屋根が美しい伝統的な日本家屋の建物だ。 ▲ 左側が平井さん、右側が中田さん。 始まりの前夜 ビジネスパートナーであり、師弟関係でもある平井さんと中田さん。ワイナリーを建てる前までは全く別の人生を歩んでいた。 平井さんの歩み ▲ チャーミングな笑顔で周りを虜にする平井さん。 平井さんは東京の司法書士事務所を経営するビジネスマンであり、ワインラバーでもあった。ワインへの気持ちが高まり、2018年に事務所を後進にゆずり、52歳で長野県に移住。千曲川ワインアカデミーでワイン造りを学び、信州うえだファームで農業研修を受け、就農する。東京での安定した生活を捨てられたのは、ワイン愛の強さ故かもしれないが、好奇心の強さ、柔軟な考え方、思い切りの良さといったところにも秘密がありそうだ。また、人との出会いを縁に変えるチャーミングな人柄を忘れてはいけない。 農業研修先でのカーヴ・ハタノの波田野氏との出会いが転機となる。「波田野さんの造るワインが本当に美味しくて、衝撃が走った!ワイン造りの師匠ではあるが、自分は波田野さんの大ファンで追っかけ。家のセラーは波田野さんのワインだらけで、垂直で全て揃えている」、と豪語するほど。好きになったら一直線。ツンデレなんて言葉は辞書にないほど、好き光線が出る。この光線を浴びた人は、平井さんを好きにならずにはいられないのだ。 中田さんの歩み ▲ 中田さんの語り口は揺るぎなく、説得力に満ちている。 一方の中田さんも東京出身。祖父の代まで農家を営む家で生まれた。農家になりたいという夢を追いかけ、2012年、ヴィラデスト・ワイナリーへの就職を機に長野県東御市に移住。ワイナリースタッフも、併設のレストランで提供する野菜栽培を担っていたそうだ。そして、当時ヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めていたのが波田野さんだった。「波田野さんも自分も移住組。若造の頃から公私共に本当にお世話になって、心から信頼している先輩」だと言う。 波田野さんが独立後、中田さんがヴィラデストで栽培・醸造の責任者を務めたが、2019年に独立する----野菜農家として。えぇっっ‼ワイナリーじゃないの~!?と思ってしまうが、元々野菜農家になりたかった本人にとっては当然の選択だ。中田さんにとって、玉ねぎもブドウも同じ農作物。ただ、独立後もシャルドネの一枚畑は持ち続け、カーヴ・ハタノで委託醸造していたという。 「ワイン」ではなく、「農業」からスタートしているからこその選択だ。周りと比較せず、夢を持ち続け、臨機応変に動く。どっしりしつつ軽やかなのだ。 それぞれの歩みが重なる~ワイナリーの始動 別々の道を歩んでいた2人を結びつけたのは、波田野さん。ある日、野菜農家として汗を流していた中田さんに天の一言が下り、平井さんと中田さんが急接近するのだ。 (波田野)「ちょっと遊びの話なんだけど、とある人ともう一軒ワイナリーを建てようと思っててさ。お前、醸造長やるだろ?」 (中田)「え?あ…はい!」 これで決まったらしい。「とある人」とはもちろん平井さんのこと。平井さんの熱意をくんだ波田野さんが一役を買ってくれたのだ。「手にしたものは地域のために活かしなさい」と波田野さんから常々言われていたそうだが、野菜農家として独立したはずの中田さんが即決するとは…恐るべし師弟関係! ▲ アクアテラソル馨光庵HPより。平井さんと中田さんを結びつけた波田野さんにも色々とお話を伺ってみたい。 思いが詰まったワイナリー建設...

長野・ソラリスシリーズ vol.2
日本ワインコラム | ソラリスシリーズ vol.2 / vol.1 はこちら マンズワイン最高峰のプレミアムワイン「ソラリス」シリーズを手掛ける小諸ワイナリー。営業部の島田さんと渡辺さんの計らいもあり、前回から約1年と間を空けず再訪することができた。翌週から梅雨入りするのだが、我々がお邪魔した日は快晴。暑かったぁ~!湿度はなく、日陰に入れば涼しいものの、標高が高い分紫外線は強く、日差しが痛いほど。そんなアツイ日に、チームの皆さんから激アツな話を沢山伺った。 ▲ 前回同様、ソラリス愛、チーム愛溢れる話を沢山シェアして下さった島田さん。 ▲ 新たにソラリスチームに加わった渡辺さんは、苦労も笑いに変えてしまう、ワイン愛とガッツの塊のようなお方。 ソラリスシリーズが生まれた背景やワインの美味しさの秘密については、前回のコラムに纏めているので参照頂きたい。確かに素晴らしい環境下でワイン造りが行われているが、条件全てに於いて恵まれているとも言いきれない。そんな中でも世界と肩を並べるワインを輩出している背景には、「制限」という存在や「基準」の不在に対してチームが真摯に向き合っていることも大きいと思われ、Vol.2となる今回はそこにフォーカスを当てたい。また、番外編として、小諸ワイナリーに訪れた際に足を運びたいスポットも紹介していく。 制限があることの難しさ~徹底的に考えるからこそ広がる可能性 小諸は冷涼な気候で、降雨量が少なく日照時間が長い、そして寒暖差が大きい内陸性の気候で、日本ではワイン用ブドウ栽培に向いている場所である。しかし、ソラリスシリーズを造る小諸ワイナリーがベンチマークとして捉えるのは世界の銘醸地だ。そうすると、否が応でも気候の違いや歴史の短さなどの様々な壁にぶち当たる。しかし、「難しい!」と嘆いて匙を投げるのではない。難しいからこそ挑戦し、高みを目指しているのだ。 有機という制限に挑戦する理由 世界に比べて圧倒的に降雨量が多い日本で有機栽培を行うことは極めて難しい。そんな中、前回のコラムの「有機栽培に挑戦する」という段落でも紹介した通り、2010年から有機栽培に挑戦し、現在は畑の40%程度が有機に移行済だ。有機JASの認定を受けているのは、市場にアピールしたいからではない。「JAS認定という制限があることで、ブドウ栽培に対して深く考えざるを得ないから認定を受けている」そうだ。病気の兆しが現れたらすぐ薬を撒いていては栽培者として成長しない。そもそも病気にならないためにできることを模索する。 「考え抜いた先にしか可能性は広がらない」 というのが栽培・醸造責任者の西畑氏がチームに説く姿勢だ。 ▲(左)株元の草刈りや、畑の周りの藪の整備はマスト。病気の原因になる虫の住処を与えないのだ。「1日かけて草抜いても、複数列終わる程度っすよ!!有機ってほっんとーに大変なんです!」と渡辺さんが力説すれば、その隣で「草を刈っても2週間で元通りになりますしね…」と常勤顧問の松宮さんが達観した表情で付け加えられた。 ▲(中央)徹底的に管理してもコウモリガの幼虫が樹に入り、食害を引き起こすことも。見つけたら即駆除するそう。 ▲(右)最近導入された自動芝刈りロボット。草食の羊から「めぇちゃん」と名付けられた。戦力になるかどうか…? 島田さんはこうも言う。 「我々が自社で管理する畑の広さは12haのみ。全て有機にしたところで、周辺環境に与えるインパクトは微々たるもの。それよりも、有機でもブドウ栽培できるということを他の農家に示し、業界全体に影響を与えることの方が重要」と。 その観点で、日本固有品種のマスカット・ベーリーAを有機栽培し、そのワインが「Japan Wine Competition 2024」で金賞を受賞したことは意義深い。慣行栽培を続ける周辺農家に対しても、有機で高品質のものができるという結果を見せることができたのだ。一つ一つ結果を積み重ねることで、いつか大きな変化が生まれる。そんな予感を感じさせる話だ。 ないものは作る ヨーロッパに比べ、日本ではワイン用ブドウの苗木を手に入れるのは難しい。ワイナリーの数が増える中、苗木不足も指摘されている。ワイン用ブドウは、フィロキセラという虫対策のため、フィロキセラに耐性のある北米系品種を台木とし、その台木にヨーロッパ系の品種を接いで1つの苗木にする。マンズワインの小諸ワイナリーでは、台木も栽培し、苗木作りまで行っている。昨年、3,000本ほど接いだというのだから、大規模だ!...
長野・ソラリスシリーズ vol.2
日本ワインコラム | ソラリスシリーズ vol.2 / vol.1 はこちら マンズワイン最高峰のプレミアムワイン「ソラリス」シリーズを手掛ける小諸ワイナリー。営業部の島田さんと渡辺さんの計らいもあり、前回から約1年と間を空けず再訪することができた。翌週から梅雨入りするのだが、我々がお邪魔した日は快晴。暑かったぁ~!湿度はなく、日陰に入れば涼しいものの、標高が高い分紫外線は強く、日差しが痛いほど。そんなアツイ日に、チームの皆さんから激アツな話を沢山伺った。 ▲ 前回同様、ソラリス愛、チーム愛溢れる話を沢山シェアして下さった島田さん。 ▲ 新たにソラリスチームに加わった渡辺さんは、苦労も笑いに変えてしまう、ワイン愛とガッツの塊のようなお方。 ソラリスシリーズが生まれた背景やワインの美味しさの秘密については、前回のコラムに纏めているので参照頂きたい。確かに素晴らしい環境下でワイン造りが行われているが、条件全てに於いて恵まれているとも言いきれない。そんな中でも世界と肩を並べるワインを輩出している背景には、「制限」という存在や「基準」の不在に対してチームが真摯に向き合っていることも大きいと思われ、Vol.2となる今回はそこにフォーカスを当てたい。また、番外編として、小諸ワイナリーに訪れた際に足を運びたいスポットも紹介していく。 制限があることの難しさ~徹底的に考えるからこそ広がる可能性 小諸は冷涼な気候で、降雨量が少なく日照時間が長い、そして寒暖差が大きい内陸性の気候で、日本ではワイン用ブドウ栽培に向いている場所である。しかし、ソラリスシリーズを造る小諸ワイナリーがベンチマークとして捉えるのは世界の銘醸地だ。そうすると、否が応でも気候の違いや歴史の短さなどの様々な壁にぶち当たる。しかし、「難しい!」と嘆いて匙を投げるのではない。難しいからこそ挑戦し、高みを目指しているのだ。 有機という制限に挑戦する理由 世界に比べて圧倒的に降雨量が多い日本で有機栽培を行うことは極めて難しい。そんな中、前回のコラムの「有機栽培に挑戦する」という段落でも紹介した通り、2010年から有機栽培に挑戦し、現在は畑の40%程度が有機に移行済だ。有機JASの認定を受けているのは、市場にアピールしたいからではない。「JAS認定という制限があることで、ブドウ栽培に対して深く考えざるを得ないから認定を受けている」そうだ。病気の兆しが現れたらすぐ薬を撒いていては栽培者として成長しない。そもそも病気にならないためにできることを模索する。 「考え抜いた先にしか可能性は広がらない」 というのが栽培・醸造責任者の西畑氏がチームに説く姿勢だ。 ▲(左)株元の草刈りや、畑の周りの藪の整備はマスト。病気の原因になる虫の住処を与えないのだ。「1日かけて草抜いても、複数列終わる程度っすよ!!有機ってほっんとーに大変なんです!」と渡辺さんが力説すれば、その隣で「草を刈っても2週間で元通りになりますしね…」と常勤顧問の松宮さんが達観した表情で付け加えられた。 ▲(中央)徹底的に管理してもコウモリガの幼虫が樹に入り、食害を引き起こすことも。見つけたら即駆除するそう。 ▲(右)最近導入された自動芝刈りロボット。草食の羊から「めぇちゃん」と名付けられた。戦力になるかどうか…? 島田さんはこうも言う。 「我々が自社で管理する畑の広さは12haのみ。全て有機にしたところで、周辺環境に与えるインパクトは微々たるもの。それよりも、有機でもブドウ栽培できるということを他の農家に示し、業界全体に影響を与えることの方が重要」と。 その観点で、日本固有品種のマスカット・ベーリーAを有機栽培し、そのワインが「Japan Wine Competition 2024」で金賞を受賞したことは意義深い。慣行栽培を続ける周辺農家に対しても、有機で高品質のものができるという結果を見せることができたのだ。一つ一つ結果を積み重ねることで、いつか大きな変化が生まれる。そんな予感を感じさせる話だ。 ないものは作る ヨーロッパに比べ、日本ではワイン用ブドウの苗木を手に入れるのは難しい。ワイナリーの数が増える中、苗木不足も指摘されている。ワイン用ブドウは、フィロキセラという虫対策のため、フィロキセラに耐性のある北米系品種を台木とし、その台木にヨーロッパ系の品種を接いで1つの苗木にする。マンズワインの小諸ワイナリーでは、台木も栽培し、苗木作りまで行っている。昨年、3,000本ほど接いだというのだから、大規模だ!...

広島・三次ワイナリー
日本ワインコラム |広島三次ワイナリー 「三次」と書いて「みよし」と読む。広島県の北部、中国地方の中心部に位置し、江の川、馬洗川、西城川の3本の大きな川が巴状に合流する盆地である。ブドウ栽培が始まったのは1955年頃からと言われており、今では“黒い真珠”と称されるピオーネの一大産地として有名な場所だ。 1994年に広島県初のワイナリーとしてこの地に誕生したのが、今回の訪問先である広島三次ワイナリー。今年創業30周年を迎える歴史のあるワイナリーだ。第三セクターとして誕生したという背景もあり、当初は観光ワイナリー的な位置づけで捉えられていたが、昨今は国内外から高く評価される本格的なワインで名を馳せ、多くのファンを魅了する。 ▲ 広島三次ワイナリーの外観。赤い屋根と高い塔が印象的で、外観からも広々した場所なのが分かる。沢山の方が訪れる場所で、到着した日も駐車場はほぼ満車! 質の高いワインを造り出す秘密はどこにあるのか?生粋の三次っ子だという製造課マネージャーの沖田さんに色々とお話を伺った。 ▲ 安心感のある語り口の沖田さん。広島三次ワイナリー栽培・醸造チームのインスタに“好青年を装った毒舌男”と紹介されていたのが気になる…笑。我々には“好青年“としか思えなかったです!! 観光ワイナリーからの脱却 広島三次ワイナリーは三次市やJAひろしま等が出資する第三セクターとして誕生。生食用ブドウを栽培する過程で出る大量の規格外のブドウを活用するという目的から創設された経緯もあり、設立当時は観光ワインとしての色合いが強いものだった。ワイナリーには観光客向けの施設も充実しており、集客も業績も安定していたが、日本ワインブームの到来と共に、土地の個性を活かした本格的なワインに注目が集まり、観光ワインが淘汰されつつあるという現実も目の当たりにする。 ▲ ワインショップの前には白い椅子が沢山並び、ゆったり過ごせるスペースも。 ▲ ワインショップの中の様子。ワインがずらり並ぶ! このままでは生き残れない…という危機感が募り、経営陣は1つの大きな決断をする。これまでの観光ワイナリーとして位置付けから経営方針をシフトし、原料から見直したのだ。2007年に自社圃場を確保しブドウ栽培を開始、2008年には三次産ブドウ100%で造るTOMOEシリーズをスタートした。 更に、2つ目の大きな決断となったのが、2013年に後にワイナリー長となる太田直幸氏を迎え入れたことだ。 ▲ 広島三次ワイナリーのHPより。優しい笑顔が素敵な太田氏。 太田氏はニュージーランドのリンカーン大学でブドウ栽培とワイン醸造の勉強をし、現地の農園やワイナリーで長く働いた経験を持つ。沖田さん曰く、太田氏は「ブドウのいいところを最大限に引き出す」という考えをお持ちで、これまでとは異なるアプローチで、質を重視した栽培や醸造を徹底したそう。その結果、ワインの質が向上し味わいも本格的に。国内外の数々のコンクールで受賞するまでになったのだ。 経営方針を180度変え、一から新しい文化を作り上げた広島三次ワイナリー。強いリーダーシップなしには成しえなかったと思うが、三次という場所の優位性、栽培家や醸造家一人一人の情熱も忘れてはいけない。まずは畑から見ていこう。 恵まれた畑の環境 盆地ならではの優位性 ワイナリーから車で程近く、山間部を切り開いた場所に畑がある。標高350m前後、一番高いTOMOEシリーズ「シャルドネ新月」の畑は標高400mに位置する。どの畑も開けた場所にあるので、日の出から日の入りまでしっかりと太陽が当たる。また、盆地ならではの気候で、昼夜の寒暖差が大きく、ブドウがゆっくり熟す環境にある。山肌を通る風も吹くので、比較的病気になりにくい環境なのも嬉しいところだ。 ▲ さーっと視界が開けた場所にあるブドウ畑。太陽の恵みを感じながら、心地よい風も吹き抜ける。 恵まれた環境とは言え、温暖化の影響はある。「シャルドネ新月」は、新月の夜に収穫するナイトハーベストを行っていたことから命名されたワインだが、昨今は夜間も気温が高い日が多く、夜に収穫するメリットが下がってきていることと、夜間の作業は摘み残しも起こりやすいことから、昼間に収穫した後、ブドウをしっかり冷蔵し酸化や腐敗を防ぐという手法に切り替えたそう。 ▲ 棚栽培されている「シャルドネ新月」の畑。棚の高さは奥に進むほど低くなっているそうで、「手前は問題ないのだけど、奥に行くほど中腰で辛くなる…けど、すごくいい農家さんが手入れしてくれて、素晴らしいブドウができている」と、沖田さん。 日本で珍しい貴腐ブドウが育つ場所...
広島・三次ワイナリー
日本ワインコラム |広島三次ワイナリー 「三次」と書いて「みよし」と読む。広島県の北部、中国地方の中心部に位置し、江の川、馬洗川、西城川の3本の大きな川が巴状に合流する盆地である。ブドウ栽培が始まったのは1955年頃からと言われており、今では“黒い真珠”と称されるピオーネの一大産地として有名な場所だ。 1994年に広島県初のワイナリーとしてこの地に誕生したのが、今回の訪問先である広島三次ワイナリー。今年創業30周年を迎える歴史のあるワイナリーだ。第三セクターとして誕生したという背景もあり、当初は観光ワイナリー的な位置づけで捉えられていたが、昨今は国内外から高く評価される本格的なワインで名を馳せ、多くのファンを魅了する。 ▲ 広島三次ワイナリーの外観。赤い屋根と高い塔が印象的で、外観からも広々した場所なのが分かる。沢山の方が訪れる場所で、到着した日も駐車場はほぼ満車! 質の高いワインを造り出す秘密はどこにあるのか?生粋の三次っ子だという製造課マネージャーの沖田さんに色々とお話を伺った。 ▲ 安心感のある語り口の沖田さん。広島三次ワイナリー栽培・醸造チームのインスタに“好青年を装った毒舌男”と紹介されていたのが気になる…笑。我々には“好青年“としか思えなかったです!! 観光ワイナリーからの脱却 広島三次ワイナリーは三次市やJAひろしま等が出資する第三セクターとして誕生。生食用ブドウを栽培する過程で出る大量の規格外のブドウを活用するという目的から創設された経緯もあり、設立当時は観光ワインとしての色合いが強いものだった。ワイナリーには観光客向けの施設も充実しており、集客も業績も安定していたが、日本ワインブームの到来と共に、土地の個性を活かした本格的なワインに注目が集まり、観光ワインが淘汰されつつあるという現実も目の当たりにする。 ▲ ワインショップの前には白い椅子が沢山並び、ゆったり過ごせるスペースも。 ▲ ワインショップの中の様子。ワインがずらり並ぶ! このままでは生き残れない…という危機感が募り、経営陣は1つの大きな決断をする。これまでの観光ワイナリーとして位置付けから経営方針をシフトし、原料から見直したのだ。2007年に自社圃場を確保しブドウ栽培を開始、2008年には三次産ブドウ100%で造るTOMOEシリーズをスタートした。 更に、2つ目の大きな決断となったのが、2013年に後にワイナリー長となる太田直幸氏を迎え入れたことだ。 ▲ 広島三次ワイナリーのHPより。優しい笑顔が素敵な太田氏。 太田氏はニュージーランドのリンカーン大学でブドウ栽培とワイン醸造の勉強をし、現地の農園やワイナリーで長く働いた経験を持つ。沖田さん曰く、太田氏は「ブドウのいいところを最大限に引き出す」という考えをお持ちで、これまでとは異なるアプローチで、質を重視した栽培や醸造を徹底したそう。その結果、ワインの質が向上し味わいも本格的に。国内外の数々のコンクールで受賞するまでになったのだ。 経営方針を180度変え、一から新しい文化を作り上げた広島三次ワイナリー。強いリーダーシップなしには成しえなかったと思うが、三次という場所の優位性、栽培家や醸造家一人一人の情熱も忘れてはいけない。まずは畑から見ていこう。 恵まれた畑の環境 盆地ならではの優位性 ワイナリーから車で程近く、山間部を切り開いた場所に畑がある。標高350m前後、一番高いTOMOEシリーズ「シャルドネ新月」の畑は標高400mに位置する。どの畑も開けた場所にあるので、日の出から日の入りまでしっかりと太陽が当たる。また、盆地ならではの気候で、昼夜の寒暖差が大きく、ブドウがゆっくり熟す環境にある。山肌を通る風も吹くので、比較的病気になりにくい環境なのも嬉しいところだ。 ▲ さーっと視界が開けた場所にあるブドウ畑。太陽の恵みを感じながら、心地よい風も吹き抜ける。 恵まれた環境とは言え、温暖化の影響はある。「シャルドネ新月」は、新月の夜に収穫するナイトハーベストを行っていたことから命名されたワインだが、昨今は夜間も気温が高い日が多く、夜に収穫するメリットが下がってきていることと、夜間の作業は摘み残しも起こりやすいことから、昼間に収穫した後、ブドウをしっかり冷蔵し酸化や腐敗を防ぐという手法に切り替えたそう。 ▲ 棚栽培されている「シャルドネ新月」の畑。棚の高さは奥に進むほど低くなっているそうで、「手前は問題ないのだけど、奥に行くほど中腰で辛くなる…けど、すごくいい農家さんが手入れしてくれて、素晴らしいブドウができている」と、沖田さん。 日本で珍しい貴腐ブドウが育つ場所...

岡山・コルトラーダ
日本ワインコラム |コルトラーダ 梅雨とは思えないほどの猛暑に見舞われた前週とは打って変わり、訪問前夜に大雨に見舞われた中国地方…波乱の幕開けである。東京からの参加組は首尾よく飛行機で岡山空港に入り、レンタカー移動したのだが、電車&バスで現地入り予定だったライターは大雨の影響で足止め。取材に間に合わなかったのだ(涙)。ということで、今回は、いつもと少し方法を変えて。チームから受け取った情報を元に、皆さまにお伝えしたいと思う。 ▲ ワイナリーの外観。木をふんだんに使った造りで趣がある。 ▲ 窓際のディスプレイに温かみを感じる。 岡山県新見市にあるコルトラーダ。岡山空港から車で北西に1時間半。岡山駅から特急電車とタクシーで移動した場合も1時間半といった距離感だ。この地に移住し、ワイン造りに向き合っているのが今回の取材相手の保坂耕三さん。淡々とした語り口だけど、おかしいと思うことはきちんと口にする様子に不屈の精神を感じ、全てを包み隠さず語られる姿に誠実で実直なお人柄を感じさせられた。やはり、強い人は優しいのだ。 ▲ くしゃっとした笑顔を見せてくれた保坂さん。つられて笑ってしまいそうだ。 今すぐ中国・四国のワインをチェック! ワインに出会う前 保坂さんが新見市に移住したのは2011年秋。以前は有機野菜の栽培、流通、販売などに長く従事されていた。また、1999年に法改正され導入された有機JASの認定審査の事務局にもおられ、初年度の認定業務を担当されたそう。「関係者全員が手探り状態だった」と振り返られた言葉から、その仕事の大変さがひしひしと伝わってくる… この頃の保坂さんは、ワインに対してちょっとお高くとまった印象をお持ちだったようだ。ところが、イタリア旅行でそのイメージは覆され、ワイン造りの道に進むことを決めてしまうのだ。 カーゼ・コリーニのロレンツォ氏との出会いで 運命の出会いとなったのが、イタリア、ピエモンテ州にあるワイナリー「カーゼ・コリーニ」。 持続可能で自然なワインを造ることで本国イタリアのみならず、日本でも人気のあるワイナリーなので、ご存知の方も多いだろう。保坂さんは2010年にここを訪れ、2021年に惜しくもお亡くなりになった前当主のロレンツォ氏と直接会話した。ロレンツォ氏は地質学を専門とする農業博士であり、イギリス・ケンブリッジにある研究機関で穀類の耐性遺伝性の研究プロジェクトに従事したり、国立ブドウ栽培研究所で持続可能なブドウ栽培についての研究をしたりと、学術的な活動でも知られる御仁だ。 もともと有機栽培の分野に長く身を置いていたからだろう、ロレンツォ氏とすぐに意気投合したようだ。土の重要性について語り合う中で、「ワインも農業だ」と腹落ちしたそうだ。 これまでも農業をしたいという希望はあったものの、鮮度が命で時間との勝負となる野菜栽培には二の足を踏んでいた。ワインはブドウを収穫してから醸造という時間が入る。いい、悪いは抜きにして、自分に向いていると思った。 「ワインを造ろう。」…即決だった。 鉄は熱いうちに打て ▲ コルトラーダのフェイスブックアカウントより。グラデーションのある青空、立ち上がる雲、こんもりした緑、そして遠目に見える虹!!!これは、恋に落ちてしまう景色だ。 イタリア旅行から戻ってからの動きが早い。会社を辞め、岡山県新見市に移住したのが2011年秋。北海道は函館のご出身で、移住前は首都圏におられたので、西日本は少し縁遠い気がするが、自然豊かな環境に魅了されたのと、ワイン用ブドウを栽培している法人が既にあったということが決め手になったようだ。 2012年には同じ地域にあるドメーヌ・テッタ( → 詳細はこちら)でブドウ栽培の研修を始める。2013年からは畑を少しずつ開墾し、2014年は栃木、2015、16年は長野のワイナリーで委託醸造した。2017年から2020年の間は県内にあるラ・グランド・コリーヌで委託醸造し、収穫以降はブドウ以外に何も加えないスタイルでのワイン造りを確立。 そして、2021年に自社ワイナリーを立ち上げた。ワイン造りを志してから、急ピッチで体制を整えられた保坂さん。年数だけ追っていると順風満帆のように思えるが、目まぐるしい10数年だったに違いない。 合理的な考え方から生まれる自然なワイン造り 保坂さんのワインは所謂「自然派」とカテゴライズされる部類に入るだろう。畑では除草剤は使わず、殺虫剤は使うとしても年に1回程度、農薬も必要最低限の使用に限られる。醸造の過程でも亜硫酸といった添加物は一切使わず、ブドウだけでワインを造っている。...
岡山・コルトラーダ
日本ワインコラム |コルトラーダ 梅雨とは思えないほどの猛暑に見舞われた前週とは打って変わり、訪問前夜に大雨に見舞われた中国地方…波乱の幕開けである。東京からの参加組は首尾よく飛行機で岡山空港に入り、レンタカー移動したのだが、電車&バスで現地入り予定だったライターは大雨の影響で足止め。取材に間に合わなかったのだ(涙)。ということで、今回は、いつもと少し方法を変えて。チームから受け取った情報を元に、皆さまにお伝えしたいと思う。 ▲ ワイナリーの外観。木をふんだんに使った造りで趣がある。 ▲ 窓際のディスプレイに温かみを感じる。 岡山県新見市にあるコルトラーダ。岡山空港から車で北西に1時間半。岡山駅から特急電車とタクシーで移動した場合も1時間半といった距離感だ。この地に移住し、ワイン造りに向き合っているのが今回の取材相手の保坂耕三さん。淡々とした語り口だけど、おかしいと思うことはきちんと口にする様子に不屈の精神を感じ、全てを包み隠さず語られる姿に誠実で実直なお人柄を感じさせられた。やはり、強い人は優しいのだ。 ▲ くしゃっとした笑顔を見せてくれた保坂さん。つられて笑ってしまいそうだ。 今すぐ中国・四国のワインをチェック! ワインに出会う前 保坂さんが新見市に移住したのは2011年秋。以前は有機野菜の栽培、流通、販売などに長く従事されていた。また、1999年に法改正され導入された有機JASの認定審査の事務局にもおられ、初年度の認定業務を担当されたそう。「関係者全員が手探り状態だった」と振り返られた言葉から、その仕事の大変さがひしひしと伝わってくる… この頃の保坂さんは、ワインに対してちょっとお高くとまった印象をお持ちだったようだ。ところが、イタリア旅行でそのイメージは覆され、ワイン造りの道に進むことを決めてしまうのだ。 カーゼ・コリーニのロレンツォ氏との出会いで 運命の出会いとなったのが、イタリア、ピエモンテ州にあるワイナリー「カーゼ・コリーニ」。 持続可能で自然なワインを造ることで本国イタリアのみならず、日本でも人気のあるワイナリーなので、ご存知の方も多いだろう。保坂さんは2010年にここを訪れ、2021年に惜しくもお亡くなりになった前当主のロレンツォ氏と直接会話した。ロレンツォ氏は地質学を専門とする農業博士であり、イギリス・ケンブリッジにある研究機関で穀類の耐性遺伝性の研究プロジェクトに従事したり、国立ブドウ栽培研究所で持続可能なブドウ栽培についての研究をしたりと、学術的な活動でも知られる御仁だ。 もともと有機栽培の分野に長く身を置いていたからだろう、ロレンツォ氏とすぐに意気投合したようだ。土の重要性について語り合う中で、「ワインも農業だ」と腹落ちしたそうだ。 これまでも農業をしたいという希望はあったものの、鮮度が命で時間との勝負となる野菜栽培には二の足を踏んでいた。ワインはブドウを収穫してから醸造という時間が入る。いい、悪いは抜きにして、自分に向いていると思った。 「ワインを造ろう。」…即決だった。 鉄は熱いうちに打て ▲ コルトラーダのフェイスブックアカウントより。グラデーションのある青空、立ち上がる雲、こんもりした緑、そして遠目に見える虹!!!これは、恋に落ちてしまう景色だ。 イタリア旅行から戻ってからの動きが早い。会社を辞め、岡山県新見市に移住したのが2011年秋。北海道は函館のご出身で、移住前は首都圏におられたので、西日本は少し縁遠い気がするが、自然豊かな環境に魅了されたのと、ワイン用ブドウを栽培している法人が既にあったということが決め手になったようだ。 2012年には同じ地域にあるドメーヌ・テッタ( → 詳細はこちら)でブドウ栽培の研修を始める。2013年からは畑を少しずつ開墾し、2014年は栃木、2015、16年は長野のワイナリーで委託醸造した。2017年から2020年の間は県内にあるラ・グランド・コリーヌで委託醸造し、収穫以降はブドウ以外に何も加えないスタイルでのワイン造りを確立。 そして、2021年に自社ワイナリーを立ち上げた。ワイン造りを志してから、急ピッチで体制を整えられた保坂さん。年数だけ追っていると順風満帆のように思えるが、目まぐるしい10数年だったに違いない。 合理的な考え方から生まれる自然なワイン造り 保坂さんのワインは所謂「自然派」とカテゴライズされる部類に入るだろう。畑では除草剤は使わず、殺虫剤は使うとしても年に1回程度、農薬も必要最低限の使用に限られる。醸造の過程でも亜硫酸といった添加物は一切使わず、ブドウだけでワインを造っている。...

岡山・domaine tetta
日本ワインコラム |domaine tetta 山道をしばらく登っていくと、突如シャープでモダンな建物が現れた。一瞬「こんなところに美術館?」と思ったのだが、視線を奥にやると一面のブドウ畑が目に入り、ワイナリーだと気付かされる。 ここが今回の訪問先、岡山県新見市哲多町にあるdomaine tettaだ。洗練された空間使いと眼下に広がる一面のブドウ畑を目にすると、海外のワイナリーに来たような錯覚に陥ってしまう。 ▲ domaine tettaのホームページより。ワイナリー入り口からしてスタイリッシュ! ▲ ワイナリーのテラスから見える景色。ばーっと広がるブドウ畑に圧倒される。 そして取材のお相手は、代表の高橋さんと2020年から栽培・醸造長を任されている菅野さん。 高橋さんは泰然自若とした語り口の中に、青い炎のような静かな情熱と強靭な精神を感じさせられる方。一方の菅野さんは誠実で真直ぐな眼差しが眩しく、ストイックと言ってもいいほど真面目にワイン造りに向き合っておられるのがひしひしと伝わってくる。この2人が目指す世界はどんなところなのだろうか? ▲ 高橋さん(左)と菅野さん(右)。短時間のインタビューだったが、信頼関係が垣間見られ、いい関係だなぁ~としみじみ思わされた。 ワインありきでスタートしたのではない まず驚いたのが、高橋さんの家業が新見で代々続く建設業であること!全くジャンルの違うビジネスを経営する二刀流なのだ。でも、なぜ建設業からワインの世界に飛び込んだのだろう? ワイナリーの前に広がる8haの広大なブドウ畑。圧巻の景色だが、少し前までは全く違う姿だった。平成初期に県による造成で出来た生食用ブドウの畑だったのだが、経営していた農業法人が撤退し、20年近く耕作放棄地となっていたそう。ビジネスとして成り立たなかったのは仕方ない。しかし、地元の景色が荒れていく姿を見るのは、やはり辛い…。そういう想いもあり、高橋さんは手を挙げたという。自分がここでブドウ栽培しワインを造る、と。 しかし、なぜブドウ栽培をしたことも、ましてやワイン醸造の経験がない高橋さんが、ワイナリーを造ろうと思ったのだろう?・・・その秘密は畑の環境にある。 ▲ 15年ほど前までは耕作放棄地だったとは信じられないほど、整然と並ぶブドウ畑。 畑の秘密①:日本で珍しい石灰質土壌 畑に足を踏み入れると、白い岩や石が畑のあちらこちらにある。新見市は南北に広がり、場所によって土壌環境が異なる。南に位置する哲多町は、石灰岩と赤土で構成される石灰岩土壌を誇る。石灰質はブルゴーニュやシャンパーニュ地方といったワインの銘醸地に多く見られる土壌で、保水と水はけのバランスが良いことで知られている。日本で石灰を採掘できる場所は非常に限られている上、石灰岩土壌でブドウ栽培しているワイナリーは更に限られる。高橋さん曰く「日本では、domaine tetta以外で1、2社程度ではないか」とのこと。これはかなり貴重な武器である。実は、この土壌環境に目を付け、以前、勝沼醸造がこの地でメルロ、シャルドネ、ピノ・ノワールといった欧州系ワイン用ブドウを栽培していたそう。大手も認めるポテンシャルの高い場所なのだ。 ▲ 化石化したサンゴ礁が隆起したカルスト台地にある畑の土壌には、白い岩や石がゴロゴロと転がっている。畑の中には、雨でドリーネ(石灰岩地域で見られるすり鉢状の窪地)が出来て地表が陥没したところもあるそう。 畑の秘密②:ブドウ栽培に適した環境 以前は生食用ブドウを栽培していた場所というだけあり、ブドウ栽培に適した環境だ。 例えば、「晴れの国・おかやま」と称されるだけあり、降雨量の多い日本の中では、比較的晴れの日が多く、日照時間が長い。また、中国山脈を背に背負う場所に位置し、畑が標高400-420mのカルスト台地上にあることから、寒暖差が生まれ、ブドウの色付きも良く、酸落ちがしにくい。更に、南西に向かう斜面の谷から風が吹くことで、ブドウの熱を冷まし、湿気が溜まりにくい環境にある。 ▲...
岡山・domaine tetta
日本ワインコラム |domaine tetta 山道をしばらく登っていくと、突如シャープでモダンな建物が現れた。一瞬「こんなところに美術館?」と思ったのだが、視線を奥にやると一面のブドウ畑が目に入り、ワイナリーだと気付かされる。 ここが今回の訪問先、岡山県新見市哲多町にあるdomaine tettaだ。洗練された空間使いと眼下に広がる一面のブドウ畑を目にすると、海外のワイナリーに来たような錯覚に陥ってしまう。 ▲ domaine tettaのホームページより。ワイナリー入り口からしてスタイリッシュ! ▲ ワイナリーのテラスから見える景色。ばーっと広がるブドウ畑に圧倒される。 そして取材のお相手は、代表の高橋さんと2020年から栽培・醸造長を任されている菅野さん。 高橋さんは泰然自若とした語り口の中に、青い炎のような静かな情熱と強靭な精神を感じさせられる方。一方の菅野さんは誠実で真直ぐな眼差しが眩しく、ストイックと言ってもいいほど真面目にワイン造りに向き合っておられるのがひしひしと伝わってくる。この2人が目指す世界はどんなところなのだろうか? ▲ 高橋さん(左)と菅野さん(右)。短時間のインタビューだったが、信頼関係が垣間見られ、いい関係だなぁ~としみじみ思わされた。 ワインありきでスタートしたのではない まず驚いたのが、高橋さんの家業が新見で代々続く建設業であること!全くジャンルの違うビジネスを経営する二刀流なのだ。でも、なぜ建設業からワインの世界に飛び込んだのだろう? ワイナリーの前に広がる8haの広大なブドウ畑。圧巻の景色だが、少し前までは全く違う姿だった。平成初期に県による造成で出来た生食用ブドウの畑だったのだが、経営していた農業法人が撤退し、20年近く耕作放棄地となっていたそう。ビジネスとして成り立たなかったのは仕方ない。しかし、地元の景色が荒れていく姿を見るのは、やはり辛い…。そういう想いもあり、高橋さんは手を挙げたという。自分がここでブドウ栽培しワインを造る、と。 しかし、なぜブドウ栽培をしたことも、ましてやワイン醸造の経験がない高橋さんが、ワイナリーを造ろうと思ったのだろう?・・・その秘密は畑の環境にある。 ▲ 15年ほど前までは耕作放棄地だったとは信じられないほど、整然と並ぶブドウ畑。 畑の秘密①:日本で珍しい石灰質土壌 畑に足を踏み入れると、白い岩や石が畑のあちらこちらにある。新見市は南北に広がり、場所によって土壌環境が異なる。南に位置する哲多町は、石灰岩と赤土で構成される石灰岩土壌を誇る。石灰質はブルゴーニュやシャンパーニュ地方といったワインの銘醸地に多く見られる土壌で、保水と水はけのバランスが良いことで知られている。日本で石灰を採掘できる場所は非常に限られている上、石灰岩土壌でブドウ栽培しているワイナリーは更に限られる。高橋さん曰く「日本では、domaine tetta以外で1、2社程度ではないか」とのこと。これはかなり貴重な武器である。実は、この土壌環境に目を付け、以前、勝沼醸造がこの地でメルロ、シャルドネ、ピノ・ノワールといった欧州系ワイン用ブドウを栽培していたそう。大手も認めるポテンシャルの高い場所なのだ。 ▲ 化石化したサンゴ礁が隆起したカルスト台地にある畑の土壌には、白い岩や石がゴロゴロと転がっている。畑の中には、雨でドリーネ(石灰岩地域で見られるすり鉢状の窪地)が出来て地表が陥没したところもあるそう。 畑の秘密②:ブドウ栽培に適した環境 以前は生食用ブドウを栽培していた場所というだけあり、ブドウ栽培に適した環境だ。 例えば、「晴れの国・おかやま」と称されるだけあり、降雨量の多い日本の中では、比較的晴れの日が多く、日照時間が長い。また、中国山脈を背に背負う場所に位置し、畑が標高400-420mのカルスト台地上にあることから、寒暖差が生まれ、ブドウの色付きも良く、酸落ちがしにくい。更に、南西に向かう斜面の谷から風が吹くことで、ブドウの熱を冷まし、湿気が溜まりにくい環境にある。 ▲...