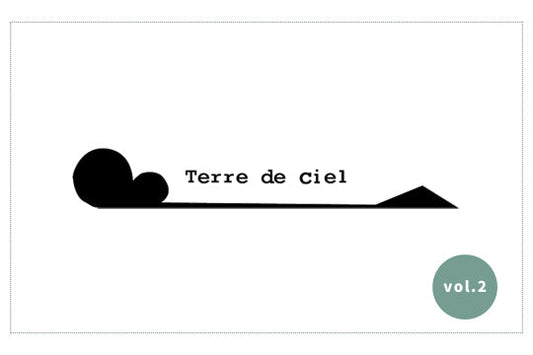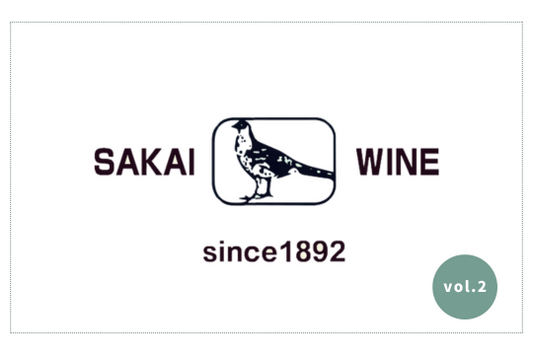日本ワインコラム 北海道・余市 ドメーヌタカヒコ / vol.2 ----- 訪問日:2021年7月20日
前回の訪問からは1年弱の時間が流れたことになる。
コロナ禍という、目まぐるしく変化する状況の中、それに応じて舵取りを迫られるのが一般的だろう。しかし農家にとっては、特に需要に事欠かないスター生産者にとっては、この短い期間における大きな変容というものを予想するのはむずかしい。
「うちは基本的には新しいことには手を出さないドメーヌですからね。」と、やはり心当たりがないような鈍い反応を見せた曽我さんであったが、しかし、これもまたやはり一筋縄ではいかなかった。彼がまず挙げたのは「輸出」だった。

輸出を始めていくことになりました。
とはいっても、大量に出すのではなくピンポイントで、ある程度ブランドの宣伝・構築に役に立つレストランさんに流してもらうようなかたちです。ありがたいことに、たくさんお声もいただいているので、そういったところからブランド構築をしていければと。
その中で、余市の他のワイナリーや中規模ワイナリーも一緒に出していくことが出来るようなシステムを探すこともやっていければいいですね。
「ブランド構築」というビジネスライクな言葉を置くと、シンプルで洗練されたメッセージで海外市場における認知を確立するような、グローバル戦略を思い浮かべてしまう。たしかに「ナナツモリ ピノ・ノワール」と「ジャパニーズ・ウマミ、ダシ」を直列に結び、イメージを最大限流れやすくすることもできるだろう。
しかし、曽我さんがそのようなことを許すだろうか。そのようにはどうにも思えない。
「シンプルで低コスト、かつ忙しい農家でも出来るワイン造り」という曽我さんが掲げる命題と「降水量が多く、肥沃な土壌が広がる土地」という環境から、「ナナツモリ」の味わいを切り離すことはできない。
それは、人的因子と環境因子を複合した、「余市のテロワール」という必須の土台であり、ワインを語るコミュニケーションのバックグラウンドとなるものだ。そして、そのテロワールは世界的にも稀な例であり、国外での理解には長いストーリーが求められるはずである。
ともすれば、曽我さんがそのパイオニアとなることもうなずける。
海外での商売という視点はさておき、余市のワインを語る際の基礎背景を、その伝道師として滔々と語り広めて行くことがミッションであるとすれば、それの適任者は曽我さんしかいないだろう。
なにしろ、曽我さんは話が長い。
失礼しました。
いやむしろ、長大なストーリーを語れるほどに、曽我さんの脳内では「余市のテロワール」がひとつの世界として高い解像度で成立している。
一方で、「余市のテロワール」というものを自身で確立させてきた曽我さんが、主に「人的要因」の文脈で将来に見据えるものがある。

僕たちの世代は「ドメーヌ、ドメーヌ」と言ってきましたが、そこにも良くない側面があって、それは農家が育たないことです。
余市は農家の町ですから、そことのコミュニケーションも重要です。山田くん(山田堂)などは、ネゴシアンをやっていくということで、これからの若い世代には、そういったスタイルでワイン造りを行う子たちも出てくるのだと思います。ワイナリーはやりたくないけれど、葡萄は作りたいという若い子もいますから。そういった動きも応援していかなければいけないですね。
ドメーヌ・タカヒコをはじめ、余市町にワイナリーを構える生産者は多くの場合入植者だ。
元々は果樹生産地であった農業の町だが、離農や高齢化によって耕作放棄地が増え、その隙に入り込む形で次々と姿を現したのがワイン生産者たちである。
近年のワイナリーの断続的な誕生は、地場産業の衰退とセットなのだ。
それを意識した上で、曽我さんは「余所から来た者が内々で盛り上がっても仕方がない。」「自社圃場という小さいスケールで満足し、立ち止まってはいけない。」というような問題意識を募らせているということだろう。
買い葡萄からのワインも一定量作っているとはいえ、ドメーヌであることにある種こだわりを持ってきた彼自身が、広く切り拓いてこなかったもうひとつの道だ。
例えばブルゴーニュもドメーヌ元詰めの潮流が本格化するまでは、ネゴシアンたちの影響が支配的だった。両者の関係性は、ネゴシアンたちが葡萄を買い叩くことで農家を抑え込むという、フェアトレードとは程遠いものに収束し、そこで積もり重なった農家の不満がドメーヌ元詰め運動の引き鉄となる。
このシークエンスはあまり褒められたものではないが、裏返せば、ネゴシアンの元で農家が独立を成し遂げることができるほどの力を蓄えられたと言ってもいい。そして、原料供給より加工品を供給する方が、一般的に利幅が大きいことから、「ドメーヌ化」への参入は広がりを見せる。
ネゴシアンの存在が圧力として作用することを避けて、 公平なコミュニケーションの元に農家対ネゴシアンの関係が成立すれば、日本におけるブルゴーニュ的な産業構造の遷移が起こりうるかもしれない。恐らく曽我さんはそこに期待の目を持っている。
そして、彼が遠くに見る変遷の結末は、彼が実践するワイン造りが、ネゴシアンとの交わりから生まれたドメーヌが、彼のメソッドを少なからず反映することにある。

曽我さんは「農家でもできるワイン造り」を実践することで、ドメーヌ元詰めの動きを活性化しようと試みてきた。そして、次の世代はネゴシアンをすることで農家に力を蓄えさせ、元詰めを始められるような可能性を与える。
このように考えると、原点におけるベクトルは異なるが、双方の収束位置はしっかりと符合している。
ここで、ネゴシアン的な集約の方法は、先述の「余市のテロワール」の否定材料になるというクエッションも可能なのかもしれない。つまり、前回の取材で余市を「大企業がまだ駒を置いていない土地」と評した曽我さんは、ミクロネゴスを想定しているだろう。そこに大きな集約はないし、だから山田堂の志を例にあげるのだろう。
「10年後の構想として、自分のチビ達が20歳になってくるので、20歳を過ぎたら、子供たちがやるにしてもやらないにしても、ワイナリーとして次のステージに移っていくことになる。そのための準備を少しずつやっています。」
まずは、地域の農家のスタンダードであること、というある種ドメスティックな理想を掲げ、生産量を増やす予定も、輸出の予定もないと仰っていた昨年の取材を遍く覆すような形で変化を続けるドメーヌ・タカヒコ。
しかし、他方で今まで自身が試みてきたこととは異なる方向の、10年後におそらく利用可能な、新しい水路を開き、可能性を広げていく。その転換の姿勢には呆気に取られたが、曽我さんの思考にできるだけ同期しようと試みれば、それも彼の広い視野の範疇のように思われた。
そして同時に、そのダイナミックな躍動があるからこそ、曽我貴彦さんは多くの注目を集めて止まないのだろう、と彼の言葉弾幕を浴びた後にズキズキと感じたのだ。

日本ワインコラム 北海道・余市 ドメーヌタカヒコ / vol.1 ----- 訪問日:2020年9月9日
 ワイナリー前の看板。トップワイナリーのオーラが溢れ出す。
ワイナリー前の看板。トップワイナリーのオーラが溢れ出す。
「力強いワインを日本で造る必要はない」
「日本で最も入手困難なピノ・ノワールの生産者が、北海道で探求するのは繊細さ」だ。
 曽我貴彦さん、語りだしたら誰にも止められない。
曽我貴彦さん、語りだしたら誰にも止められない。
はっきりとしたワインを作りたかったら、海外へ行けばいい。日本で造るワインには、日本に固有の味わいや食文化をはじめとした世界観を導入する必要がある。無口な職人と、天文単位ほどの間合いを保った日本ピノ・ノワールの覇者は蕩々と語った。
さて、例えば「水っぽい」という言葉は、日本ワインに向けられる批判的な文句の中で、最もよく聞くものの一つだ。
欧州やニューワールドのような乾燥した気候による「凝縮感」や「力強さ」を求めると、やはり今一つ物足ない。こういった意見は未だ根強く、欧州産地と比べてどうしても多い降水量という泥濘に足を取られて中々前に進めない。
そういった中、雨は克服するべき課題であるのか。力強さにどれだけの価値があるのか。そんな問題提起をするのが曽我貴彦さんだ。
雨が降る環境の中でどういった葡萄・ワインを造るか。どんな方法でも雨を遮った均質的な生育環境は、ワインを均一化してしまいます。灌水が必要なカリフォルニアや、ビニールハウス由来のワインなんて特にそうかもしれない。自分たちがやるべきことは、そうではなくて、雨が降ることによってもたらされる複雑さ、繊細さを目指したワイン造りをしていくことです。
雨が降れば、手間がかかる、病気のリスクが増える、大量生産が難しくなりますが、雨をプラスに変えるような繊細な味わいのワインを、少量かもしれませんが造ることが出来る。その中で高付加価値化していくというのは、これからの時代にあった方向性だと考えています。」
 美しい畑
美しい畑
曽我さんが降水量とともに、ワインへ繊細・複雑な味わいをもたらす要素に挙げるのが、日本の肥沃な土壌だ。
一般に痩せた土壌を高く評価する常識から考えて、葡萄栽培に適していると評されることがほとんどない日本の火山性土壌。日本ワインファンの憧れであり続けるピノ・ノワールは、余市登町の火山性土壌に由来する小高い丘の上に広がる。安山岩を主体とする土壌の中には、土石流によって運搬されてきたと思われる玄武岩がところどころに含まれる。
 風化した安山岩に由来する砂礫に富んだ土壌。
風化した安山岩に由来する砂礫に富んだ土壌。
日本は火山性土壌の土地です。うちの畑も火山性。
その中で、ワインの方向性として石灰岩土壌にシフトするか、火山性土壌にシフトするか悩みましたが、やっぱり火山性を目指すべきかと思っています。
ワインの主要産地であるヨーロッパ諸国には、石灰岩ベースの食文化がある。例えば、ヨーロッパの硬い水、そこから造られる野菜などからは、出汁という食文化は生まれてきませんよね。硬水から出汁はとれない。対して、日本は火山に由来する肥沃な土壌と、柔らかい水、火山性土壌の食文化いうものがあると思います。まずはそういった文化の中で、日本ワインを生かすことを目指していきたい。」
 表土近くには黒い玄武岩の礫が転がる。
表土近くには黒い玄武岩の礫が転がる。
例えばナナツモリ・ピノ・ノワールを含め、日本の土壌が生む出汁のような旨味を持ったワインは、やはり独自の食文化に馴染むような個性を持っている。そういったヨーロッパには中々存在しない味わいの文化が、考え方の基軸となる。
ブルゴーニュが石灰を誇るように、日本の火山性の土壌という無二の存在をポジティヴに捉えていくには、その軸が欠かせない。
 標高約60m。夕刻でも日当たりがいい
標高約60m。夕刻でも日当たりがいい
加えて、曽我さんは、肥沃な土壌で丁寧に育てられた葡萄だからこそ出せる複雑性に目を向けている。
 緩やかな斜面は南を向いている。
緩やかな斜面は南を向いている。
リッチな土壌での栽培は手間がかかりますよね。
樹勢が強くなるからコントロールをしなければならない。
収量が増えるから減らさなくてはならない。
そう言った理由で、痩せた土壌が好まれるのだと思います。肥沃な土壌で葡萄を育てていた人は、おそらく手間がかかるからやめてしまったんです。
でも、育ててみるとどういう葡萄ができるのか、それは不味い葡萄なのだろうか。実際そんなことはなくて、ワインに独特の味わいをもたらす葡萄ができます。
窒素含有量がおおければ、ワインにもアミノ酸が多く含まれるでしょうし、広葉樹林に恵まれた日本の土壌は、ビオディナミなんかで土壌中の微生物を増やすまでもなく、それらに富んでいる。
そういった環境がワインに与える複雑な味わい、そういったものを、テクニカルな情報を含め、紹介して広めていかなくてはならないと感じています。
 畑にはピノ・ノワールのみが植えられる。
畑にはピノ・ノワールのみが植えられる。
新興産地として、アメリカ、オーストラリア、南アフリカなど多くの優れた国々が存在するが、その中で日本のように食文化というバックグラウンドを持つ地域はあまり多くない。
ニューワールドのひとつの欠点は歴史がないことだと思っています。それは、栽培の歴史ではなくて食文化の歴史です。
ヨーロッパには各国に食の深い歴史があって、それがワインと結びつき、テロワールや風土を形成している。移民による多民族国家であるアメリカなどの産地にはそういったものがありません。だから、ワインについても技術や土地のテクニカルな情報をテロワールと称して、市場へアピールしていかなければならない。
では、日本でワインを造っていくことを考えたときどうか。日本には固有の食文化があります。そう言った文化との結びつきを目指して、どのようにワインが育っていくのかということ考えると、誰がテロワールを造るのかという疑問が出てくる。企業なのか、一般人なのか。やはりワインは農作物なので、農家が造るべきなのではないのかと思います。そういった視座にたったとき、農家が造ることができて、かつワインに近いものの例として、味噌・醤油・漬物のようなものがあげられます。
味噌・醤油・漬物。
地元農産物から造られ、地域名産品としてもあげられることが多い食品だ。それらの食品には、農家でも作ることが出来るような再現性の高さという共通項がある。信州から全国へ広がり、その一方で長野県名産品として広く認知される野沢菜は一つの顕著な例だ。
味噌・醤油・漬物の世界観をワインへ当てはめることは、日本の風土論的にもしっくりくることだと思っています。農作物を桶に入れて発酵させるというようなシンプルな手法での加工ですよね。だからこそ、農家であれば誰でも作れる。そして、信州味噌、赤味噌、白味噌が地域ごとに存在して、野沢菜の漬物は何処、奈良漬けは何処といった認知も広がっている。本当は、日本はそういった食文化をAOCとして規定するべきでした。AOC信州味噌を造るべきだっ
たのです。
ともあれ、そういった日本の食文化は、ブルゴーニュのワインがどうで、ジュラがどうだといったフランスの文化とも重なってくる。では、フランスでそれら地域ごとのワインの味を決めたのは誰か。やはり農家だったのではないかと思います。自分たちで葡萄を造って、発酵させて、それが広がっていった。
 ミルランダージュが起こった、粒が不揃いの房がちらほら。
ミルランダージュが起こった、粒が不揃いの房がちらほら。
そういった背景のなかで、僕たちのワイン造りにおける目標は、農家のおじちゃんの息子や孫がワインを作ってくれること。そして、そういった農家が地域に5~6軒できる。それが一つの風土の完成形なんです。
味噌・醤油・漬物の世界観でのワイン造りというキーワードの中で、農家でも造れるワインを目指す曽我さんのワイン造りは、非常にシンプルなものとなっている。醸造所は、ある程度広いものの伽藍洞で、隅に積まれているのは樹脂製のタンク。あとは圧搾機とフォークリフトが中途半端にたたずんでいるのみだ。
農家の人たちが、余市で安定してワインを造れる方法、そして何となくこういう感じのワインなら造れるというスタンダードを示していくことにこだわりを持ってやっています。ワイナリーに来てくださった方に、どうしてこんなにチープな設備なのか。設備を変えればもっといいワインができると言われることもありますが、僕たちにとって、それは次のステップです。まず、しっかりとしたスタンダードを造る、そして、これは究極であってはならない。自分のワインを究極とほめてくださる方もいますが、この究極にはまだ伸びしろがあります。
醸造においても、農家にとって再現性が低いこと何一つやらない。
除梗・破砕は金持ちのやることだから、収穫の全房を樹脂タンクに放り込む。
収穫当日にワインの仕込みは忙しくてできないから、やらない。
収穫のあとには剪定があるから、葡萄をタンクの中に放置する。
忙しいから、澱引きはしない。
澱引きをしたくないから亜硫酸を入れない。農家の視点を最優先し、醸造の常識を尽く覆していく。
 ドメーヌタカヒコのピノノワール
ドメーヌタカヒコのピノノワール
昔はブルゴーニュなんかもそういう世界観だったのではないかと思っているんですよ。ずっと全房で発酵させてきたのに、突然金持ちか現れて除梗を始めて。それが機械化とともに流行して、全房発酵は田舎臭いなんて言われるようになったんじゃないかなと。今後余市でも、除梗を始める人間が出てくるかもしれないけれど、それは次世代の問題としてそれでよくて。
 自社畑には13系統のクローンが植えられている。
自社畑には13系統のクローンが植えられている。
「大企業が、まだ駒を置いていない土地」
曽我さんは余市の可能性をそう評した。
大きな伸びしろを見据えながらも、だからこそ抱く風土の完成という緩やかな理想。ナナツモリ・ピノ・ノワールは、そんな手付かずの土地に打たれた礎となる一手だ。いつか樹脂製タンクと全房発酵という、味噌・醤油・漬物的世界観が成熟し、余市の風土となる時が来ると信じている。だから、ナナツモリを。
はい、…手に入りません…。
予定を1時間以上超え、2時間40分にも及んだ
「曽我貴彦のオール・ナイト・ヨイチ」。
本記事では、その全貌の3割程しかご紹介できていないことと思う。無念だ。
インタヴュー後、幾ばくの電灯もない暗闇に放り出された我々が途方に暮れて仰いだ星空。それほどに雄大な時間があった折、きっと全てを書き起こしたいと思う。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。